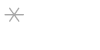三年目の作家、として
1998年 木戸隆行著
六月五日、金曜日
(例えばこのように書き出してみる)
ザー、ザー、ザー……
深夜、土砂降りの雨。アスファルトを叩き付け、滞り、流れ、路面に反射するオレンジ色の外灯。
俺は雨宿りを止め、歩き出す。腕に叩き付ける雨。みるみる濡れ、流れ、指先から滴り落ちる。頬に貼り付く髪。鼻先にぶら下がる滴。
「書くことは、それ自体、既に哲学である」
濡れて縮むスニーカー。シャツの中を流れる雨。夜空を見上げる。闇の彼方から現れる無数の白い雨脚。俺の顔を叩き付ける。叩き付ける。叩き付ける。
近付くヘッドライト。細かな飛沫をあげて通り過ぎる。遠のく真っ赤なテールライト。曲がる。消える。俺はまた歩き出す。
夢を見る。この雨が、世界中の誰をも余すことなく濡らしている姿を。
傘を手に、交差点に立ち止まる女。俺の表面に流れる雨をじっと見つめている。
「抜けるような青空」
女は傘を閉じた。土砂降りの雨。閉じられた傘は、時計の針のように半回転して地面を差した。俺は女を見つめた。
徐々に濡れて萎んでいくその長い髪。雨が当たるたび、僅かに閉じるまぶた。微かな笑みを含んだその口元。形容を越えた、艶やかな唇。いよいよ激しく降り付ける雨。
「全てのものは互いに選び合っている」
女は涙していた。諦めを求めていたかのように。
六月七日、日曜日
早朝の朧光がカーテンを貫いている。俺はタバコを燻らせている。青白いもやに満たされたこの空間に身を委ねながら、俺に寄り添い眠る女の顔を眺める。
口付けによって剥がされ、露になった肌は雨上がりの若葉のように瑞々しい。満たされた寝顔。何を満たされたのか。誰が満たしたのか。
「幸福には神が必要だ、そう言う者がいる」
(そして、物話はいつの間にか継続した存在になっていた。物語のアイデンティティー。思いを馳せれば結末が見えてくる。私は嫌気が差し、その破壊に取り掛る)
女は目を覚まし、ゆっくりと身体を起こした。美しい背筋。そこには黒い翼が生えていた。
女は物憂げに翼を広げ、確かめるように軽く羽ばたいた。俺は知った。女が間もなく飛び去ろうとしているのを。
「空に何が待っていると言うのだろう」
女は窓から身を乗り出し、翼を広げると、俺に背を向けたままこう言った。
「あなたは決して飛べないひと。身重で、翼もない」
(しかし、これは軌道の修正ではなく、リアルのファンタジーへの転換であり、世界の破壊である。私の望まない転化。破壊の方向を変える)
俺は安らかに眠る目の前の女の顔を殴り付けた。何度も、何度も、何度も。
「神は死んだ、神は死んだ、神は死んだ!」
女の顔はみるみる腫れ上がり、赤らみ、黒ずみ、流血した。なおも殴り続ける俺を、女は何の脅えもない瞳で見上げていた。
「私は、愛することしかできない」
(これも私は望まない。更に思いを巡らせ、私はついに回帰する。つまり、書き出した瞬間、それは完結していると言える。私はやむなく定められた流れに沿って、また書き始める)
女は俺の愛撫にゆっくり目覚めると、徐々に強まる光に身を起こし、その滑らかな背中を影にした。
柔らかな逆光の中の、しなやかな流線型。女は導かれるように立ち上がり、カーテンに手を掛けた。
「朝って、やって来るものなの、それとも……」
女の影が止まった。細く開かれたカーテンの隙間から差し込む朝日に、タバコの煙が揺れている。影が振り返った。
「ねえ、どう思う?」
(女が人格を持ち始めた。男にも人格を持たせることにする。それは世界の開化と閉鎖とを意味する)
「ああ……ナナのように、きっと」
ナナはまたカーテンの外に目を戻した。
ベッドの下でしわくちゃに絡まり合った二人の服。波打つシーツが残したナナの跡。朝の光はいつもこのように俺たちを迎え、そして葬るのだ。
六月十二日、金曜日
(この日付けは節である。何故、私はこのように節を作らなければならないのであろう、いや、何故作っているのであろう。節の必要性。それは章も然り、段落も然り、更には句読点にすら言える。何故。
それを知るために、比較的容易なところで、句読点を省いて進めてみる)
「見ろよあのシトロエン」と俺が言うとナナは無防備にコーヒーを口にしながらそれを横目で見てそのカップを包むナナの指の一本一本が清楚でナナは「私日本車は嫌い同じ部品をいろんな種類に使い回しているから」と言ったから俺は「それはどこの国でも同じだ」と答えるとナナは視線をテーブルに落としてカップの口に残ったコーヒーをその清楚な指で拭くと「でも日本車とシトロエンは違うわ」と言った
(これはこれで面白いが、部分的に使われることに限って成立するものである。これが百ページ、二百ページと続けば読者は疲れ果て、イメージを受け入れられなくなるであろう。
次に、句読点を入れてみる。まず、その句読点間に出来る限り語句を詰め込み、出来る限り句読点量を少なくする方法で試みる)
オープンテラスのカフェから見える銀杏の並木が悶えるように風に揺れている。漏らすように俺が吐き出した煙草の煙の中で小さくなるブルーのシトロエンを横切り、目前の歩道を男たちが笑みを浮かべて走るように歩き日傘を差した女たちが這うように歩く。
「幸福を求める人種」
いつまでもカップの縁を辿り続けるか細いナナの指を強く握り締めた俺の手を、ナナは諦めに似た優しさで見つめていた。
「人間社会の生態系」
俺はナナの手を引き寄せ口に含んだ。それはもちろんナナの指を噛み砕くためでも飲み込むためでもなく、俺の腕の間にナナの頭が入る空間があるように俺の口の中にナナの指を入れる空間があるからなのだ。
(次は、句読点間を出来る限り狭め、出来る限り多量の句読点を入れてみる)
「赤って、何の色だと思う?」
舌、で、感じる、ナナ、の、か細い、指。柔らかな、指。滑らかな、指。滑らかな、爪。冷えた、指。
「花、果実、夕日、血」
満たされず、強く、噛んだ。一瞬、顔、を、歪め、遠く、を、見つめた、まま、の、ナナ。
「口紅、マニキュア、私のライター、唯則のサングラス、それに……」
舌、で、感じる、ナナ、の、血液。温かな、血液。それは、愛、の、連環。鉄、の、連環。俺、は、舌、を、噛み、ナナ、の、愛、と、混ぜ、合わ、せ、戯れ、た。
「春の、雪」
(以上の試みの結果、私はこう感じるに至った。文章には適度な区切りが必要である、と。それは論理的にはどのように考えたらいいであろうか。私は、こう考える。
人間は全てを、世界を、つまり時間と空間とを無数の部分に断絶させ、記憶するものとしないものとを取捨選択して捉えている。継続ではなく、断絶させている。
何故ならば、全てを記憶するには、人間の記憶の容量が、あまりにも小さいからである。
そして、人間は効率的に記憶を呼び起こすために、その選ばれた全ての部分を秩序正しく分類し、保存しているのである。
例えば、人はある一日の出来事を思い出すとき、生まれてからその日までの全ての記憶を順序よく思い出してからその日の出来事に辿り着いたりしない。また更に、その一日の一出来事を思い出すのに、朝目覚めてからのその日の全ての記憶を思い出したりしない。
つまり、章や節や段落や句点や読点は、人間の年、月、日、時刻などに相当するのであり、それは記憶の単位なのである。であるから、人間に向かった伝達には、このような区切りが必要とされるのである。そして、その区切る間隔は、人間の区切るリズムに近ければ近い程よいと言える。
では、一体、そのリズムとはどれぐらいの長さのものなのであろうか。私が直感的に感じたところでは、理性的な長さ、感覚的な短さ、である。
しかし、それは人によって様々であるかもしれないし、そうではないかもしれない。同一の人でも、朝と夜では違うかもしれないし、そうではないかもしれない。気分によっても然りである。
だが、これだけは言える。それはゼロではなく、無限大でもない、と。そして、正確に知ることのできるその基準となるリズムは、自らのリズム以外にない、と。
つまり、作者は、常に自らのその一語、一文、一段落、一節、一章における意図と流れを視野に置き、検分しながら書き進めるべきなのである)
テーブルから伸びるコーヒーの湯気。ナナの指を流れる赤。テーブルから伸びる煙草の煙。俺の口に広がる赤。そして俺は、分かたれることを恐れるように、ナナの頭を抱き寄せた。
「未消化な理性」
路面に照り付ける日差し。単一な空の青。ざわめく緑。流れる赤。遠く見つめるナナの瞳に映るそれら全ては、分かたれ、統合された。
「私、綺麗な洋服が好き」
鏡の前でスリップドレスを合わせるナナの眼差し。
「着飾ることがどうして嘘になるの? 本当の姿は裸だけなのに」
俺の足。ナナの脚。俺の腰。ナナの腰付き。俺の広げられた掌。ドレスを肩に合わせるナナの指。ナナが振り返った。
「何て言われても、モルガン」
(何の前ぶれもなく、今度は節を省いてみた。やはり混乱を招くだけで切り替えがうまく行われないことが証明されたように思う。そして、この問題を解消するためには、節に相当する説明が必要であろう。
しかし、その移行方法が読者をこの世界から隔離させてしまうであろうことは容易に推察される。何故なら、先に述べたように、人間は世界を断絶させる存在なのであり、出来事の繋ぎというものはただ言語上にのみ存在するからである。
改めて提示する。「私、綺麗な〜」から、次に示される節であった)
六月十五日、月
ナナが首を傾けた。事実、そのドレスがナナの脚の、腰の、胸の、肩の、腕の美しさを際立たせることは明白だった。微かに滑り降りたナナのブレスレット。
「表象は本質の一部である。本質の、一部である」
俺はナナの腕を掴み、試着室に引き込むと、その美しさを手荒く称賛した。脚を、腰を、背を、胸を、腕を、肩を、首を、そして、艶やかに光る唇を。
激しい愛撫にナナは瞳を閉じ、吐息を漏らした。美へのためらいを捨てた女として。
「可能的自己を制限する人種」
カーテンが波立つ。力の抜けたナナの膝が鏡でうごめく。透き通ったナナの首筋。
「お客様、いかがですか」
外から女の声がする。ナナの耳を噛みながら手を伸ばし、一気にカーテンを開くと、眩しいほど純白の空間が飛び込んだ。
色彩を手に取る疎らな人影。貼られた大きなモノクロ写真。ギョッとした店員の顔。俺はその手にドレスを差し出す。
「これ」
かがんでサンダルを履き直すナナ。
「それと、あの帽子」
俺が指差した方を見上げ、振り返ってナナは微笑んだ。
店を出て、夕闇の並木道を歩く。空を覆う漆黒のケヤキ。古アパート。すれ違う人影。楽し気に帽子を被り、跳ねるように歩くナナ。振り子の買い物袋。
「自己は自己を自己が自己に表現したものによって知る。例えば胸の締め付け」
立ち止まって煙草をくわえた。植え込みに紛れたビニール袋。痩せこけた土。掌を照らし出すライター。靴底で削れる小石の感覚。夕闇に一点の火種。溢れ、流れ出す白煙。
ナナの赤らんだ踵がヒールの上で僅かに上下する。ナナのふくらはぎが僅かに隆起する。スカートの裾が僅かにはためく。流れる煙。後ろ手に持たれた紙袋。流れる煙。帽子の後ろ頭。流れる煙。夕闇。流れる煙。
「歓喜と幸福とは同義か」
古びた公衆トイレ。古びたコンクリートブロック。俺が手を引くと、ナナは理解した。黒光りしたコンクリートの床。小さな穴に流れ込む汚水。錆び付いたノブを引き、ナナが入り、俺が続き、錆び付いた鍵を掛ける。
「憲法第九条を改正せよ」俺が、か。どのように、だ。「セックスフレンド募集中のりこ」男の字で、か。今でも、か。「貴基殺す」宣言、か。俺に、か。
ナナの鼻唄。ナナの黒い下着。ナナの背中。すらりと伸びたナナの脚。俺は煙草を踏み消した。靴から伸びる呻くような煙。ナナの鼻唄。肌を滑り降りたドレス。ナナが振り返った。
「どう?」
露になった繊細な肩。控えめな胸の膨らみ。美しい腰の流線。裾から伸びる艶やかで悪戯な脚線。
「これ以上は、あり得ない」
「本当?」
ナナが微笑した。やはり、あり得ない。俺はナナが脱いだ服を掴み、小さな四角い窓から投げ捨てた。
「愛において、全ては真実だ」
翻りながら舞い落ちる二切れの抜け殻。ちらつく青白い蛍光灯。ドアを開け、伸びやかに道に出るナナ。はためくドレス。ストラップ。暗闇に近い夕闇。
「ナナ」
ナナの振り返り、問う仕種。
「アルファロメオに乗ったこと、あるか?」
首を横に振るナナ。赤く点滅するパーキングメーター。
「じゃあ乗ろう」
ナナは俺の目線の先を追い、微笑んだ。ウインドウの向こうに見えるステアリング。微かに見える、差し込まれたままのキー。赤く点滅するパーキングメーターの数字。
7、7、7、ナナ。
ドアを開き、キーを回す。夜空に抜けるエンジン音。高鳴る。助手席で笑うナナ。美しい脚。ステアリングを右に切り、アクセルを踏み込むとウィールが叫んだ。
「それはあたかも回答の後に作られた問題のように陳腐だった」
六月十八日、木
青山通り。テールランプの帯。黄色に変わる信号。高速三号を流れる光。
「夜の道って、どうして寂しいの……こんなに車が繋がっているのに」
「道とは誰かが通り過ぎた跡のことだ」
「こんなに人も歩いているのに」
「いつまでも辿っている」
「青」
「解放、脅迫」
「ラジオ、かける?」
「ああ」
「……There’s not one day that goes by
That I don’t cry for you
There’s not one day that goes by
That I’m not singing the blues
There’s not……」
「歌声。美しい歌声。ナナの美しい歌声。俺のナナの美しい歌声。日本人の俺のナナの美しい歌声。人間の日本人の俺のナナの美しい歌声。生物の人間の日本人の俺のナナの美しい歌声。存在が有の生物の人間の日本人の俺のナナの美しい歌声。246」
「唯則……」
「こんなスピードじゃアルファロメオが台無しだ」
「綺麗な人……」
「ナナ……」
「人はいつまで愛を持っていられるの?」
「死ぬまで。人はいつから愛を持っている?」
「愛から生まれるの」
「エロスからだ。明治通り。寿命とは?」
「何も知らないの……」
「楽しい話をしよう。例えば……」
「ライター貸して?」
「煙草をくわえる、ナナの柔らかな唇。ライターを握る、しなやかな指。照らし出される、透き通った首筋。煙に包まれる、憂いのある瞳。美しい」
「褒めることが、楽しいの?」
「美しさを見出す自分の美しさが、だ。見ろ、後ろのシートに財布がある」
「東京って言葉、使ったことある?」
「ない。青山、広尾、恵比寿、代官山。狭い世界。幾ら入ってる?」
「いち、に、さん……ファイブ、シックス……ナフ、ディス……分からない……」
「じゃあ捨てろ」
「優しい言葉が好き……ねえ、飛んで行く」
「紙、痛み、喜び、時間、紙。空に放してやれ」
「もっと」
「自由!」
「もっと」
「不自由!」
「そう……」
「人を不自由にするのは人、人から自由を欲するのは人」
「だから……ねえ、いろんな声が聞きたい」
「愛、愛、愛」
「高さだけ?」
「愛、愛、愛」
「ふざけるだけ?」
「愛、愛、愛」
「かすれるだけ?」
「愛、愛、愛」
「息を吸いながら……他には?」
「ない。三の四乗……八十一……十分だろ?」
「足りない……足りるはずがないの」
「でも飽きる」
聳え立つウェスティンホテル。アスファルトを点滅させるハザード。目を落とすナナ。ドアを開くと漆黒の夜空が高く澄み切っていた。
六月二十三日、火
(先日、友人に「日本語をみがく小辞典」なるものをお借りした。それは〈名詞編〉、〈動詞編〉、〈形容詞・副詞編〉の三編に分かれていて、学浅い私にとって少なからず開眼させるものであろうことが予想される。
だが、私自身の経験上、それについての思考を何もしていないところに知識を持ち込むと、つまり今の状態なのだが、全否定か全肯定しか行われず、補足や修正など、私の考える知識の有効利用が行われないことが多い。
それは、言い換えれば、私の中に私以外の者だけで作られた言語理論の土台が築かれ、或いは、私がその理論以外のものだけで土台を築いてしまい、その本来の理論の姿への修正に費やす膨大な時間が必要になるという滑稽な事態が生じることが多いのである。
であるから、私はこの絶好の機会に、時機早尚を承知の上で、矛盾や誤謬や無意味を可能な限り避けることに注意を払いつつ、その理論の構築を試みようと思う)
吹き抜けの天井で回転するいくつもの巨大なプロペラ。メガレストラン。ナナが口にしているアプリコットクーラー。俺の節榑立った手。似合いのジョッキ。蒸し暑い。
「東京湾の水と多摩川の水って、どっちが綺麗なの?」
「それは透明度のことか、毒性のことか、美的感覚に訴える度合いのことか?」
狭苦しい後ろのテーブルから聞こえる声。
「……あなたらしくない、って。頭に来たから、私、こう言ったの。私は私なのに?」
ナナの向こうの狭苦しいテーブルから聞こえる男の声。
「……あいつに笑われたのは、辛かった」
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。
「私に、何ができるの?」
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。
「私は、何をすればいいの?」
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。
「私は、何がしたいの?」
(まず、私が構築したい理論とはどんなものなのか考える。だが、すぐには明確に規定できないので、消去法で限定してみる。
第一に、それは品詞の区分を規定するものではない。例えば、一般にこれは名詞だと区分されているものを、動詞だと主張するためのものではない。そこには従う。
第二に、活用を規定するものではない。例えば、か、き、く、く、け、けの五段活用をく、く、け、か、こ、き、き、かの変則八段活用にすることを主張するものではない。そこには口語、文語などの使用条件や効果を除き、従う。
第三に、仮名遣いや送り仮名を規定するものではない。例えば「動く」を「う動く」だと主張するものではない。そこには従う。
第四に、それは日本語を放棄するものではない。寧ろ、日本語の可能性を探るものである。だが、それは日本語のみに留まることを意味しない。あらゆる言語記号の表現における可能性の探求である。
以上が短時間で思い浮かんだ条件であるが、これらだけでは不十分であることは痛切に確信している。
だが、少なくとも私にとってそれ以上はあり得ない理論であると言える条件は、私の死をもって初めて満たされるのであり、生前に、しかもここに理論構築を図りそれを記そうとする以上、不足はやむを得ないものとしなければならない。
しかし先に述べたように、これは構築作業の完了を宣言するものではなく、過程であり、経過報告である。そのことを読者であるあなたにも、後の私自身にも理解して頂きたい。
ある種、言い訳がましい前置きが長くなったが、上の四条件から自らの中に思い描かれた構築したい理論の内容は以下の通りである。
第一に、語の意味が成立する可能性とその効果である。
第二に、語の順序或いは反復の効果である。
第三に、表記法や語尾の効果である。
第四に、語と語の繋がり、主語と述語と修飾語の関係、そして語の量の効果である。
つまり、規定よりも効果の分析である。さらに、一語の理論から一文、一段落、一節、一文章へと視野を広げて行きたい。
第五に、文と文との繋がりの可能性、或いは広げて段落、節、章、同士の繋がりの可能性、つまり、文章の成立の可能性とその効果である。
第六に、語と語、文と文、段落と段落、節と節、章と章との間の描かれない部分、或いは空白の効果である。これは書かないものの効果である。
第七に、文章の量の効果である。
第八に、文章の流れの効果である。
第九に、描写とその効果である。
第十に、題名の効果である。
以上、私自身が寒気を催すような目標を掲げ、それらを僅かでも明らかにすることにより、ある語や文、さらに段落、節、文章の目的に沿った効果的な使用が可能になるのではないか。
しかし、これらを規定して行くために使用する判断理由、つまりこの理論を形成する公理というものが先立って規定されなければならない。まずそれを示そうと思う)
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。長いナナの髪の毛先が頬で揺れていた。繊細なナナの肩が震えていた。
「愛し合おう、愛さなくなるまで」
ナナの唇が艶やかに微笑した。
「直感は非言語的思考過程から出された結論である」
ナナは立ち上がり、身を乗り出し、俺に口付けた。倒れたグラスから伸びる水の膜。
「私、ゴダールの映画が大好き。優しくて残酷、現実的で非現実的、恐ろしくて滑稽。見つかった! 何が? 永遠が!」
振り向いて歩き、吹き抜けから階下を見下ろすナナ。悪戯に曲げられた片脚。奏でられるアコーディオン。ナナの鼻唄。回るプロペラ。人いきれ。
俺は煙草に火を点けた。
「だから俺は自分に感謝し、恨まずにいられないんだ」
ナナの美しさが弾んでいた。
六月二十四日、水
(では、公理を求める。まず、私が先に挙げた理論構築を目指す目的、を明らかにする。
それは、私が最上の文物芸術作品の実現を目指すからである。
次に、芸術とは何であるか、を明らかにする。
芸術とは、表現者がある間接的な手段を通じて感受者にその内部からある感覚をもたらすもののことである。
間接的な手段というのは、彫刻であり、絵画であり、音楽であり、そのような物を通じて伝達する手段のことであり、直接、感受者に触れたり叩いたりする手段ではないことを示している。そのような直接的な手段を通じて伝達するものは芸術ではなく現実である。
内部からある感覚をもたらすというのは、現実に物理的に存在する姿とは違うものを感受者に知覚させることである。
例えば絵画で言うならば、白い花が描かれている絵によって、白い花だけではなく、例えば美しさであり、切なさを知覚させるものである。それは外部から直接与え得るものではなく、感受者の内部から引き出すものである。
次に、内部から引き出すことのできるものとはどんなものであるか、を考える。
それは最低限、時間的広がりと空間的広がりとを持つもの、つまり世界を持つものである。しかも感受者に自分自身がその世界にいると感じさせるような世界である。
何故なら、感受者の内部からある感覚を引き出すためには感受者自身がそのものに働きかけなければならないのであり、その働きかけとは描かれていない部分の時間的、空間的広がりを埋める行為に他ならないからである。
そしてその埋める行為によって作品と同化した感受者は、その作品中の世界において、現実世界で知覚するような、ある感覚を生々しく覚えるのである。
次に、どのようにして芸術の優劣を決定するのか、を明らかにする。
芸術の優劣は、感受者にもたらされた感覚の種類の数とその強度との積で決まる。
以上のことから、最上の文物芸術作品とは何であるか、を結論する。
最上の文物芸術作品とは、表現者が言語を手段として世界を構築し、感受者の内部に、先に示した積が最大となる、ある感覚をもたらすもののことである。
では、その実現のためには何が必要であるか。
それには最低限、言語を効果的に伝達する力、つまり表現力が必要である。つまり、言語理論の構築が有効である。そして、もたらすべき感覚を常に明確に見据えながら文を構築する力が必要である。
以上のことから、言語理論を構築するに当たっての公理を示す。
それは感受者が知覚できる効果でなければならず、しかも目的の達成に対して役立つ方式で言及されなければならない。その最上の目的は感受者にもたらそうとする感覚であり、そこから下って世界、描写と枝葉に分かれて行くのである)
高く澄み切った夜空。並木に降り注ぐ月光。ベンチに座るナナ。通りを疎らに過ぎるハイヤー。向かいに見える高層ビル。黒光りしたセンチュリーが停まる。
ドアを開く運転手。窓の明かりが疎らなマンション。帽子を被るナナ。白く高い月を見上げたナナの帽子。俺は煙草に火を点けた。暗がりに際立つ一点の赤い光。細く立ちのぼる煙。
「ナナ……何をしたい……愚かな問い」
通り過ぎるハイヤー。立ったまま、帰りを待つ運転手。澄み切った夜空。ベンチに座るナナ。帽子。肩。
「ナナ」
「ねえ……私がこれから話すこと、聞かないで……私、唯則に伝えたくて話すんじゃない、唯則に向かって話したいだけなの」
ナナが振り向いた。優しい瞳。寂しげにほころんだ口元。立ちのぼる煙。
「赤と青と緑なら、私は迷わず赤を選ぶの。でも、そこに黄色が入ったら、私はいつまでも迷って選べない。だって、そこから先は確かにあって、でも触れられなくて、いつまでも続くから」
立ちのぼる煙。立ちのぼる煙。立ちのぼる煙。
「自己批判なんて不可能だ」
「聞かないでくれて、ありがとう」
「嘘だ」
煙草を月に投げ捨てた。赤い光の点が放物線を描いた。ナナを抱きしめた。柔らかく、滑らかで、繊細で、美しい。俺の背中で広げられたナナの手の感触。
「明日はきっと晴れるね」
ナナの透き通った首筋。
「初めて聞いた」
ソワソワ立つ運転手。腕時計に目を遣った。
「ナナ」
背中でなぞられる「?」
「センチュリーに乗ったこと、あるか?」
左右になぞるナナの指先。駆け出す運転手。駆け込む入口に「TOILET」
「じゃあ乗ろう」
上下になぞるナナの指先。手を繋ぎ、歩き出す。軽やかに絡み合う指と指。弾んで渡る大通り。ドアを開け、ナナを乗せる。
今度は俺が白手袋。ゆっくりアクセルを踏み込んで、ヘッドライトがセンターラインを照らしたとき、後部座席のボスが笑った。
「海岸へ!」
六月二十五日、金
(第一、語の意味が成立する可能性とその効果について。
まず、語は意味を表し得るだろうか、と問うてみる。だが、それを述べる事自体、既に意味が成立することの証明になっている。より強く言えば、この語を私が書き、あなたはただこの語のみによって理解しているのだから、語の意味は成立していなければならない。
だが同時に、私たちはそのものが語であるということは理解できても、その語が何を意味するかを理解できないことがある。意味を知らないものを語と認識するとはどういうことか。
それは、私たちが意味を知っている語からの表象上の類推に他ならない。
では、その表象上の記号から意味を理解することは、どのようにして可能になったのであろうか。
それは連合、言い換えれば条件付け、例を挙げればパブロフの犬のような条件付けによってである。
人の言語は音から始まる。ある物を見たときにある音を聞き、それが度重なると、そのものを意識することがすぐにその音を呼び起こすような連合が起こる。
そして次に、その音と同じものを表す記号とを連合させ、ついに、記号とそのものとは観念の中で結合する。つまり、観念が記号を呼び、記号が観念を呼ぶようになる。
そしてそれが物体にだけではなく、動作や状態、感情、思想にまで達し、細分化し、より正確に伝達し、受け取ることが可能になるのである。そして更に、その語同士を自由に結合することが可能になれば、現実にはあり得ない、またあり得なかったものを生み出すことが可能になるのである。
ただ、ここで不可解なのは、私たちが意味を記号から直接受け取るのではなく、一旦音に換えてから受け取っているということである。そして思考も、音によって行われているということである。これは何を意味するか。
私が思うに、それは頭の中でそれが意味する像を描くこととその現実の記号を視覚的に知覚することとは、同時に行い得ないからではないであろうか。
試しに、次の言語を意識して見ながらそれが意味するものをイメージできるか、やってみて欲しい。
「星空」
次に、それを音に変換して、その音を意識しながらイメージできるか試して欲しい。どうであろうか。結果は明白ではないであろうか。
では、ここから何を導き出すことができるか。
それは、私たちの脳内で、映像を想像する部分と現実の映像を知覚する部分とは、恐らく同一の部分であるということである。
つまり、私たちが情景を表す文を見ながら同時にその情景を想像することはできないということになり、であるから、読み急がせる文章は、想像させる空間が狭くなる、または粗くなる、と言うことができるのである。
より簡潔に言えば、時間と空間とは反比例するのである)
ボスの指令はこうだった。
「第一京浜から羽田線へ」
バックミラーの中のボス。艶やかに伸びる脚を組み、煙草を燻らせている。俺の握るステアリングの向こうには、宙に浮かんだ外灯が、どこまでも伸びている。澄み切った星空を滑走路が貫いている。
「トゥルルル、トゥルル、トゥルル」
電話の音。
「トゥルル、トゥルル、はい……ああ、ああ……」
受話器を手に煙草を吹かすボス。窓の外に広がる星空に目を遣り、微かに溜め息をつく。
「……明日から君の席はないと思え」
受話器を置くボス。
「いかがなされました」
「ああ……私が今、多くの人間を少しずつ奴隷にしている……つまり、私を奴隷の主だ、と言っていた……」
煙草をもみ消すボス。
「だから、私は悪だ、と……停めろ」
路面を点滅させるハザードランプ。車を脇に止め、俺はボスのドアを開ける。ボスはその艶やかな脚を路面に下ろすと、ゆっくり立ち上がり、俺に抱き付いた。
「……助手席が、いい」
(次に、有限である語の種類によって無限である事物の種類を表すことが可能であるのか、可能であるならば、どのような方法によってであるか、を考える。
言語の伝達が可能であるということは、特殊が普遍を持つということである。言い換えれば、他の人間と同一ではない一個人が他の人間が持つものと同一な道具を持つということである。
それは必然的に、一語が完全に限定されたある事物のみを表すのではなく、類似した他の事物をも表すものでなくてはならないことを意味する。端的に言えば、事物そのものではなく、事物がもつ性質を表すものでなくてはならないことになる。
何故なら、例えば、私が今行っている「考える」ということとあなたが今行っている「考える」ということとが全く同質のものであるということは証明できないのであり、更に言えば、私が今行っている「考える」ということと私が過去に行っていた「考える」ということとが同質ではないのであり、言語が完全に限定されたある事物のみを表すのであれば、それぞれに別の名称が与えられなければならないからである。
だが、実際にそれぞれに別の名称を与えてしまえば、言語の種類数は天文学的数値に上り、更に果てしなく増殖してしまう。そしてそれらが普遍性を持たないことは明白である。
では、どのようにしてそれを解決するのか。いや、実際にどのように解決しているのか。
それは有限個の語同士を組み合わせ、組み合わされたものを一つの意味として伝達することにより、その種類数を増やそうというものである。それだけではない。そこに文脈によって形作られた状況をも組み込むのである。
例えば、今ここで私が「私たち」と言えば、それは全ての人間を表すが、ナナが「私たち」と言えば、それはナナと唯則のことを表す、というように。
こうして、私たちは有限個の言語によって無限個の事物を言い表すことに限りなく近付くことができるのである。
だが、そこには必ず類推の弊害が付きまとうことを忘れてはならない。具体的に言えば、説明不足、意味の取り違い、深読み、などである。
これらのような弊害に常に気を配りながら、私たちは書き、かつ、読み、また、話し、かつ、聞くべきであろう)
助手席に座り、鼻唄を歌うナナ。流れる外灯。星空。ナナの鼻唄。目の前に割って入るテールランプ。星空。バックミラー。静寂。ナナの鼻唄が消えた。
「私……もう、唯則のこと、愛せない」
流れる外灯。真っ直ぐ前を向き、呟くナナ。
「もう、好きじゃないの」
流れる外灯。
「その話し方が好きじゃない」
流れる外灯。
「そのハンドルの握り方が好きじゃない」
流れる外灯。
「その目も、その鼻も、その口も、その表情も、一度に好きじゃなくなったの」
俺はブレーキを踏み付けた。叫ぶウィール。暴れる挙動。暴れる挙動。叫ぶウィール。暴れる挙動。暴れる挙動。暴れる挙動。澄み切った星空。
「……だったら、降りろ」
「やっぱり……」
俺は顔を上げた。ナナの寂しげな瞳が俺を刺していた。
「唯則は私の言葉しか見ていない……」
ナナの口が歪んだ。一気に頬を伝った一筋の涙。赤らんだ華奢な鼻。鋭い顎にぶら下がり、小刻みに震える涙の滴。
「嘘だったのか」
「う……そ……?」涙の滴が千切れ落ちた。「……分かった……私、もう本当のことしか言わない……それも……思ったこと全部言葉にしてあげる!」
口を結び、前に顔を逸らすナナ。
「そんなことできるはずがない。できるならナナの中身が全て言葉でできていることになる。できるはずがない」
ナナがまた振り返った。
「できるわ!」
俺はまたアクセルを開けた。スピードが上がる。流れる外灯。「煙草が吸いたい」と言って火を点けたナナ。限りなく澄んだ星空。緩やかなカーブに合わせて回る俺の白手袋。
それは、既に存在の手錠を嵌められていたのだ。
(例えばこのように書き出してみる)
ザー、ザー、ザー……
深夜、土砂降りの雨。アスファルトを叩き付け、滞り、流れ、路面に反射するオレンジ色の外灯。
俺は雨宿りを止め、歩き出す。腕に叩き付ける雨。みるみる濡れ、流れ、指先から滴り落ちる。頬に貼り付く髪。鼻先にぶら下がる滴。
「書くことは、それ自体、既に哲学である」
濡れて縮むスニーカー。シャツの中を流れる雨。夜空を見上げる。闇の彼方から現れる無数の白い雨脚。俺の顔を叩き付ける。叩き付ける。叩き付ける。
近付くヘッドライト。細かな飛沫をあげて通り過ぎる。遠のく真っ赤なテールライト。曲がる。消える。俺はまた歩き出す。
夢を見る。この雨が、世界中の誰をも余すことなく濡らしている姿を。
傘を手に、交差点に立ち止まる女。俺の表面に流れる雨をじっと見つめている。
「抜けるような青空」
女は傘を閉じた。土砂降りの雨。閉じられた傘は、時計の針のように半回転して地面を差した。俺は女を見つめた。
徐々に濡れて萎んでいくその長い髪。雨が当たるたび、僅かに閉じるまぶた。微かな笑みを含んだその口元。形容を越えた、艶やかな唇。いよいよ激しく降り付ける雨。
「全てのものは互いに選び合っている」
女は涙していた。諦めを求めていたかのように。
六月七日、日曜日
早朝の朧光がカーテンを貫いている。俺はタバコを燻らせている。青白いもやに満たされたこの空間に身を委ねながら、俺に寄り添い眠る女の顔を眺める。
口付けによって剥がされ、露になった肌は雨上がりの若葉のように瑞々しい。満たされた寝顔。何を満たされたのか。誰が満たしたのか。
「幸福には神が必要だ、そう言う者がいる」
(そして、物話はいつの間にか継続した存在になっていた。物語のアイデンティティー。思いを馳せれば結末が見えてくる。私は嫌気が差し、その破壊に取り掛る)
女は目を覚まし、ゆっくりと身体を起こした。美しい背筋。そこには黒い翼が生えていた。
女は物憂げに翼を広げ、確かめるように軽く羽ばたいた。俺は知った。女が間もなく飛び去ろうとしているのを。
「空に何が待っていると言うのだろう」
女は窓から身を乗り出し、翼を広げると、俺に背を向けたままこう言った。
「あなたは決して飛べないひと。身重で、翼もない」
(しかし、これは軌道の修正ではなく、リアルのファンタジーへの転換であり、世界の破壊である。私の望まない転化。破壊の方向を変える)
俺は安らかに眠る目の前の女の顔を殴り付けた。何度も、何度も、何度も。
「神は死んだ、神は死んだ、神は死んだ!」
女の顔はみるみる腫れ上がり、赤らみ、黒ずみ、流血した。なおも殴り続ける俺を、女は何の脅えもない瞳で見上げていた。
「私は、愛することしかできない」
(これも私は望まない。更に思いを巡らせ、私はついに回帰する。つまり、書き出した瞬間、それは完結していると言える。私はやむなく定められた流れに沿って、また書き始める)
女は俺の愛撫にゆっくり目覚めると、徐々に強まる光に身を起こし、その滑らかな背中を影にした。
柔らかな逆光の中の、しなやかな流線型。女は導かれるように立ち上がり、カーテンに手を掛けた。
「朝って、やって来るものなの、それとも……」
女の影が止まった。細く開かれたカーテンの隙間から差し込む朝日に、タバコの煙が揺れている。影が振り返った。
「ねえ、どう思う?」
(女が人格を持ち始めた。男にも人格を持たせることにする。それは世界の開化と閉鎖とを意味する)
「ああ……ナナのように、きっと」
ナナはまたカーテンの外に目を戻した。
ベッドの下でしわくちゃに絡まり合った二人の服。波打つシーツが残したナナの跡。朝の光はいつもこのように俺たちを迎え、そして葬るのだ。
六月十二日、金曜日
(この日付けは節である。何故、私はこのように節を作らなければならないのであろう、いや、何故作っているのであろう。節の必要性。それは章も然り、段落も然り、更には句読点にすら言える。何故。
それを知るために、比較的容易なところで、句読点を省いて進めてみる)
「見ろよあのシトロエン」と俺が言うとナナは無防備にコーヒーを口にしながらそれを横目で見てそのカップを包むナナの指の一本一本が清楚でナナは「私日本車は嫌い同じ部品をいろんな種類に使い回しているから」と言ったから俺は「それはどこの国でも同じだ」と答えるとナナは視線をテーブルに落としてカップの口に残ったコーヒーをその清楚な指で拭くと「でも日本車とシトロエンは違うわ」と言った
(これはこれで面白いが、部分的に使われることに限って成立するものである。これが百ページ、二百ページと続けば読者は疲れ果て、イメージを受け入れられなくなるであろう。
次に、句読点を入れてみる。まず、その句読点間に出来る限り語句を詰め込み、出来る限り句読点量を少なくする方法で試みる)
オープンテラスのカフェから見える銀杏の並木が悶えるように風に揺れている。漏らすように俺が吐き出した煙草の煙の中で小さくなるブルーのシトロエンを横切り、目前の歩道を男たちが笑みを浮かべて走るように歩き日傘を差した女たちが這うように歩く。
「幸福を求める人種」
いつまでもカップの縁を辿り続けるか細いナナの指を強く握り締めた俺の手を、ナナは諦めに似た優しさで見つめていた。
「人間社会の生態系」
俺はナナの手を引き寄せ口に含んだ。それはもちろんナナの指を噛み砕くためでも飲み込むためでもなく、俺の腕の間にナナの頭が入る空間があるように俺の口の中にナナの指を入れる空間があるからなのだ。
(次は、句読点間を出来る限り狭め、出来る限り多量の句読点を入れてみる)
「赤って、何の色だと思う?」
舌、で、感じる、ナナ、の、か細い、指。柔らかな、指。滑らかな、指。滑らかな、爪。冷えた、指。
「花、果実、夕日、血」
満たされず、強く、噛んだ。一瞬、顔、を、歪め、遠く、を、見つめた、まま、の、ナナ。
「口紅、マニキュア、私のライター、唯則のサングラス、それに……」
舌、で、感じる、ナナ、の、血液。温かな、血液。それは、愛、の、連環。鉄、の、連環。俺、は、舌、を、噛み、ナナ、の、愛、と、混ぜ、合わ、せ、戯れ、た。
「春の、雪」
(以上の試みの結果、私はこう感じるに至った。文章には適度な区切りが必要である、と。それは論理的にはどのように考えたらいいであろうか。私は、こう考える。
人間は全てを、世界を、つまり時間と空間とを無数の部分に断絶させ、記憶するものとしないものとを取捨選択して捉えている。継続ではなく、断絶させている。
何故ならば、全てを記憶するには、人間の記憶の容量が、あまりにも小さいからである。
そして、人間は効率的に記憶を呼び起こすために、その選ばれた全ての部分を秩序正しく分類し、保存しているのである。
例えば、人はある一日の出来事を思い出すとき、生まれてからその日までの全ての記憶を順序よく思い出してからその日の出来事に辿り着いたりしない。また更に、その一日の一出来事を思い出すのに、朝目覚めてからのその日の全ての記憶を思い出したりしない。
つまり、章や節や段落や句点や読点は、人間の年、月、日、時刻などに相当するのであり、それは記憶の単位なのである。であるから、人間に向かった伝達には、このような区切りが必要とされるのである。そして、その区切る間隔は、人間の区切るリズムに近ければ近い程よいと言える。
では、一体、そのリズムとはどれぐらいの長さのものなのであろうか。私が直感的に感じたところでは、理性的な長さ、感覚的な短さ、である。
しかし、それは人によって様々であるかもしれないし、そうではないかもしれない。同一の人でも、朝と夜では違うかもしれないし、そうではないかもしれない。気分によっても然りである。
だが、これだけは言える。それはゼロではなく、無限大でもない、と。そして、正確に知ることのできるその基準となるリズムは、自らのリズム以外にない、と。
つまり、作者は、常に自らのその一語、一文、一段落、一節、一章における意図と流れを視野に置き、検分しながら書き進めるべきなのである)
テーブルから伸びるコーヒーの湯気。ナナの指を流れる赤。テーブルから伸びる煙草の煙。俺の口に広がる赤。そして俺は、分かたれることを恐れるように、ナナの頭を抱き寄せた。
「未消化な理性」
路面に照り付ける日差し。単一な空の青。ざわめく緑。流れる赤。遠く見つめるナナの瞳に映るそれら全ては、分かたれ、統合された。
「私、綺麗な洋服が好き」
鏡の前でスリップドレスを合わせるナナの眼差し。
「着飾ることがどうして嘘になるの? 本当の姿は裸だけなのに」
俺の足。ナナの脚。俺の腰。ナナの腰付き。俺の広げられた掌。ドレスを肩に合わせるナナの指。ナナが振り返った。
「何て言われても、モルガン」
(何の前ぶれもなく、今度は節を省いてみた。やはり混乱を招くだけで切り替えがうまく行われないことが証明されたように思う。そして、この問題を解消するためには、節に相当する説明が必要であろう。
しかし、その移行方法が読者をこの世界から隔離させてしまうであろうことは容易に推察される。何故なら、先に述べたように、人間は世界を断絶させる存在なのであり、出来事の繋ぎというものはただ言語上にのみ存在するからである。
改めて提示する。「私、綺麗な〜」から、次に示される節であった)
六月十五日、月
ナナが首を傾けた。事実、そのドレスがナナの脚の、腰の、胸の、肩の、腕の美しさを際立たせることは明白だった。微かに滑り降りたナナのブレスレット。
「表象は本質の一部である。本質の、一部である」
俺はナナの腕を掴み、試着室に引き込むと、その美しさを手荒く称賛した。脚を、腰を、背を、胸を、腕を、肩を、首を、そして、艶やかに光る唇を。
激しい愛撫にナナは瞳を閉じ、吐息を漏らした。美へのためらいを捨てた女として。
「可能的自己を制限する人種」
カーテンが波立つ。力の抜けたナナの膝が鏡でうごめく。透き通ったナナの首筋。
「お客様、いかがですか」
外から女の声がする。ナナの耳を噛みながら手を伸ばし、一気にカーテンを開くと、眩しいほど純白の空間が飛び込んだ。
色彩を手に取る疎らな人影。貼られた大きなモノクロ写真。ギョッとした店員の顔。俺はその手にドレスを差し出す。
「これ」
かがんでサンダルを履き直すナナ。
「それと、あの帽子」
俺が指差した方を見上げ、振り返ってナナは微笑んだ。
店を出て、夕闇の並木道を歩く。空を覆う漆黒のケヤキ。古アパート。すれ違う人影。楽し気に帽子を被り、跳ねるように歩くナナ。振り子の買い物袋。
「自己は自己を自己が自己に表現したものによって知る。例えば胸の締め付け」
立ち止まって煙草をくわえた。植え込みに紛れたビニール袋。痩せこけた土。掌を照らし出すライター。靴底で削れる小石の感覚。夕闇に一点の火種。溢れ、流れ出す白煙。
ナナの赤らんだ踵がヒールの上で僅かに上下する。ナナのふくらはぎが僅かに隆起する。スカートの裾が僅かにはためく。流れる煙。後ろ手に持たれた紙袋。流れる煙。帽子の後ろ頭。流れる煙。夕闇。流れる煙。
「歓喜と幸福とは同義か」
古びた公衆トイレ。古びたコンクリートブロック。俺が手を引くと、ナナは理解した。黒光りしたコンクリートの床。小さな穴に流れ込む汚水。錆び付いたノブを引き、ナナが入り、俺が続き、錆び付いた鍵を掛ける。
「憲法第九条を改正せよ」俺が、か。どのように、だ。「セックスフレンド募集中のりこ」男の字で、か。今でも、か。「貴基殺す」宣言、か。俺に、か。
ナナの鼻唄。ナナの黒い下着。ナナの背中。すらりと伸びたナナの脚。俺は煙草を踏み消した。靴から伸びる呻くような煙。ナナの鼻唄。肌を滑り降りたドレス。ナナが振り返った。
「どう?」
露になった繊細な肩。控えめな胸の膨らみ。美しい腰の流線。裾から伸びる艶やかで悪戯な脚線。
「これ以上は、あり得ない」
「本当?」
ナナが微笑した。やはり、あり得ない。俺はナナが脱いだ服を掴み、小さな四角い窓から投げ捨てた。
「愛において、全ては真実だ」
翻りながら舞い落ちる二切れの抜け殻。ちらつく青白い蛍光灯。ドアを開け、伸びやかに道に出るナナ。はためくドレス。ストラップ。暗闇に近い夕闇。
「ナナ」
ナナの振り返り、問う仕種。
「アルファロメオに乗ったこと、あるか?」
首を横に振るナナ。赤く点滅するパーキングメーター。
「じゃあ乗ろう」
ナナは俺の目線の先を追い、微笑んだ。ウインドウの向こうに見えるステアリング。微かに見える、差し込まれたままのキー。赤く点滅するパーキングメーターの数字。
7、7、7、ナナ。
ドアを開き、キーを回す。夜空に抜けるエンジン音。高鳴る。助手席で笑うナナ。美しい脚。ステアリングを右に切り、アクセルを踏み込むとウィールが叫んだ。
「それはあたかも回答の後に作られた問題のように陳腐だった」
六月十八日、木
青山通り。テールランプの帯。黄色に変わる信号。高速三号を流れる光。
「夜の道って、どうして寂しいの……こんなに車が繋がっているのに」
「道とは誰かが通り過ぎた跡のことだ」
「こんなに人も歩いているのに」
「いつまでも辿っている」
「青」
「解放、脅迫」
「ラジオ、かける?」
「ああ」
「……There’s not one day that goes by
That I don’t cry for you
There’s not one day that goes by
That I’m not singing the blues
There’s not……」
「歌声。美しい歌声。ナナの美しい歌声。俺のナナの美しい歌声。日本人の俺のナナの美しい歌声。人間の日本人の俺のナナの美しい歌声。生物の人間の日本人の俺のナナの美しい歌声。存在が有の生物の人間の日本人の俺のナナの美しい歌声。246」
「唯則……」
「こんなスピードじゃアルファロメオが台無しだ」
「綺麗な人……」
「ナナ……」
「人はいつまで愛を持っていられるの?」
「死ぬまで。人はいつから愛を持っている?」
「愛から生まれるの」
「エロスからだ。明治通り。寿命とは?」
「何も知らないの……」
「楽しい話をしよう。例えば……」
「ライター貸して?」
「煙草をくわえる、ナナの柔らかな唇。ライターを握る、しなやかな指。照らし出される、透き通った首筋。煙に包まれる、憂いのある瞳。美しい」
「褒めることが、楽しいの?」
「美しさを見出す自分の美しさが、だ。見ろ、後ろのシートに財布がある」
「東京って言葉、使ったことある?」
「ない。青山、広尾、恵比寿、代官山。狭い世界。幾ら入ってる?」
「いち、に、さん……ファイブ、シックス……ナフ、ディス……分からない……」
「じゃあ捨てろ」
「優しい言葉が好き……ねえ、飛んで行く」
「紙、痛み、喜び、時間、紙。空に放してやれ」
「もっと」
「自由!」
「もっと」
「不自由!」
「そう……」
「人を不自由にするのは人、人から自由を欲するのは人」
「だから……ねえ、いろんな声が聞きたい」
「愛、愛、愛」
「高さだけ?」
「愛、愛、愛」
「ふざけるだけ?」
「愛、愛、愛」
「かすれるだけ?」
「愛、愛、愛」
「息を吸いながら……他には?」
「ない。三の四乗……八十一……十分だろ?」
「足りない……足りるはずがないの」
「でも飽きる」
聳え立つウェスティンホテル。アスファルトを点滅させるハザード。目を落とすナナ。ドアを開くと漆黒の夜空が高く澄み切っていた。
六月二十三日、火
(先日、友人に「日本語をみがく小辞典」なるものをお借りした。それは〈名詞編〉、〈動詞編〉、〈形容詞・副詞編〉の三編に分かれていて、学浅い私にとって少なからず開眼させるものであろうことが予想される。
だが、私自身の経験上、それについての思考を何もしていないところに知識を持ち込むと、つまり今の状態なのだが、全否定か全肯定しか行われず、補足や修正など、私の考える知識の有効利用が行われないことが多い。
それは、言い換えれば、私の中に私以外の者だけで作られた言語理論の土台が築かれ、或いは、私がその理論以外のものだけで土台を築いてしまい、その本来の理論の姿への修正に費やす膨大な時間が必要になるという滑稽な事態が生じることが多いのである。
であるから、私はこの絶好の機会に、時機早尚を承知の上で、矛盾や誤謬や無意味を可能な限り避けることに注意を払いつつ、その理論の構築を試みようと思う)
吹き抜けの天井で回転するいくつもの巨大なプロペラ。メガレストラン。ナナが口にしているアプリコットクーラー。俺の節榑立った手。似合いのジョッキ。蒸し暑い。
「東京湾の水と多摩川の水って、どっちが綺麗なの?」
「それは透明度のことか、毒性のことか、美的感覚に訴える度合いのことか?」
狭苦しい後ろのテーブルから聞こえる声。
「……あなたらしくない、って。頭に来たから、私、こう言ったの。私は私なのに?」
ナナの向こうの狭苦しいテーブルから聞こえる男の声。
「……あいつに笑われたのは、辛かった」
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。
「私に、何ができるの?」
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。
「私は、何をすればいいの?」
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。
「私は、何がしたいの?」
(まず、私が構築したい理論とはどんなものなのか考える。だが、すぐには明確に規定できないので、消去法で限定してみる。
第一に、それは品詞の区分を規定するものではない。例えば、一般にこれは名詞だと区分されているものを、動詞だと主張するためのものではない。そこには従う。
第二に、活用を規定するものではない。例えば、か、き、く、く、け、けの五段活用をく、く、け、か、こ、き、き、かの変則八段活用にすることを主張するものではない。そこには口語、文語などの使用条件や効果を除き、従う。
第三に、仮名遣いや送り仮名を規定するものではない。例えば「動く」を「う動く」だと主張するものではない。そこには従う。
第四に、それは日本語を放棄するものではない。寧ろ、日本語の可能性を探るものである。だが、それは日本語のみに留まることを意味しない。あらゆる言語記号の表現における可能性の探求である。
以上が短時間で思い浮かんだ条件であるが、これらだけでは不十分であることは痛切に確信している。
だが、少なくとも私にとってそれ以上はあり得ない理論であると言える条件は、私の死をもって初めて満たされるのであり、生前に、しかもここに理論構築を図りそれを記そうとする以上、不足はやむを得ないものとしなければならない。
しかし先に述べたように、これは構築作業の完了を宣言するものではなく、過程であり、経過報告である。そのことを読者であるあなたにも、後の私自身にも理解して頂きたい。
ある種、言い訳がましい前置きが長くなったが、上の四条件から自らの中に思い描かれた構築したい理論の内容は以下の通りである。
第一に、語の意味が成立する可能性とその効果である。
第二に、語の順序或いは反復の効果である。
第三に、表記法や語尾の効果である。
第四に、語と語の繋がり、主語と述語と修飾語の関係、そして語の量の効果である。
つまり、規定よりも効果の分析である。さらに、一語の理論から一文、一段落、一節、一文章へと視野を広げて行きたい。
第五に、文と文との繋がりの可能性、或いは広げて段落、節、章、同士の繋がりの可能性、つまり、文章の成立の可能性とその効果である。
第六に、語と語、文と文、段落と段落、節と節、章と章との間の描かれない部分、或いは空白の効果である。これは書かないものの効果である。
第七に、文章の量の効果である。
第八に、文章の流れの効果である。
第九に、描写とその効果である。
第十に、題名の効果である。
以上、私自身が寒気を催すような目標を掲げ、それらを僅かでも明らかにすることにより、ある語や文、さらに段落、節、文章の目的に沿った効果的な使用が可能になるのではないか。
しかし、これらを規定して行くために使用する判断理由、つまりこの理論を形成する公理というものが先立って規定されなければならない。まずそれを示そうと思う)
潤んだナナの瞳が俺を見つめていた。長いナナの髪の毛先が頬で揺れていた。繊細なナナの肩が震えていた。
「愛し合おう、愛さなくなるまで」
ナナの唇が艶やかに微笑した。
「直感は非言語的思考過程から出された結論である」
ナナは立ち上がり、身を乗り出し、俺に口付けた。倒れたグラスから伸びる水の膜。
「私、ゴダールの映画が大好き。優しくて残酷、現実的で非現実的、恐ろしくて滑稽。見つかった! 何が? 永遠が!」
振り向いて歩き、吹き抜けから階下を見下ろすナナ。悪戯に曲げられた片脚。奏でられるアコーディオン。ナナの鼻唄。回るプロペラ。人いきれ。
俺は煙草に火を点けた。
「だから俺は自分に感謝し、恨まずにいられないんだ」
ナナの美しさが弾んでいた。
六月二十四日、水
(では、公理を求める。まず、私が先に挙げた理論構築を目指す目的、を明らかにする。
それは、私が最上の文物芸術作品の実現を目指すからである。
次に、芸術とは何であるか、を明らかにする。
芸術とは、表現者がある間接的な手段を通じて感受者にその内部からある感覚をもたらすもののことである。
間接的な手段というのは、彫刻であり、絵画であり、音楽であり、そのような物を通じて伝達する手段のことであり、直接、感受者に触れたり叩いたりする手段ではないことを示している。そのような直接的な手段を通じて伝達するものは芸術ではなく現実である。
内部からある感覚をもたらすというのは、現実に物理的に存在する姿とは違うものを感受者に知覚させることである。
例えば絵画で言うならば、白い花が描かれている絵によって、白い花だけではなく、例えば美しさであり、切なさを知覚させるものである。それは外部から直接与え得るものではなく、感受者の内部から引き出すものである。
次に、内部から引き出すことのできるものとはどんなものであるか、を考える。
それは最低限、時間的広がりと空間的広がりとを持つもの、つまり世界を持つものである。しかも感受者に自分自身がその世界にいると感じさせるような世界である。
何故なら、感受者の内部からある感覚を引き出すためには感受者自身がそのものに働きかけなければならないのであり、その働きかけとは描かれていない部分の時間的、空間的広がりを埋める行為に他ならないからである。
そしてその埋める行為によって作品と同化した感受者は、その作品中の世界において、現実世界で知覚するような、ある感覚を生々しく覚えるのである。
次に、どのようにして芸術の優劣を決定するのか、を明らかにする。
芸術の優劣は、感受者にもたらされた感覚の種類の数とその強度との積で決まる。
以上のことから、最上の文物芸術作品とは何であるか、を結論する。
最上の文物芸術作品とは、表現者が言語を手段として世界を構築し、感受者の内部に、先に示した積が最大となる、ある感覚をもたらすもののことである。
では、その実現のためには何が必要であるか。
それには最低限、言語を効果的に伝達する力、つまり表現力が必要である。つまり、言語理論の構築が有効である。そして、もたらすべき感覚を常に明確に見据えながら文を構築する力が必要である。
以上のことから、言語理論を構築するに当たっての公理を示す。
それは感受者が知覚できる効果でなければならず、しかも目的の達成に対して役立つ方式で言及されなければならない。その最上の目的は感受者にもたらそうとする感覚であり、そこから下って世界、描写と枝葉に分かれて行くのである)
高く澄み切った夜空。並木に降り注ぐ月光。ベンチに座るナナ。通りを疎らに過ぎるハイヤー。向かいに見える高層ビル。黒光りしたセンチュリーが停まる。
ドアを開く運転手。窓の明かりが疎らなマンション。帽子を被るナナ。白く高い月を見上げたナナの帽子。俺は煙草に火を点けた。暗がりに際立つ一点の赤い光。細く立ちのぼる煙。
「ナナ……何をしたい……愚かな問い」
通り過ぎるハイヤー。立ったまま、帰りを待つ運転手。澄み切った夜空。ベンチに座るナナ。帽子。肩。
「ナナ」
「ねえ……私がこれから話すこと、聞かないで……私、唯則に伝えたくて話すんじゃない、唯則に向かって話したいだけなの」
ナナが振り向いた。優しい瞳。寂しげにほころんだ口元。立ちのぼる煙。
「赤と青と緑なら、私は迷わず赤を選ぶの。でも、そこに黄色が入ったら、私はいつまでも迷って選べない。だって、そこから先は確かにあって、でも触れられなくて、いつまでも続くから」
立ちのぼる煙。立ちのぼる煙。立ちのぼる煙。
「自己批判なんて不可能だ」
「聞かないでくれて、ありがとう」
「嘘だ」
煙草を月に投げ捨てた。赤い光の点が放物線を描いた。ナナを抱きしめた。柔らかく、滑らかで、繊細で、美しい。俺の背中で広げられたナナの手の感触。
「明日はきっと晴れるね」
ナナの透き通った首筋。
「初めて聞いた」
ソワソワ立つ運転手。腕時計に目を遣った。
「ナナ」
背中でなぞられる「?」
「センチュリーに乗ったこと、あるか?」
左右になぞるナナの指先。駆け出す運転手。駆け込む入口に「TOILET」
「じゃあ乗ろう」
上下になぞるナナの指先。手を繋ぎ、歩き出す。軽やかに絡み合う指と指。弾んで渡る大通り。ドアを開け、ナナを乗せる。
今度は俺が白手袋。ゆっくりアクセルを踏み込んで、ヘッドライトがセンターラインを照らしたとき、後部座席のボスが笑った。
「海岸へ!」
六月二十五日、金
(第一、語の意味が成立する可能性とその効果について。
まず、語は意味を表し得るだろうか、と問うてみる。だが、それを述べる事自体、既に意味が成立することの証明になっている。より強く言えば、この語を私が書き、あなたはただこの語のみによって理解しているのだから、語の意味は成立していなければならない。
だが同時に、私たちはそのものが語であるということは理解できても、その語が何を意味するかを理解できないことがある。意味を知らないものを語と認識するとはどういうことか。
それは、私たちが意味を知っている語からの表象上の類推に他ならない。
では、その表象上の記号から意味を理解することは、どのようにして可能になったのであろうか。
それは連合、言い換えれば条件付け、例を挙げればパブロフの犬のような条件付けによってである。
人の言語は音から始まる。ある物を見たときにある音を聞き、それが度重なると、そのものを意識することがすぐにその音を呼び起こすような連合が起こる。
そして次に、その音と同じものを表す記号とを連合させ、ついに、記号とそのものとは観念の中で結合する。つまり、観念が記号を呼び、記号が観念を呼ぶようになる。
そしてそれが物体にだけではなく、動作や状態、感情、思想にまで達し、細分化し、より正確に伝達し、受け取ることが可能になるのである。そして更に、その語同士を自由に結合することが可能になれば、現実にはあり得ない、またあり得なかったものを生み出すことが可能になるのである。
ただ、ここで不可解なのは、私たちが意味を記号から直接受け取るのではなく、一旦音に換えてから受け取っているということである。そして思考も、音によって行われているということである。これは何を意味するか。
私が思うに、それは頭の中でそれが意味する像を描くこととその現実の記号を視覚的に知覚することとは、同時に行い得ないからではないであろうか。
試しに、次の言語を意識して見ながらそれが意味するものをイメージできるか、やってみて欲しい。
「星空」
次に、それを音に変換して、その音を意識しながらイメージできるか試して欲しい。どうであろうか。結果は明白ではないであろうか。
では、ここから何を導き出すことができるか。
それは、私たちの脳内で、映像を想像する部分と現実の映像を知覚する部分とは、恐らく同一の部分であるということである。
つまり、私たちが情景を表す文を見ながら同時にその情景を想像することはできないということになり、であるから、読み急がせる文章は、想像させる空間が狭くなる、または粗くなる、と言うことができるのである。
より簡潔に言えば、時間と空間とは反比例するのである)
ボスの指令はこうだった。
「第一京浜から羽田線へ」
バックミラーの中のボス。艶やかに伸びる脚を組み、煙草を燻らせている。俺の握るステアリングの向こうには、宙に浮かんだ外灯が、どこまでも伸びている。澄み切った星空を滑走路が貫いている。
「トゥルルル、トゥルル、トゥルル」
電話の音。
「トゥルル、トゥルル、はい……ああ、ああ……」
受話器を手に煙草を吹かすボス。窓の外に広がる星空に目を遣り、微かに溜め息をつく。
「……明日から君の席はないと思え」
受話器を置くボス。
「いかがなされました」
「ああ……私が今、多くの人間を少しずつ奴隷にしている……つまり、私を奴隷の主だ、と言っていた……」
煙草をもみ消すボス。
「だから、私は悪だ、と……停めろ」
路面を点滅させるハザードランプ。車を脇に止め、俺はボスのドアを開ける。ボスはその艶やかな脚を路面に下ろすと、ゆっくり立ち上がり、俺に抱き付いた。
「……助手席が、いい」
(次に、有限である語の種類によって無限である事物の種類を表すことが可能であるのか、可能であるならば、どのような方法によってであるか、を考える。
言語の伝達が可能であるということは、特殊が普遍を持つということである。言い換えれば、他の人間と同一ではない一個人が他の人間が持つものと同一な道具を持つということである。
それは必然的に、一語が完全に限定されたある事物のみを表すのではなく、類似した他の事物をも表すものでなくてはならないことを意味する。端的に言えば、事物そのものではなく、事物がもつ性質を表すものでなくてはならないことになる。
何故なら、例えば、私が今行っている「考える」ということとあなたが今行っている「考える」ということとが全く同質のものであるということは証明できないのであり、更に言えば、私が今行っている「考える」ということと私が過去に行っていた「考える」ということとが同質ではないのであり、言語が完全に限定されたある事物のみを表すのであれば、それぞれに別の名称が与えられなければならないからである。
だが、実際にそれぞれに別の名称を与えてしまえば、言語の種類数は天文学的数値に上り、更に果てしなく増殖してしまう。そしてそれらが普遍性を持たないことは明白である。
では、どのようにしてそれを解決するのか。いや、実際にどのように解決しているのか。
それは有限個の語同士を組み合わせ、組み合わされたものを一つの意味として伝達することにより、その種類数を増やそうというものである。それだけではない。そこに文脈によって形作られた状況をも組み込むのである。
例えば、今ここで私が「私たち」と言えば、それは全ての人間を表すが、ナナが「私たち」と言えば、それはナナと唯則のことを表す、というように。
こうして、私たちは有限個の言語によって無限個の事物を言い表すことに限りなく近付くことができるのである。
だが、そこには必ず類推の弊害が付きまとうことを忘れてはならない。具体的に言えば、説明不足、意味の取り違い、深読み、などである。
これらのような弊害に常に気を配りながら、私たちは書き、かつ、読み、また、話し、かつ、聞くべきであろう)
助手席に座り、鼻唄を歌うナナ。流れる外灯。星空。ナナの鼻唄。目の前に割って入るテールランプ。星空。バックミラー。静寂。ナナの鼻唄が消えた。
「私……もう、唯則のこと、愛せない」
流れる外灯。真っ直ぐ前を向き、呟くナナ。
「もう、好きじゃないの」
流れる外灯。
「その話し方が好きじゃない」
流れる外灯。
「そのハンドルの握り方が好きじゃない」
流れる外灯。
「その目も、その鼻も、その口も、その表情も、一度に好きじゃなくなったの」
俺はブレーキを踏み付けた。叫ぶウィール。暴れる挙動。暴れる挙動。叫ぶウィール。暴れる挙動。暴れる挙動。暴れる挙動。澄み切った星空。
「……だったら、降りろ」
「やっぱり……」
俺は顔を上げた。ナナの寂しげな瞳が俺を刺していた。
「唯則は私の言葉しか見ていない……」
ナナの口が歪んだ。一気に頬を伝った一筋の涙。赤らんだ華奢な鼻。鋭い顎にぶら下がり、小刻みに震える涙の滴。
「嘘だったのか」
「う……そ……?」涙の滴が千切れ落ちた。「……分かった……私、もう本当のことしか言わない……それも……思ったこと全部言葉にしてあげる!」
口を結び、前に顔を逸らすナナ。
「そんなことできるはずがない。できるならナナの中身が全て言葉でできていることになる。できるはずがない」
ナナがまた振り返った。
「できるわ!」
俺はまたアクセルを開けた。スピードが上がる。流れる外灯。「煙草が吸いたい」と言って火を点けたナナ。限りなく澄んだ星空。緩やかなカーブに合わせて回る俺の白手袋。
それは、既に存在の手錠を嵌められていたのだ。