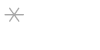フィールドワーカー
2006年 木戸隆行著
いたずらに過ぎた時間──これが本当の僕の姿だと思う。自分の生き方をついにつかむこともなく──何事もなかったかのように一挙に解決する力、これが僕には決定的に欠けているのだ。いい人なのか、クールなのか、それとも親しみやすいのか、このどれにも実のところ僕はなれる。話しかけるのか、話しかけないのか──ただ、さりげないフォローだけは僕に望めない。唐突に、平然と無理を言ってのけるのが僕だと言えば僕だ(憎まれたら憎まれっぱなし)。
もてる・もてたい・付き合っていた男の話に興じるのは決してセクシーではないぞ、と今言いたい。なぜなら夜のフィールドワーカーである僕は、とあるカフェの出口に一番近い席で、実際に関西なまりのこのかわいらしい声を聞いているからだ。彼女の声がとても迫ってくる。なぜこんなにも彼女の声「だけ」が迫ってくるのか、それだけが不思議だ。七不思議。「BSとかなら映っちゃうんじゃないかくらいの思い出」──君も不思議なことを言うね。言いたいこと言うね。やりたいことやるね。僕もそんな君の奔放さに習って、いくつもの過ちを犯してきた。思い出せばきりがないし、恨まれる覚えもかなりある(武勇伝は一つもないけど)。それなのに普段から世界中から陥れられた被害者のように振る舞って、一審も二審も敗訴。こうなりゃ自分で捜査してやると走り始めたのも束の間、僕は「日本人」という大きな罠にはめられる。それもネガティブな「日本人」だ。ネガティブな「日本人」にはまるで良いところがない。僻みと妬み、それから、どこから湧いてくるのかまるで見当もつかないプライドと、それによってねじ曲げられた桁外れな謙遜とが複雑に入り混じり、結局その人が空っぽだった(つまり思考せず、反応した)という印象しか残さない。空っぽな人間は次々に反応する。そしてネガティブな日本人である僕は彼女の言動にいちいち反応し、これじゃあダメだとペンを握り直したのも束の間、目に飛び込んで来た彼女のローファーに「君はヒールまで捨ててしまったのか!」と吐き捨てる。
否定でなく肯定──本当は、それだけで生きていけるはずなのだ。
もてる・もてたい・付き合っていた男の話に興じるのは決してセクシーではないぞ、と今言いたい。なぜなら夜のフィールドワーカーである僕は、とあるカフェの出口に一番近い席で、実際に関西なまりのこのかわいらしい声を聞いているからだ。彼女の声がとても迫ってくる。なぜこんなにも彼女の声「だけ」が迫ってくるのか、それだけが不思議だ。七不思議。「BSとかなら映っちゃうんじゃないかくらいの思い出」──君も不思議なことを言うね。言いたいこと言うね。やりたいことやるね。僕もそんな君の奔放さに習って、いくつもの過ちを犯してきた。思い出せばきりがないし、恨まれる覚えもかなりある(武勇伝は一つもないけど)。それなのに普段から世界中から陥れられた被害者のように振る舞って、一審も二審も敗訴。こうなりゃ自分で捜査してやると走り始めたのも束の間、僕は「日本人」という大きな罠にはめられる。それもネガティブな「日本人」だ。ネガティブな「日本人」にはまるで良いところがない。僻みと妬み、それから、どこから湧いてくるのかまるで見当もつかないプライドと、それによってねじ曲げられた桁外れな謙遜とが複雑に入り混じり、結局その人が空っぽだった(つまり思考せず、反応した)という印象しか残さない。空っぽな人間は次々に反応する。そしてネガティブな日本人である僕は彼女の言動にいちいち反応し、これじゃあダメだとペンを握り直したのも束の間、目に飛び込んで来た彼女のローファーに「君はヒールまで捨ててしまったのか!」と吐き捨てる。
否定でなく肯定──本当は、それだけで生きていけるはずなのだ。