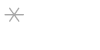完結した夏
1998年 木戸隆行著
東京アンダーグラウンド誌「SPEAK」2000年4月号 CM掲載作品
東京アンダーグラウンド誌「SPEAK」2000年4月号 CM掲載作品
31(遠)
「男だったらもっと食べろ」男がテーブルの向こうから箸で俺の皿を指した。「ん?」二つに割れたたくましいあごが髭で青々としている。「ほら」皿を指した。俺はうつむいた。「……ったく」男が食事を頬ばった。
「……ええ、探してるわよ」俺の背後で母が電話をしている。「……うん……今かけ合ってる仕事が、何とかなりそうなの……あ、でも待って……まだはっきり決まったわけじゃなくて……」男の食器がカチャカチャと音を立てている。「……そう……そうよ……だからもう一月だけ……」テーブルに映っている男の顔が、食事を頬ばったり母の方を見たりしている。
この男は、いつまでこの家にいるのだろう?……母の席のテーブルには食べかけの昼食が残されていて、その隣にはほとんど減っていない俺の昼食がある。テーブルに映っている男の顔は母の皿と俺の皿で少しずつ欠けながら、苛立った様子で口を動かしている。
「ご、ち、そ、う、さ、ま」男が電話口に聞こえるような声で言った。「ちょっと!」振り返ると、母が受話器を手で塞いで男をにらみつけていた。「どういうつもり!」振り返ると、男が嫌気の差した顔で笑っていた。「別に」
「あ、もしもし?ごめんなさい。今、知り合いが家にきてて……なあに、その言い方?私がうそをついてるとでも……」男が俺の頭を小突いて「お前のせいだぞ」立ち上がった。
「どうして自分の娘を信じられないの?……いっつもそう……」男の毛深い脚が母の白い脚に寄り、ゴツゴツした大きな手が母の尻を丸く撫でた。母が受話器を耳に当てたまま、男をきつくにらみつけた。「おーこわ」男がおどけて部屋を出た。
「……うそ!お母さん、私のこと一度だって信じてくれたことないじゃない!あのときだってそう!……お母さん、あいつのことばかりかばって……私だけを悪者にして……どうしてなの?ねえ……私のことが、そんなに邪魔なの?」
男が部屋に戻ってきて、歩きざま、母の尻をまた撫でた。瞬間、母が男の頬を力一杯張った。「いい加減にしてよ!」男の目に怒りが走った。「何だぁ?」二人はしばらくにらみ合った。窓からジーッとアブラゼミの声が高鳴った。
「……はん」男が鼻で笑ってソファーに座った。母は背を向けて受話器を耳に当てた。上げられた後ろ髪が首筋にほつれている。「……ごめんなさい、水面がちょっと悪戯……」
母の首筋に二本の筋肉が隆起した。「もういいわ!……分かったわよ!」二本の筋肉が隆起した。「もうあんたなんかに頼まないわよ!……ええ!そうよ!……私が今までどれだけあんたにこき使われて……ちょっと!もしもし!」
「おーおー、凄い迫力ですこと」男がタバコをくわえながらソファーに大きくもたれた。母は受話器を首に当てたまま動かなかった。「ボク、ああいう風にだけはなっちゃだめだぞー?昔からなあ、短気は損気と言って……」母の首筋に当てられた受話器が小刻みに震えた。「おお、今度は涙……全く、自由自在だね」母の頭が向こうに沈んだ。「いい女優になれる……」
「やめろ!」俺は立ち上がり、男をにらみつけた。「……やめろ!」
男は座ったままゆっくりと身を乗り出し、灰皿にタバコの灰を落とした。「……何だ?」男が顔を上げ、じっと俺を見据えた。「……何を、やめるんだ?」えぐるように鋭い目だった。
「いいの」後ろから、母の腕が俺の身体に巻きついた。「いいのよ、水面……ありがとう」後ろから、俺の頭を撫でた。「……ママは大丈夫だから……ね……いい子だから……」俺の頭を撫でた。男はまだ俺を見据えていた。「ほら……」母の手が両肩をつかんだ。
俺はうつむいて、母に導かれるまま部屋を出た。廊下を玄関まで歩き、向き直って、母がしゃがんで頭を撫でた。
「ママ、あの人と大事なお話があるから」俺の身体は恐怖と興奮とで震えていた。「水面はお外に遊びに行ってらっしゃい?ね?いい子だから」母が優しく頭を撫でた。
首をゆっくり縦に傾けると、母は笑顔を残して立ち上がった。後ろ姿がリビングに消えた。
玄関に腰を下ろすと、ドアの横のすりガラスがぼおっと明るく光っていた。スニーカーを履き、見ると、母のハイヒールの横で、男の大きな皮靴が異様な存在感を放っていた。立ち上がり、それを蹴り飛ばそうとして躊躇すると、廊下の奥からかすかに母の声が聞こえた。
……ごめんなさい……
32(近)
「ちょっとなんなの!?勝手にひとの家に上がらないでよ!」玄関から陽子の掠れた金切り声がした。俺はベッドで寝返りを打った。「いるんだろ?」部屋のドアの向こうに男の声が近づいた。勇ましい足音が近づいた。「ちょっと!」なだれ込むようにドアが開いた。
おやおや、たくましい商社マンの登場だ。
「こいつか?」口の周りからあごに沿って生やした髭……いや、剃っていない、と言った方が正しいか……やつれた感じだ。
「出てってよ!」陽子が男の腕を向こうに引っ張っている。だが、そのたくましさにビクともしない。「出てって!」
男はドアノブを手に俺をじっとにらみつけている。やれやれ……合鍵を持った暴漢……しかも嫉妬に狂っている……早いとこ、俺の胸倉をつかんで気の済むまで殴り続けたらどうだ?……血を流し、腫れ上がらせて……いっそ、殺してしまうのはどうだ?
俺は男から目を外し、タバコをくわえて火を点けた。ベッドルームの四角い窓がぼおっと白く輝き、俺の身体を覆う白いカバーがくっきりとしわを陰にしている。タバコの煙がゆっくりと光の中を立ち上り、漂い、広がって行く……何て心地いい倦怠感……ようやく足音が近づいた。
「陽子を、返してくれ」
俺は男を見上げた。どうやら、つまらない冗談ではないらしい。俺の枕もとにしっかりと立ち、両拳を握り締め、男のその真剣な目つきは問いの答えを伺いながらも「はい」という答えしか受けつけない、そういう目だった。
まんざらでもないのだろう、止めに入らない陽子に目をやると、慌てて取り繕うように「ちょっと……」と手を伸ばした。それはそうだろう、『お互いに相手の空気を認めていた』仲だ。
「頼む、お願いだ」男はベッドから一歩下がると床に膝をつき、両手をついて深々と土下座した。シャツの襟首から太い首が見えた。
やれやれ……どうやら『俺』は『陽子』の『所有者』で、その『俺』を泣き落として『自分』が『陽子』の『所有者』になるつもりらしい……しかもその図式に気づきもせずに……俺はタバコを吸い込んだ。
経験上、この類いの人種は、これから自分の心情について、それがあたかも世界を揺るがす重大事であるかのように延々と語り、挙句の果てに『生きられない』に行き着く。語られる相手には、そいつが死のうが生きようが何の意味も持たないにも関わらず。しかも、そう言いながら『死ぬ』ことができない。つまり『生きない』ことと『死ぬ』ことが別のことだと思っている。
「俺には陽子がいないと……」
男は本当に予想した通りの言葉を口にした……それは俺が自分の言葉なのかと錯覚するほどだった……「陽子がいなくなってから、俺は」……知っていることを教えられている感覚……「だめなんだ」……脅迫にもならない脅迫が続き……陽子は……「出てってよ」……男のシャツを引っ張りながら、本当のところ、止める気がない……最後まで聞くつもりらしい……
それなら「ちょっと」俺がやめさせるしかなかった。「あのさ……俺に話す風を装って、実際はようちゃんに話すのやめてくれるか?煩わしいんだよ。直接ようちゃんに話せばいいことだろ?それにあんたが死のうが生きようが、俺には何の意味もない」その気はなかったが、皮肉めいた言い方になった。
「おまえ……」髭だらけの男のあごが近づいた。「もう一遍言ってみろ!」俺の胸倉をつかんだ。陽子が男の背中から抱きつき、仲裁した。「いい加減にしてよ!」
……何で俺が、この二人の痴話喧嘩に巻き込まれなければならないんだ?
どこかの応援団のような嗄れた叫び声を上げながら「ぶっ殺してやる!」男が後ろ向きで引き摺られて行った。陽子に引き摺られるくらいだ、本当は俺のことを殺すつもりはなかったんだろう。全く、演技好きな奴だ。
ダン!玄関のドアが蹴られた。
俺はタバコを深く吸い、枕もとにある一冊の躍動的な本を開いた。躍動……確かにその全てが美ではなく、美の全てが躍動でもなかったが、躍動の一部が美の一部であることは確かだった。本の表紙は赤かったが、その題名までは知らなかった。
「……ちょっと、ひどいんじゃない?」戻って来た陽子の責めるような目は、それが疑問文ではなく、肯定文だということを表していた。そこからさらに連鎖して……
俺が男と言い争い、それによって陽子の地位を高め、そうしてから、俺が男を説き伏せ、陽子が男から恨まれることのないようにし、そうしてから、陽子が俺に独占されている感覚を得る、つまり陽子が俺を独占すること、を望んでいた。
俺はベッドから立ち上がった。「どこ行くの?」キッチンに出て、トイレのドアを開けた。二畳ほどの洋式トイレだが、コバルトブルーのライトが好きだった。便器の蓋と便座を持ち上げ、勢いよく放尿した。溜まった水が一瞬にして細かく泡立ち、その白なのか青なのか判然としない泡を貫くように、下腹部に力を込めた。便器を挟んでいる俺の両足が生々しかった。
キッチンの蛇口を捻り、手を洗い、風呂を見て、レコードの部屋をよく眺めながら過ぎ、ベランダに出た。風が割と強かった。
左右の隅に置かれた鉢植えの葉がガサガサと騒ぎ、だが、空は夏の青だった。春、秋の包み込むようなそれとは違い、刺すような日差しが全身に心地好かった。粉塵で黒く汚れた首都高も、それはそれで夏だった。自尊心が傷ついたのか、あるいは欲求が満たされなかったのか、とにかくその辺りと葛藤していたのだろう陽子が部屋から出てくるまでには、まだ時間があった。俺は椅子を引いて大きく背もたれた。
文香は?
そうだ……カラーストッキングを履かせよう……光の角度によって緑色や紫色に変化する……そう、玉虫色のやつだ……あの美しい脚線に、妖艶な色彩を加え……小振りだが艶かしい乳房を片手でつかみ……喜びに歪んだ顔を何度も噛んで……挿入しそうで、しない……そうやって二日間過ごそう……そうだ……それがいい……ようやく陽子が現れた。
「みいちゃ……」「よく考えればいい。俺は帰る」陽子の髪を上げ、首筋に口づけて部屋を出た。
山手通りは街路樹や遠くからセミの声がして、バイクのエンジン音が紛れるほどだった。左前方のビルは窓から黒いよだれを垂らし、横断歩道の先では工事中のビルが頭にクレーンを乗せていた。坂を上り、246を横切って、薬局の店内で文香の脚線をイメージした。
そして袋小路に入って行った。右手に薬局の袋を提げ、口にタバコをくわえ、公園では、藪蚊に襲われる子供たちが遊んでいた。俺は足を止め、鉄棒の横にあるスプリングつきの木馬にまたがった。木馬の頭を貫くグリップを握り、子供たちの視線を浴び、そして前後しながら激しく叫んだ。
「文香!今帰ってやるからな!」
33(遠)
公園のブランコで、陽子と俺は前後に大きく揺れていた。頭上では、高木が太い枝を四方に張り巡らせていて、葉と葉の隙間から光の筋が差していた。ジーッと煽るようにセミは鳴き、陽子の身体の表面には木漏れ日のかけらが次々と流れていた。
「どっちが靴を遠くまで飛ばせるか、競争ー!」陽子のブランコが風を切りながら下りてきて、地面に最も近づいた瞬間、陽子の右足から白いスニーカーが飛び立ち、木陰を抜けて青空に舞った。
スニーカーはゆっくりと回転しながら空を泳ぎ……飛行機雲を通過して……砂場よりもずっと向こう……鉄棒の手前に降下して……地面に跳ね返り……転がり……鉄棒を越えて……停止した。
「みいちゃんもはやくー!」陽子が靴のない脚だけ前に伸ばして大きく前後に揺れていた。俺は靴のかかとを外し、地面に最も近づいた瞬間「タァ」足を蹴り出して飛ばした。
だが、靴はほとんど真上に上がり……飛行機雲さえ越えることなく……砂場の手前で跳ね返り……こちらに向かって転がった。
「ハハハハハ!」左で陽子の掠れた笑い声が前後した。「ヘタクソー!ハハハハハ……」笑い声が前後した。「ハハハハハ……」笑い声が前後した。
笑い声が前後した。
「おい、あれ、こないだ転校してきた……」公園の入口から、野球帽を被った三人組の少年達が自転車に乗って入ってくるのが見えた。二人の少年は補助輪を片方だけつけた自転車に乗り「……だよ」一番年長に見えるもう一人の少年は、大きな自転車を三角乗りしている。
三人は公園の外周の道を、ジグザグ運転しながら遠巻きに近づき「……やっぱりそうだよ……」背後に廻り、こちらを見ながら右に抜けて行った。陽子はうつむきながらザッ、ザッと片足で地面を擦って減速し、ブランコを下りて俺を見上げた。
「……みいちゃん、あっち行こ」陽子が片足でケンケンと跳ねながら、飛ばしたスニーカーを拾いに行った。俺も地面に足を擦り、ブランコを停止させると、深く掘れた砂が靴の隙間から侵入した。「はやく、行こ」陽子が俺の靴を差し出した。
公園を出て雑木林を抜けると、昼下がりの日を浴びた青い水田が地平線の山の麓まで広がっていて、その真ん中に、真っ直ぐ農道が伸びていた。農道の途中には市民プールと清掃工場の煙突があり、左手には住宅地があった。
陽子はポニーテールを揺らしながらあぜ道に下りた。俺も後に続いて飛び下りると、足下の水田で細長いドジョウが泥の煙幕を巻き上げて逃げた。ザリガニを探して覗き込みながら歩いて行くと、コンクリートの円い筒でできた農業用水の引き入れ口を発見した。両膝を突いて筒の中を手で探ると、鈍い痛みが指先を挟み、徐々にその力を強めて行った。
「ようちゃん、ザリガニ!」だが、陽子の後ろ姿は振り向かずにあぜ道を歩いて行った。
ザリガニに指を挟ませたまま引き揚げようとすると、放したのか、鈍い痛みが消えた。俺はさらに深く手を差し入れ、ヌルヌルとした筒をひとしきり探った。だが、ザリガニの身体はついに指に触れなかった。諦めて手を引き抜くと、腕に二匹の赤黒いヒルが付着していた。俺は素早くそれを払い落とすと、ヒルは力なくUの字になって宙を舞い、水田に張られた水に波紋を立てて沈んで行った。
「みいちゃん」陽子が一つ先のあぜ道の十字路で立ち止まった。「だれにも、言ってないよね?」陽子がしゃがみ込み、足下の草を引き抜いた。
「……なにを?」俺はヒルの着いていた腕を擦った。「……あのことだよ……だれにも言わないって、約束したでしょ?」陽子が再び歩き出した。俺は走って追いついた。
稲の先端には、まだ殻は青いが、大きく実った稲の穂が頭をわずかに垂れていた。歩きながら三粒ほど米をそぎ取り、殻を剥いて口にすると、干し草のような粉っぽい味がコリコリと前歯に心地好かった。
その時「ふじしろーがおーとこーとあっちっちー、ふじしろーがおーとこーとあっちっちー……」さっきの三人組がはやし立てながら、右手の農道を通過した。陽子が両拳をきつく握った。
あぜ道の十字路をいくつも過ぎ、小川を跳び越えて着地すると、ゆるんだ土手に四つの靴跡が残った。水田を抜けて空地に出ると、陽子が何も言わずに走り出した。俺は後を追いかけた。夏草の鋭い葉で肌を切り、苔の生えたブロック塀の細道を走り抜け、成熟したヒマワリを化粧ブロックの隙間に見ると、砂利の敷かれた駐車場に出た。四方に打ち込まれた木の杭に誰かの学校用の運動靴が干されていた。
そこから大通りに出て、コンクリートの川に沿って路肩を歩いた。川を挟んで向こうには背の高い生け垣があって、その天辺より上では真新しい藍色の屋根瓦が光っていた。継ぎ接ぎのある古びたアスファルトの路面は所々に赤サビのような染みがあり、行き交う全ての車の窓は暑苦しそうに開かれている。陽子のヤセッポッチの脚が路側帯の白線に沿って歩き、その影がほとんど真下に落ちている。
「……ようちゃん、宿題、終わった?」陽子のやせっぽっちの両腕が、バランスを取るように軽く開いた。「まだ」陽子の上半身がバランスを失って左右に大きく揺れ、ついに白線から路肩に足を着いた。「今日も家を出るとき、お母さんとけんかした」今日は俺が誘い出したのだった。
陸橋を上り、眼下に線路を見下ろすと、三両編成の電車が通った。電車の行く先には古びた木造の駅があり、駅より左手には、これも古びた市街地が広がっている。右手には半円形の天体望遠鏡を屋上に頂く高校があり、その周囲を住宅が取り囲んでいる。
手摺には、大きなカマキリが腹部を膨らませたり縮めたりしながらじっと獲物を待っていた。「ようちゃん、カマキリ……」手を伸ばすと、カマキリは大きな羽を広げて異様に飛び去った。その時、声が近づいた。
「ふじしろーがおーとこーとぶっちゅっちゅー……」またあの三人組だった。「ふじしろーがおーとこーとぶっちゅっちゅー……」どうやらつけ回しているらしかった。
ついに陽子が振り向いた。「ちょっと!」三人組の行く手を遮り、立ち塞がった。「あんたたち、こんなことして楽しいの!」
三人は近くまで来て自転車を止めると、一番年長に見える少年が歩み出た。「なんだ?」陽子に迫り、顔を突き合わせた。「転校生のくせに、生意気だぞ」少年の顔が近づいた。
その時……パーン!……陽子が少年の頬を張った。少年の野球帽が横にずれた。「なによ!転校したこともないくせに!」
少年が頬を押さえた。「……ってえな!このブス!」三人は慌てて自転車にまたがると「デブ!」走り出し「チビ!」叫びながら坂を下って行った。
「みいちゃん!」陽子が俺に振り返った。「どうして約束やぶったの!?」陽子のかん高い掠れ声が空に響いた。「やぶってない……」「うそ!」陽子が俺の肩を両手で突いた。「うそ!」突いた。「うそ!」突いた。
ドサッ!……俺は仰向けに転倒した。
「あ……」陽子が慌てて駆け寄った。「だいじょうぶ?」すぐ目の前に陽子の膝頭がしゃがみ込んだ。「だいじょうぶ?」陽子が心配そうに顔を覗き込んだ。「だいじょうぶ?」
「……僕」俺はゆっくり起き上がり「言ってないよ!」陽子の腹を目がけて突進した。その拍子、陽子は路面に後頭部を痛打して「いたい!」両手で頭を抱え込んだ。
陽子の顔が一気に歪んだ。「いたい……」陽子の顔が一気に赤らみ、目尻からどっと涙がこぼれた。「いたいよ……」陽子の口が『うえーっ』という泣き声とともに、糸を引きながら真っ赤に開いた。
俺は慌てて手を伸ばし、陽子の後頭部をさすった。「ごめんね」後頭部をさすった。「ごめんね」後頭部をさすった。「ごめんね」だが、陽子は泣きながら首を横に振り「ごめんね」俺の手を振り払って立ち上がると「ごめんね」走って坂を下って行った。「ごめんね……」
空は……空は青かった。
俺はその場に座り込んだ。真上にはギラギラと太陽が揺らめいていて、その横に、トンボが三匹浮いていた。トンボは羽ばたくたびに位置を変え、だが、いつまでもそこにいた。下からセミの声がして、時々、電車が通過した。目の前を車が疎らに通り過ぎ、その間、俺は日が暮れないのをずっと恨んでいた。
34(近)
ドアを開いた。「文香、もう少し綺麗に食べられないのか?」床にはスーパーのトレーやラップ、野菜の芯や皮など、冷蔵庫の中のあらゆるものを食べ荒らした痕跡が生臭く散らかっていた。俺はそれらを足でどけ、冷蔵庫のドアを開いた。棚にはビールが二本残っているだけだった。
「文香……」俺はプルタブを上げた。「……何、してる」文香はベッドの上で、必死に身体を隠すようにシーツを胸に当て、怯え切った目で俺から後退さっていた。
「……何を、してんだ?」俺はビールを飲みながらベッドに近づいた。文香はじっと俺を見詰めながら、手足をもつれさせて後退さった。俺はビールを床に投げ、大股で文香に詰め寄った。「何をしてんだ!」逃げる文香の手首をつかんだ。
いやあああああああ!……文香が白目を剥き、狂人のように叫んだ。
「何だ、これ……」なおも逃げようとする文香の細い腕に、青紫色のアザがくっきりとついていた。二センチ幅の四本のアザが、まるで人間の指のように文香の腕に巻きつき……いや……それは確かに人間の指だった。
文香は俺に腕をつかまれたまま鬼気迫る形相でベッドを後退さり、そのまま床にドサリと落ち、背を向けて這いつくばり、なおも俺から逃げようとした。腕が抜けそうなほど肩は陥没し、長い髪が激しく騒ぎ、美しい背筋が曲がりくねり、腰の曲線が左右にねじれた。
「文香!」俺は力一杯文香の腕を引き寄せた。いやああああ!白目を剥き、鼻から口から熱い液体を垂れ流している文香を、拘束衣のようにきつく抱き締めた。「文香!」いやああ!「文香!」いやぁぁ……
腕の中で抗っていた文香の動きが、徐々に、徐々に、沈静した。
「文香……」俺は文香の頭に口づけた。腕の中で文香はしきりに首をひきつらせていた。「文香……」俺は温めるように文香を抱き締め、口づけた。文香は足首にも同様のアザをつけていた。
何が、あった?
こんなにくっきりアザが残っているということは……文香の握力を考えれば、自分で握ってつけたとは考えにくい……ということは、俺と文香以外の第三者がつけたことになる……しかも力の強い……恐らく大人の男だ……
ゴミの散乱した床をよく見ると、かすかに靴跡のような汚れがあちこちにあった。それは記憶の範囲では俺の靴跡ではなかった。本棚やクローゼットの散乱した様子も、見方によっては争った形跡に見えなくもなかった。
そうすると……やはり誰かがこの部屋に侵入し……両手両足首にアザがついているということは……『大』の字に張りつけられるような格好で手足を広げられ……つまり……犯された?
俺は抱く腕を緩め、中の文香を覗いた。文香の両脚は人形のように不自然に『く』の字に折れ曲がり、背中は老婆のように丸まり、両腕は力なく垂れ、目も口も完全に放心し、半ば開いていた。俺はもう一度強く文香を抱き締め、頬を頭に押しつけた。
誰が……一体「誰が!くそったれ!」文香の背中が折れ曲がるほどきつく抱き締めた。
その時、電話が高く鳴り響いた。「誰だ!お前か!お前だ!殺してやる!ぶっ殺してやる!」電話が高く鳴り響いた。「首を引き千切り、ぐちゃぐちゃに踏み砕き」電話が高く鳴り響いた。「絶対に、今すぐ、ぶっ殺してやる!」電話が高く鳴り響いた。
文香は腕の中で折れ曲がり、放心して天井を見上げていた。
電話が高く鳴り響いた。俺は受話器を上げた。「うるっせえんだよ!」叩きつけて切った。するとまた鳴り響いた。俺は受話器を上げた。「うるせえって言ってんだろ!」「うるせえのはてめえだろうが!」
受話器の向こうで、ドスの効いた男の声が叫んだ。「あぁ!?」ドスの効いた声が叫んだ。「違うかこら!?おお!?」ドスの効いた声が叫んだ。
……何だ?この感じは……
「てめえ、いつんなったら金返すんだ!?あぁ!?次はあんなんじゃ済まねえぞ!?あぁ!?こら!聞いてん……」受話器を置いた。するとまたかかってきた。受話器を上げて置いた。だが、またすぐにかかってきた。俺はプラグに手を伸ばし、抜いた。
……『次はあんなんじゃ済まねえぞ』?
……『次は』?
……『次』?
文香を両腕で抱え上げると、頭と腕がダラリと垂れた。開け放たれた両目が壁に向かって白目を剥き、それでいて、乳房の揺れる様子は瑞々しかった。左腕には赤らんだ膝頭が二つあり、その先で、上下に振れる足先が愛おしかった。
俺はベッドにゆっくり文香を下ろした。そしてシャツを脱ぎ、ズボンを下ろし、挿入した。文香は乾いていた。だが俺は濡れていた。人形のようにピクリとも動かない文香に入れて出し、出して入れ、乳房をわしづかみにした瞬間、時空を越えて、俺は強姦魔と一致した。
全ては俺から派生したこと……文香の小振りな乳房が震えるように回転し、かすかに浮かび上がる肋骨の『ハ』の字がうごめいている。腹筋にあいた美しい縦ベソ。腰骨の間の三角地帯。艶やかな二本の腿のつけ根を割って、俺は情熱的に前後する。
虚空を見詰める文香の瞳……そこにはきっと……気が狂いそうなほど鳴り響くチャイム……破れそうなほど蹴られるドア……鼓膜の奥に届く罵声……恐る恐るドアを開け……だが愚かにも全裸の文香……男の顔は獣に変化し……押し倒され……揉み合い……両足を開かれて……
……いやああぁやめてえぇぇぇ水面ぉ水面ぉぉ……
俺は陰茎を引き抜き、文香をうつぶせに転がした。奇跡の感覚を禁じえない美しい背筋、そしてその下降曲線。瑞々しく盛り上がる尻をわしづかみ、左右に開き、肛門に辿り当て、挿入する。そしてその美しい背中に覆い被さる。
……もはやカラータイツが必要でないことは明白だろう……
俺の目の前には振動する文香の後頭部がある。
35(遠)
「ただいま……」ドアの形に夕日が差し込み、玄関のタイルの床に俺の影が長く落ちた。背中からヒグラシの声が流れ込み、ひっそりと静まり返った廊下の奥まで響いて行った。右手には一着もかけられていないコートかけがあり、その骨格が壁に等身大に投じられていた。
靴を脱ぎ、リビングのドアをそっと開けると、母と男がソファーでじっと押し黙っていた。男は母から顔を背けて壁をにらみ、母は男の膝に片手を置いて視線を床に落としている。
「ただいま……」とつぶやくと、母がゆっくり目を上げた。
「もう……帰ってきたの……」
母は物憂げに立ち上がり、ゆっくりこちらに歩いて来ると、俺の両肩に手を乗せて「水面、ちょっと……」と、そっと廊下に連れ出した。
母に背を押されるまま廊下を歩き、階段の上り口まで来ると、肩をゆっくり振り向かされた。母の白いワンピースの腰にしわが立ち、母の顔が目の前にしゃがみ込んだ。
「ママ、大事なお話がまだ終わってないから……」母の生臭い息が鼻を突いた。「もう少し二階に上がっていて?」夕日を真横から浴びた母の顔が傾き、目鼻の陰影が際立った。「ね……」金光の差し込んだ母の黒目がガラス玉のように輝き「さ……」俺の背中を階段に押した。
階段を上る自分の影が、前方の段に添って折れ曲がる。母は上り口で俺が上り切るのを見届けると、リビングの方に歩いて行った。俺は最上段に腰かけた。
階段の上り口に見える廊下の床板が、その境目を曖昧にしながらまぶしく金色に輝いている。その最も明るい部分は溶鉱炉でドロドロに溶けた鉄のように流動的に輝いている。
何これ……階下から母の声がした。……何のつもり……「いい加減にしてよ!」ドアの開く音がした。
「それじゃあ不足か!」男の怒鳴り声が廊下に響き渡った。「もっともっと金を出せ、か!ハハハ!そりゃあそうだ!そのために俺に『またがった』んだからな!」
「だから!違うって言ってるでしょ!」
「何が違う!」
「何から何まで違うわよ!」
「はん……」廊下のきしむ音がして「……何が『結婚しない?』だ……ハッ……最初からおかしいと思ってたんだ……」階段の上り口の前を男の足が通り過ぎ、すぐに母の足が続いた。
「……ねえお願い……本当に違うのよ……」布の擦れる音がした。「どう言えば分かってくれるの……」
廊下のきしむ音がした。「じゃあ、あれは何だ?ん?……あの紙は、何だ!」「だからあれは……前の主人が借りた……」「離せ!」布のはためく音がした。
「……何が前の主人だ……」廊下がきしみ、靴音がした。「……今朝、電話で話してたことも嘘なんだろ?」「何のことよ……」「職を見つけたとかどうとか、あれはつまり俺のことなんだろ?……そうなんだろ!」
「違うわよ!」
「じゃあどんな職に就いた!ああ!どんな職に就いたか言ってみろ!」
「銀行の……経理よ」
「言ってろ……」カツカツと靴音がして「待ってよ!」母の声とともに玄関の外へ遠ざかって行った。
入れ替わり、ヒグラシの声が金色の階段を涼しく上って来た。日に焼けた砂の匂いが吹き抜け、ドロドロに溶けた鉄の輝きは、最下段のへりにまで達していた。荒々しく玄関に靴音が戻って来て、俺は気づかれないように部屋に入ろうと、そっと腰を上げた瞬間、上り口に母の目が見えた。
「……盗み聞き、したね?」
母は寒気がするほど冷酷な目で俺をじっと見詰めた。俺は首を横に振った。「そうなんだね?」母の片足が階段に乗せられた。俺は首を横に振った。「怒らないから、正直に言いなさい?」母の膝が一段一段上って来る。俺は首を横に振った。「ママの話、聞いてたんでしょう?」白いワンピースの腿がしわを立てながら片方ずつ持ち上がり、わずかに血管を浮き上がらせた両腕が前後に揺れ、母が一段一段上って来る。俺は恐怖で後退さった。
「……どうなの?ん?」母の身体が鼻先で静止し、そしてゆっくり、俺の正面で正座した。「本当は、聞いてたんでしょう?」
俺は目を伏せながら、ゆっくりその場に正座した。「ごめん、なさい……」
パーン!母が強烈に頬を張った。「嘘を、ついたね?」頬を張った。「ママ、いつも言ってるでしょう?」頬を張った。「嘘をついちゃ……」頬を張った。俺の鼻腔を熱いものが伝った。「だめだ、って」頬を張った。拍子、俺の鼻から鮮血が飛び散った。鮮血は金光の中、宙を舞い、パラパラと母のワンピースに降り注いだ。
母の頭がゆっくりとそれに傾いた。そして、しばらく自分の白いワンピースに付着した数滴の血痕を凝視した。「あんた……」母の頭がゆっくり上がり、完全に立ち上がった鋭い眉が現れ、完全に見開いた三白眼が現れ、激しくひきつった口もとが現れた。
「……何てことするの!」母は両手を上げ、俺の短い髪を非常な強さでつかみ上げると、怒り狂って立ち上がった。「どうするの、これ!」そのまま高々と引っ張り上げた。「ええ?どうしてくれるの!」引っ張り上げ、大きく揺すった。「ママの大切なものを!」床に叩き落とした。「どうしてくれるの!」伸しかかって首を絞めた。「返してよ!」覆い被さって首を絞めた。「ほら!返してよ!」首を絞めた。「返して!」首を絞めた。「返して!」首を絞めた。「返して!」首を絞める手が緩んだ。「……」頭上の母の顔が真っ赤に歪んだ。
「返してよぉ!」俺の胸にうずくまり、声を上げた。
陰になった母の肩から金色の光の筋が何本も伸び、それは肩が震えるたびに本数を変えた。胸を締め上げる非常な声が響き渡り、合間にヒグラシは鳴き、母の熱い水が俺の首筋に止めどなく滴り落ちた。
36(近)
文香はベッドで仰向けになったまま、人形のように動かなかった。両目は瞬きもせずに天井を見詰め、唇は力なく半開いていた。
今日で……二日になる。
俺は文香を座らせようと、前から両脇に手を差し入れて上半身を抱え起こした。二本の鎖骨の向こうで文香の首が人形のように垂れ下がり、さらにその向こうで、シーツに広がっていた黒髪が寄り集まった。文香の上体が起き上がり、頭が振り子ように前に垂れると、サイドテーブルにナイフが見えた。俺が昨日買って来たサバイバルナイフだ。
早く来い……そのとき俺は奴と刺し違える。
ベッドに座る文香の背中は力なく丸まり、腕は垂れ、艶を失った長い黒髪はボサボサに乱れて顔を覆っている。俺は棚からブラシを取り出し、電話のプラグが差し込まれているのを確認し、文香の髪に差し当てた。
奴を文香の目前で惨殺する。
文香の頭頂部を綺麗に七三に選り分けた。鋭利な刃と溝で奴の脇腹をえぐり、文香の毛先を手に取ってとかし、陰茎を切り取り、真ん中をとかし、眼球に突き刺し、根もとから真っ直ぐにとかし下ろし、グチャグチャと掻き回す。
その後、切り刻んで肉片になった奴を掻き集め、前髪を横に流し、便器にぶち込み、耳にかけ、その上に俺は脱糞し、背後に廻り、渦を巻かせて流し去り、後ろ髪をとかした。
そして、溜まった水の表面が透明に揺らめいた時……その時こそ……少なくとも俺の……丸まった文香の背中に、背骨が点々と浮き上がっている。
ジュ、ザザ……キッチンで土鍋が噴きこぼれた。俺はタバコを口にくわえ、コンロのつまみをひねって消すと、白濁した汁が土鍋の表面で泡立っていた。
俺はタバコに火を点けた……人間は飲まず食わずでは三日しか生きられないと聞いた憶えがある。
土鍋の蓋を外し、湯気立つ卵雑炊にレンゲを挿した。窓に煙を吐き出して、文香の隣に腰かけると、ベッドが沈み、文香が軽く傾いた。俺はレンゲに雑炊を取り、息を吹きかけてよく冷まし、力なく緩んでいる文香の口に差し出した。
「口、開けろ」だが、文香の唇は動かなかった。
俺は文香のあごをぐっと押し開け、雑炊をそっと流し込んだ。
ゲホッ……文香がむせ込んだ。ゲホッ、ゲホッ……そのたびに雑炊の米粒やグチャグチャの卵が噴き出し……ゲホッ……俺の顔に真っ直ぐ飛来し……ゲホッ……文香の脚やシーツに飛び散り……ゲホッ、ゲホッ……床や壁や……
ゲ、ボォッ……そして嘔吐した。
文香の身体が腰から深く折れ曲がった……ゲホッ、ゲホッ……むせ込むたびに文香の背中の筋肉がピンと張り詰め……ゲホッ……弛緩し……ゲホッ、ゲホッ……張り詰め……
ゲホッ……そして、そのまま動かなくなった。
俺は文香を抱え起こした。文香の膝の間のシーツにはグチャグチャの液体が広がっていて、それと同じ液体が文香の身体の表面でも流れていた。俺はウェットティッシュを引き出した。文香の口の周りには汚物がドロリと流れていて、そこに髪が付着していた。顔から髪を剥がし取り、ティッシュで口の汚物を拭うと、文香の半ば開いた唇や青白く透き通った頬が、そのたびごとに瑞々しく震えた。
俺は文香の頭を抱き寄せた。「頼む……」文香の頭に頬を着けた。「頼む……」腕の中の文香のまぶたは人形のように瞬かなかった。「頼む……」その時……
トゥルルルル!背後で電話が鳴った。トゥルルルル!俺はゆっくりと振り向いた。トゥルルルル!電話機から発せられる着信通知の赤い光が、閉め切った白いカーテンを点滅させた。トゥルルルル!垂れた髪に透けて見える文香の頬が、うっすら微笑んでいるような気がした。
トゥルルルル!俺はゆっくり立ち上がった。トゥルルルル!ローテーブルに置いてあるナイフに映り込んだ白壁が、俺の頭で真っ赤に染まり「くそっ……」奴に一方的に刺し殺される自分が目の前で繰り返しシミュレートされた。トゥル……
「あい……高沢、です……」「俺だ」
……『俺』?
「お前、最近、全然電話に出なかったなあ?んん?さぞ勉強に忙しかったんだろうなあ?ええ?おい……」
「……てめえ」俺は受話器を持ち替えた。「こんなときにかけてくんじゃねえ!」受話器を叩きつけた。するとまたかかって来た。俺は受話器を上げて叫んだ。「かけてくんなって言ってんだろ!」
「……みいちゃん?」トゥルルルル……受話器の中で、キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。
「……どうしたの?」「……いや」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「……何だ」「ああ……あのさ……これから、出てこない?ちょっと話があるんだけど」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「今は無理だ」「どうして?」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「今度にしてくれ」「今度じゃだめなんだよ……今じゃないと……でないと……」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「じゃあ無理だ」「お願い、大事な話なの」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「私にだけじゃない、みいちゃんにとっても大事な話だから」
……受話器の中で、キャッチフォンのコールが消えた。
「……だから、ちょっとでいいから出てきてよ」文香は力なく背中を丸めたまま、瞬きもせずに一点を凝視し「いいでしょう?」キッチンの窓はぼんやり白く光っている。床に落ちた俺の影は淡く、「ねえ、みいちゃん……」ユニットバスのドアは開かれている。
「……場所は?」
246を歩き、山手通りとの立体交差を越え、急勾配の細い階段を下りた。階段は両側を高いビルに挟まれ、そこに車のエンジン音やクラクションが無機質に反響していた。突き当たりにはBALZACに通じる赤いアスファルトの車道があり、それを越えて向こうには、ガラス張りのビルの腹が見えた。
俺は階段の中程に腰かけた。頭上には左右のビルによって長方形に囲われた青空があり、トンボが……トンボがそこに浮いていた。
俺はタバコに火を点けた。かすかにカツカツと靴音がビルに響き、見ると、下方遠く、陽子の姿が階段を上って来るところだった。赤いターバンを巻き、デニムのシャツを着て、腰骨を左右交互に上下させる艶っぽい歩き方で上って来る。俺は煙を吐き出した。煙はビル風に巻き込まれて素早く上昇し、上空で消えた。
「ごめんね、呼び出して」陽子の腰が隣に座った。階段の左側に張り渡されたフェンスは排ガスによって黒ずみ、その足下では色味の薄い雑草が低く生い茂っている。フェンスよりさらに左には煉瓦を模したビルの外壁があり、外壁の向こう端では螺旋階段が縦に渦巻いている。
陽子がタバコに火を点けた。「……このあいだ、THREEにきたお客さんで写真家の人がいて」陽子の唇から吹き出した煙が細く回転しながら消え広がった。「その人、すごいいい空気漂わせてる人なんだけど」陽子の黒いサンダルの先端から鮮やかな紫色の爪が見える。「今度、私を撮らせてくれって言ってきて」俺はタバコの煙を深く吸い込んだ。「そのギャラが、また、すごいの……」正面のビルのガラスに、薄雲の棚引く空が映り込んでいる。
俺は煙を勢いよく吐き出した。「……それで『大事なこと』は?」
陽子の唇がタバコをくわえた。「……んん……」陽子のシャツの襟がはためき、吹き抜ける風が煙を巻き込んで目に見えた。「私……」
ガァー!カラスの鳴き声がした。
「色々考えたんだけど……」その瞬間、俺の頭のつむじの付近で、火花がパーンと弾けるように、極めて嫌な感覚が閃いた。「引っ越し、しようと思って……」感覚はそれを避けるかのように形状を曖昧にしたまま、ぐんぐんと俺の体内で膨脹し「今、どこがいいか、いろいろ考えてて……」ついに、はっきりと、その姿を網膜に現した。
俺の心臓が高鳴った。「……つまり?」
「んん……二人には悪いけど……」心臓が激しく高鳴った。「私、一人になろうと思って……」だが、それが原因ではなかった。
「それがいい」俺は立ち上がり、走り出した。「ちょっと……なんなの!」
渋滞の246を横断し、人混みの歩道を薬局で曲がり、閑散とした袋小路を駆け抜けた。アパートの折り返し階段を駆け上がり、息を切らし、震える指先で鍵を差し込み、回転させた。勢いよくノブを回し、ドアを開いて見た瞬間、俺の膝が脱力した。
なぜ……なぜこんなことに気づかなかった!
「男だったらもっと食べろ」男がテーブルの向こうから箸で俺の皿を指した。「ん?」二つに割れたたくましいあごが髭で青々としている。「ほら」皿を指した。俺はうつむいた。「……ったく」男が食事を頬ばった。
「……ええ、探してるわよ」俺の背後で母が電話をしている。「……うん……今かけ合ってる仕事が、何とかなりそうなの……あ、でも待って……まだはっきり決まったわけじゃなくて……」男の食器がカチャカチャと音を立てている。「……そう……そうよ……だからもう一月だけ……」テーブルに映っている男の顔が、食事を頬ばったり母の方を見たりしている。
この男は、いつまでこの家にいるのだろう?……母の席のテーブルには食べかけの昼食が残されていて、その隣にはほとんど減っていない俺の昼食がある。テーブルに映っている男の顔は母の皿と俺の皿で少しずつ欠けながら、苛立った様子で口を動かしている。
「ご、ち、そ、う、さ、ま」男が電話口に聞こえるような声で言った。「ちょっと!」振り返ると、母が受話器を手で塞いで男をにらみつけていた。「どういうつもり!」振り返ると、男が嫌気の差した顔で笑っていた。「別に」
「あ、もしもし?ごめんなさい。今、知り合いが家にきてて……なあに、その言い方?私がうそをついてるとでも……」男が俺の頭を小突いて「お前のせいだぞ」立ち上がった。
「どうして自分の娘を信じられないの?……いっつもそう……」男の毛深い脚が母の白い脚に寄り、ゴツゴツした大きな手が母の尻を丸く撫でた。母が受話器を耳に当てたまま、男をきつくにらみつけた。「おーこわ」男がおどけて部屋を出た。
「……うそ!お母さん、私のこと一度だって信じてくれたことないじゃない!あのときだってそう!……お母さん、あいつのことばかりかばって……私だけを悪者にして……どうしてなの?ねえ……私のことが、そんなに邪魔なの?」
男が部屋に戻ってきて、歩きざま、母の尻をまた撫でた。瞬間、母が男の頬を力一杯張った。「いい加減にしてよ!」男の目に怒りが走った。「何だぁ?」二人はしばらくにらみ合った。窓からジーッとアブラゼミの声が高鳴った。
「……はん」男が鼻で笑ってソファーに座った。母は背を向けて受話器を耳に当てた。上げられた後ろ髪が首筋にほつれている。「……ごめんなさい、水面がちょっと悪戯……」
母の首筋に二本の筋肉が隆起した。「もういいわ!……分かったわよ!」二本の筋肉が隆起した。「もうあんたなんかに頼まないわよ!……ええ!そうよ!……私が今までどれだけあんたにこき使われて……ちょっと!もしもし!」
「おーおー、凄い迫力ですこと」男がタバコをくわえながらソファーに大きくもたれた。母は受話器を首に当てたまま動かなかった。「ボク、ああいう風にだけはなっちゃだめだぞー?昔からなあ、短気は損気と言って……」母の首筋に当てられた受話器が小刻みに震えた。「おお、今度は涙……全く、自由自在だね」母の頭が向こうに沈んだ。「いい女優になれる……」
「やめろ!」俺は立ち上がり、男をにらみつけた。「……やめろ!」
男は座ったままゆっくりと身を乗り出し、灰皿にタバコの灰を落とした。「……何だ?」男が顔を上げ、じっと俺を見据えた。「……何を、やめるんだ?」えぐるように鋭い目だった。
「いいの」後ろから、母の腕が俺の身体に巻きついた。「いいのよ、水面……ありがとう」後ろから、俺の頭を撫でた。「……ママは大丈夫だから……ね……いい子だから……」俺の頭を撫でた。男はまだ俺を見据えていた。「ほら……」母の手が両肩をつかんだ。
俺はうつむいて、母に導かれるまま部屋を出た。廊下を玄関まで歩き、向き直って、母がしゃがんで頭を撫でた。
「ママ、あの人と大事なお話があるから」俺の身体は恐怖と興奮とで震えていた。「水面はお外に遊びに行ってらっしゃい?ね?いい子だから」母が優しく頭を撫でた。
首をゆっくり縦に傾けると、母は笑顔を残して立ち上がった。後ろ姿がリビングに消えた。
玄関に腰を下ろすと、ドアの横のすりガラスがぼおっと明るく光っていた。スニーカーを履き、見ると、母のハイヒールの横で、男の大きな皮靴が異様な存在感を放っていた。立ち上がり、それを蹴り飛ばそうとして躊躇すると、廊下の奥からかすかに母の声が聞こえた。
……ごめんなさい……
32(近)
「ちょっとなんなの!?勝手にひとの家に上がらないでよ!」玄関から陽子の掠れた金切り声がした。俺はベッドで寝返りを打った。「いるんだろ?」部屋のドアの向こうに男の声が近づいた。勇ましい足音が近づいた。「ちょっと!」なだれ込むようにドアが開いた。
おやおや、たくましい商社マンの登場だ。
「こいつか?」口の周りからあごに沿って生やした髭……いや、剃っていない、と言った方が正しいか……やつれた感じだ。
「出てってよ!」陽子が男の腕を向こうに引っ張っている。だが、そのたくましさにビクともしない。「出てって!」
男はドアノブを手に俺をじっとにらみつけている。やれやれ……合鍵を持った暴漢……しかも嫉妬に狂っている……早いとこ、俺の胸倉をつかんで気の済むまで殴り続けたらどうだ?……血を流し、腫れ上がらせて……いっそ、殺してしまうのはどうだ?
俺は男から目を外し、タバコをくわえて火を点けた。ベッドルームの四角い窓がぼおっと白く輝き、俺の身体を覆う白いカバーがくっきりとしわを陰にしている。タバコの煙がゆっくりと光の中を立ち上り、漂い、広がって行く……何て心地いい倦怠感……ようやく足音が近づいた。
「陽子を、返してくれ」
俺は男を見上げた。どうやら、つまらない冗談ではないらしい。俺の枕もとにしっかりと立ち、両拳を握り締め、男のその真剣な目つきは問いの答えを伺いながらも「はい」という答えしか受けつけない、そういう目だった。
まんざらでもないのだろう、止めに入らない陽子に目をやると、慌てて取り繕うように「ちょっと……」と手を伸ばした。それはそうだろう、『お互いに相手の空気を認めていた』仲だ。
「頼む、お願いだ」男はベッドから一歩下がると床に膝をつき、両手をついて深々と土下座した。シャツの襟首から太い首が見えた。
やれやれ……どうやら『俺』は『陽子』の『所有者』で、その『俺』を泣き落として『自分』が『陽子』の『所有者』になるつもりらしい……しかもその図式に気づきもせずに……俺はタバコを吸い込んだ。
経験上、この類いの人種は、これから自分の心情について、それがあたかも世界を揺るがす重大事であるかのように延々と語り、挙句の果てに『生きられない』に行き着く。語られる相手には、そいつが死のうが生きようが何の意味も持たないにも関わらず。しかも、そう言いながら『死ぬ』ことができない。つまり『生きない』ことと『死ぬ』ことが別のことだと思っている。
「俺には陽子がいないと……」
男は本当に予想した通りの言葉を口にした……それは俺が自分の言葉なのかと錯覚するほどだった……「陽子がいなくなってから、俺は」……知っていることを教えられている感覚……「だめなんだ」……脅迫にもならない脅迫が続き……陽子は……「出てってよ」……男のシャツを引っ張りながら、本当のところ、止める気がない……最後まで聞くつもりらしい……
それなら「ちょっと」俺がやめさせるしかなかった。「あのさ……俺に話す風を装って、実際はようちゃんに話すのやめてくれるか?煩わしいんだよ。直接ようちゃんに話せばいいことだろ?それにあんたが死のうが生きようが、俺には何の意味もない」その気はなかったが、皮肉めいた言い方になった。
「おまえ……」髭だらけの男のあごが近づいた。「もう一遍言ってみろ!」俺の胸倉をつかんだ。陽子が男の背中から抱きつき、仲裁した。「いい加減にしてよ!」
……何で俺が、この二人の痴話喧嘩に巻き込まれなければならないんだ?
どこかの応援団のような嗄れた叫び声を上げながら「ぶっ殺してやる!」男が後ろ向きで引き摺られて行った。陽子に引き摺られるくらいだ、本当は俺のことを殺すつもりはなかったんだろう。全く、演技好きな奴だ。
ダン!玄関のドアが蹴られた。
俺はタバコを深く吸い、枕もとにある一冊の躍動的な本を開いた。躍動……確かにその全てが美ではなく、美の全てが躍動でもなかったが、躍動の一部が美の一部であることは確かだった。本の表紙は赤かったが、その題名までは知らなかった。
「……ちょっと、ひどいんじゃない?」戻って来た陽子の責めるような目は、それが疑問文ではなく、肯定文だということを表していた。そこからさらに連鎖して……
俺が男と言い争い、それによって陽子の地位を高め、そうしてから、俺が男を説き伏せ、陽子が男から恨まれることのないようにし、そうしてから、陽子が俺に独占されている感覚を得る、つまり陽子が俺を独占すること、を望んでいた。
俺はベッドから立ち上がった。「どこ行くの?」キッチンに出て、トイレのドアを開けた。二畳ほどの洋式トイレだが、コバルトブルーのライトが好きだった。便器の蓋と便座を持ち上げ、勢いよく放尿した。溜まった水が一瞬にして細かく泡立ち、その白なのか青なのか判然としない泡を貫くように、下腹部に力を込めた。便器を挟んでいる俺の両足が生々しかった。
キッチンの蛇口を捻り、手を洗い、風呂を見て、レコードの部屋をよく眺めながら過ぎ、ベランダに出た。風が割と強かった。
左右の隅に置かれた鉢植えの葉がガサガサと騒ぎ、だが、空は夏の青だった。春、秋の包み込むようなそれとは違い、刺すような日差しが全身に心地好かった。粉塵で黒く汚れた首都高も、それはそれで夏だった。自尊心が傷ついたのか、あるいは欲求が満たされなかったのか、とにかくその辺りと葛藤していたのだろう陽子が部屋から出てくるまでには、まだ時間があった。俺は椅子を引いて大きく背もたれた。
文香は?
そうだ……カラーストッキングを履かせよう……光の角度によって緑色や紫色に変化する……そう、玉虫色のやつだ……あの美しい脚線に、妖艶な色彩を加え……小振りだが艶かしい乳房を片手でつかみ……喜びに歪んだ顔を何度も噛んで……挿入しそうで、しない……そうやって二日間過ごそう……そうだ……それがいい……ようやく陽子が現れた。
「みいちゃ……」「よく考えればいい。俺は帰る」陽子の髪を上げ、首筋に口づけて部屋を出た。
山手通りは街路樹や遠くからセミの声がして、バイクのエンジン音が紛れるほどだった。左前方のビルは窓から黒いよだれを垂らし、横断歩道の先では工事中のビルが頭にクレーンを乗せていた。坂を上り、246を横切って、薬局の店内で文香の脚線をイメージした。
そして袋小路に入って行った。右手に薬局の袋を提げ、口にタバコをくわえ、公園では、藪蚊に襲われる子供たちが遊んでいた。俺は足を止め、鉄棒の横にあるスプリングつきの木馬にまたがった。木馬の頭を貫くグリップを握り、子供たちの視線を浴び、そして前後しながら激しく叫んだ。
「文香!今帰ってやるからな!」
33(遠)
公園のブランコで、陽子と俺は前後に大きく揺れていた。頭上では、高木が太い枝を四方に張り巡らせていて、葉と葉の隙間から光の筋が差していた。ジーッと煽るようにセミは鳴き、陽子の身体の表面には木漏れ日のかけらが次々と流れていた。
「どっちが靴を遠くまで飛ばせるか、競争ー!」陽子のブランコが風を切りながら下りてきて、地面に最も近づいた瞬間、陽子の右足から白いスニーカーが飛び立ち、木陰を抜けて青空に舞った。
スニーカーはゆっくりと回転しながら空を泳ぎ……飛行機雲を通過して……砂場よりもずっと向こう……鉄棒の手前に降下して……地面に跳ね返り……転がり……鉄棒を越えて……停止した。
「みいちゃんもはやくー!」陽子が靴のない脚だけ前に伸ばして大きく前後に揺れていた。俺は靴のかかとを外し、地面に最も近づいた瞬間「タァ」足を蹴り出して飛ばした。
だが、靴はほとんど真上に上がり……飛行機雲さえ越えることなく……砂場の手前で跳ね返り……こちらに向かって転がった。
「ハハハハハ!」左で陽子の掠れた笑い声が前後した。「ヘタクソー!ハハハハハ……」笑い声が前後した。「ハハハハハ……」笑い声が前後した。
笑い声が前後した。
「おい、あれ、こないだ転校してきた……」公園の入口から、野球帽を被った三人組の少年達が自転車に乗って入ってくるのが見えた。二人の少年は補助輪を片方だけつけた自転車に乗り「……だよ」一番年長に見えるもう一人の少年は、大きな自転車を三角乗りしている。
三人は公園の外周の道を、ジグザグ運転しながら遠巻きに近づき「……やっぱりそうだよ……」背後に廻り、こちらを見ながら右に抜けて行った。陽子はうつむきながらザッ、ザッと片足で地面を擦って減速し、ブランコを下りて俺を見上げた。
「……みいちゃん、あっち行こ」陽子が片足でケンケンと跳ねながら、飛ばしたスニーカーを拾いに行った。俺も地面に足を擦り、ブランコを停止させると、深く掘れた砂が靴の隙間から侵入した。「はやく、行こ」陽子が俺の靴を差し出した。
公園を出て雑木林を抜けると、昼下がりの日を浴びた青い水田が地平線の山の麓まで広がっていて、その真ん中に、真っ直ぐ農道が伸びていた。農道の途中には市民プールと清掃工場の煙突があり、左手には住宅地があった。
陽子はポニーテールを揺らしながらあぜ道に下りた。俺も後に続いて飛び下りると、足下の水田で細長いドジョウが泥の煙幕を巻き上げて逃げた。ザリガニを探して覗き込みながら歩いて行くと、コンクリートの円い筒でできた農業用水の引き入れ口を発見した。両膝を突いて筒の中を手で探ると、鈍い痛みが指先を挟み、徐々にその力を強めて行った。
「ようちゃん、ザリガニ!」だが、陽子の後ろ姿は振り向かずにあぜ道を歩いて行った。
ザリガニに指を挟ませたまま引き揚げようとすると、放したのか、鈍い痛みが消えた。俺はさらに深く手を差し入れ、ヌルヌルとした筒をひとしきり探った。だが、ザリガニの身体はついに指に触れなかった。諦めて手を引き抜くと、腕に二匹の赤黒いヒルが付着していた。俺は素早くそれを払い落とすと、ヒルは力なくUの字になって宙を舞い、水田に張られた水に波紋を立てて沈んで行った。
「みいちゃん」陽子が一つ先のあぜ道の十字路で立ち止まった。「だれにも、言ってないよね?」陽子がしゃがみ込み、足下の草を引き抜いた。
「……なにを?」俺はヒルの着いていた腕を擦った。「……あのことだよ……だれにも言わないって、約束したでしょ?」陽子が再び歩き出した。俺は走って追いついた。
稲の先端には、まだ殻は青いが、大きく実った稲の穂が頭をわずかに垂れていた。歩きながら三粒ほど米をそぎ取り、殻を剥いて口にすると、干し草のような粉っぽい味がコリコリと前歯に心地好かった。
その時「ふじしろーがおーとこーとあっちっちー、ふじしろーがおーとこーとあっちっちー……」さっきの三人組がはやし立てながら、右手の農道を通過した。陽子が両拳をきつく握った。
あぜ道の十字路をいくつも過ぎ、小川を跳び越えて着地すると、ゆるんだ土手に四つの靴跡が残った。水田を抜けて空地に出ると、陽子が何も言わずに走り出した。俺は後を追いかけた。夏草の鋭い葉で肌を切り、苔の生えたブロック塀の細道を走り抜け、成熟したヒマワリを化粧ブロックの隙間に見ると、砂利の敷かれた駐車場に出た。四方に打ち込まれた木の杭に誰かの学校用の運動靴が干されていた。
そこから大通りに出て、コンクリートの川に沿って路肩を歩いた。川を挟んで向こうには背の高い生け垣があって、その天辺より上では真新しい藍色の屋根瓦が光っていた。継ぎ接ぎのある古びたアスファルトの路面は所々に赤サビのような染みがあり、行き交う全ての車の窓は暑苦しそうに開かれている。陽子のヤセッポッチの脚が路側帯の白線に沿って歩き、その影がほとんど真下に落ちている。
「……ようちゃん、宿題、終わった?」陽子のやせっぽっちの両腕が、バランスを取るように軽く開いた。「まだ」陽子の上半身がバランスを失って左右に大きく揺れ、ついに白線から路肩に足を着いた。「今日も家を出るとき、お母さんとけんかした」今日は俺が誘い出したのだった。
陸橋を上り、眼下に線路を見下ろすと、三両編成の電車が通った。電車の行く先には古びた木造の駅があり、駅より左手には、これも古びた市街地が広がっている。右手には半円形の天体望遠鏡を屋上に頂く高校があり、その周囲を住宅が取り囲んでいる。
手摺には、大きなカマキリが腹部を膨らませたり縮めたりしながらじっと獲物を待っていた。「ようちゃん、カマキリ……」手を伸ばすと、カマキリは大きな羽を広げて異様に飛び去った。その時、声が近づいた。
「ふじしろーがおーとこーとぶっちゅっちゅー……」またあの三人組だった。「ふじしろーがおーとこーとぶっちゅっちゅー……」どうやらつけ回しているらしかった。
ついに陽子が振り向いた。「ちょっと!」三人組の行く手を遮り、立ち塞がった。「あんたたち、こんなことして楽しいの!」
三人は近くまで来て自転車を止めると、一番年長に見える少年が歩み出た。「なんだ?」陽子に迫り、顔を突き合わせた。「転校生のくせに、生意気だぞ」少年の顔が近づいた。
その時……パーン!……陽子が少年の頬を張った。少年の野球帽が横にずれた。「なによ!転校したこともないくせに!」
少年が頬を押さえた。「……ってえな!このブス!」三人は慌てて自転車にまたがると「デブ!」走り出し「チビ!」叫びながら坂を下って行った。
「みいちゃん!」陽子が俺に振り返った。「どうして約束やぶったの!?」陽子のかん高い掠れ声が空に響いた。「やぶってない……」「うそ!」陽子が俺の肩を両手で突いた。「うそ!」突いた。「うそ!」突いた。
ドサッ!……俺は仰向けに転倒した。
「あ……」陽子が慌てて駆け寄った。「だいじょうぶ?」すぐ目の前に陽子の膝頭がしゃがみ込んだ。「だいじょうぶ?」陽子が心配そうに顔を覗き込んだ。「だいじょうぶ?」
「……僕」俺はゆっくり起き上がり「言ってないよ!」陽子の腹を目がけて突進した。その拍子、陽子は路面に後頭部を痛打して「いたい!」両手で頭を抱え込んだ。
陽子の顔が一気に歪んだ。「いたい……」陽子の顔が一気に赤らみ、目尻からどっと涙がこぼれた。「いたいよ……」陽子の口が『うえーっ』という泣き声とともに、糸を引きながら真っ赤に開いた。
俺は慌てて手を伸ばし、陽子の後頭部をさすった。「ごめんね」後頭部をさすった。「ごめんね」後頭部をさすった。「ごめんね」だが、陽子は泣きながら首を横に振り「ごめんね」俺の手を振り払って立ち上がると「ごめんね」走って坂を下って行った。「ごめんね……」
空は……空は青かった。
俺はその場に座り込んだ。真上にはギラギラと太陽が揺らめいていて、その横に、トンボが三匹浮いていた。トンボは羽ばたくたびに位置を変え、だが、いつまでもそこにいた。下からセミの声がして、時々、電車が通過した。目の前を車が疎らに通り過ぎ、その間、俺は日が暮れないのをずっと恨んでいた。
34(近)
ドアを開いた。「文香、もう少し綺麗に食べられないのか?」床にはスーパーのトレーやラップ、野菜の芯や皮など、冷蔵庫の中のあらゆるものを食べ荒らした痕跡が生臭く散らかっていた。俺はそれらを足でどけ、冷蔵庫のドアを開いた。棚にはビールが二本残っているだけだった。
「文香……」俺はプルタブを上げた。「……何、してる」文香はベッドの上で、必死に身体を隠すようにシーツを胸に当て、怯え切った目で俺から後退さっていた。
「……何を、してんだ?」俺はビールを飲みながらベッドに近づいた。文香はじっと俺を見詰めながら、手足をもつれさせて後退さった。俺はビールを床に投げ、大股で文香に詰め寄った。「何をしてんだ!」逃げる文香の手首をつかんだ。
いやあああああああ!……文香が白目を剥き、狂人のように叫んだ。
「何だ、これ……」なおも逃げようとする文香の細い腕に、青紫色のアザがくっきりとついていた。二センチ幅の四本のアザが、まるで人間の指のように文香の腕に巻きつき……いや……それは確かに人間の指だった。
文香は俺に腕をつかまれたまま鬼気迫る形相でベッドを後退さり、そのまま床にドサリと落ち、背を向けて這いつくばり、なおも俺から逃げようとした。腕が抜けそうなほど肩は陥没し、長い髪が激しく騒ぎ、美しい背筋が曲がりくねり、腰の曲線が左右にねじれた。
「文香!」俺は力一杯文香の腕を引き寄せた。いやああああ!白目を剥き、鼻から口から熱い液体を垂れ流している文香を、拘束衣のようにきつく抱き締めた。「文香!」いやああ!「文香!」いやぁぁ……
腕の中で抗っていた文香の動きが、徐々に、徐々に、沈静した。
「文香……」俺は文香の頭に口づけた。腕の中で文香はしきりに首をひきつらせていた。「文香……」俺は温めるように文香を抱き締め、口づけた。文香は足首にも同様のアザをつけていた。
何が、あった?
こんなにくっきりアザが残っているということは……文香の握力を考えれば、自分で握ってつけたとは考えにくい……ということは、俺と文香以外の第三者がつけたことになる……しかも力の強い……恐らく大人の男だ……
ゴミの散乱した床をよく見ると、かすかに靴跡のような汚れがあちこちにあった。それは記憶の範囲では俺の靴跡ではなかった。本棚やクローゼットの散乱した様子も、見方によっては争った形跡に見えなくもなかった。
そうすると……やはり誰かがこの部屋に侵入し……両手両足首にアザがついているということは……『大』の字に張りつけられるような格好で手足を広げられ……つまり……犯された?
俺は抱く腕を緩め、中の文香を覗いた。文香の両脚は人形のように不自然に『く』の字に折れ曲がり、背中は老婆のように丸まり、両腕は力なく垂れ、目も口も完全に放心し、半ば開いていた。俺はもう一度強く文香を抱き締め、頬を頭に押しつけた。
誰が……一体「誰が!くそったれ!」文香の背中が折れ曲がるほどきつく抱き締めた。
その時、電話が高く鳴り響いた。「誰だ!お前か!お前だ!殺してやる!ぶっ殺してやる!」電話が高く鳴り響いた。「首を引き千切り、ぐちゃぐちゃに踏み砕き」電話が高く鳴り響いた。「絶対に、今すぐ、ぶっ殺してやる!」電話が高く鳴り響いた。
文香は腕の中で折れ曲がり、放心して天井を見上げていた。
電話が高く鳴り響いた。俺は受話器を上げた。「うるっせえんだよ!」叩きつけて切った。するとまた鳴り響いた。俺は受話器を上げた。「うるせえって言ってんだろ!」「うるせえのはてめえだろうが!」
受話器の向こうで、ドスの効いた男の声が叫んだ。「あぁ!?」ドスの効いた声が叫んだ。「違うかこら!?おお!?」ドスの効いた声が叫んだ。
……何だ?この感じは……
「てめえ、いつんなったら金返すんだ!?あぁ!?次はあんなんじゃ済まねえぞ!?あぁ!?こら!聞いてん……」受話器を置いた。するとまたかかってきた。受話器を上げて置いた。だが、またすぐにかかってきた。俺はプラグに手を伸ばし、抜いた。
……『次はあんなんじゃ済まねえぞ』?
……『次は』?
……『次』?
文香を両腕で抱え上げると、頭と腕がダラリと垂れた。開け放たれた両目が壁に向かって白目を剥き、それでいて、乳房の揺れる様子は瑞々しかった。左腕には赤らんだ膝頭が二つあり、その先で、上下に振れる足先が愛おしかった。
俺はベッドにゆっくり文香を下ろした。そしてシャツを脱ぎ、ズボンを下ろし、挿入した。文香は乾いていた。だが俺は濡れていた。人形のようにピクリとも動かない文香に入れて出し、出して入れ、乳房をわしづかみにした瞬間、時空を越えて、俺は強姦魔と一致した。
全ては俺から派生したこと……文香の小振りな乳房が震えるように回転し、かすかに浮かび上がる肋骨の『ハ』の字がうごめいている。腹筋にあいた美しい縦ベソ。腰骨の間の三角地帯。艶やかな二本の腿のつけ根を割って、俺は情熱的に前後する。
虚空を見詰める文香の瞳……そこにはきっと……気が狂いそうなほど鳴り響くチャイム……破れそうなほど蹴られるドア……鼓膜の奥に届く罵声……恐る恐るドアを開け……だが愚かにも全裸の文香……男の顔は獣に変化し……押し倒され……揉み合い……両足を開かれて……
……いやああぁやめてえぇぇぇ水面ぉ水面ぉぉ……
俺は陰茎を引き抜き、文香をうつぶせに転がした。奇跡の感覚を禁じえない美しい背筋、そしてその下降曲線。瑞々しく盛り上がる尻をわしづかみ、左右に開き、肛門に辿り当て、挿入する。そしてその美しい背中に覆い被さる。
……もはやカラータイツが必要でないことは明白だろう……
俺の目の前には振動する文香の後頭部がある。
35(遠)
「ただいま……」ドアの形に夕日が差し込み、玄関のタイルの床に俺の影が長く落ちた。背中からヒグラシの声が流れ込み、ひっそりと静まり返った廊下の奥まで響いて行った。右手には一着もかけられていないコートかけがあり、その骨格が壁に等身大に投じられていた。
靴を脱ぎ、リビングのドアをそっと開けると、母と男がソファーでじっと押し黙っていた。男は母から顔を背けて壁をにらみ、母は男の膝に片手を置いて視線を床に落としている。
「ただいま……」とつぶやくと、母がゆっくり目を上げた。
「もう……帰ってきたの……」
母は物憂げに立ち上がり、ゆっくりこちらに歩いて来ると、俺の両肩に手を乗せて「水面、ちょっと……」と、そっと廊下に連れ出した。
母に背を押されるまま廊下を歩き、階段の上り口まで来ると、肩をゆっくり振り向かされた。母の白いワンピースの腰にしわが立ち、母の顔が目の前にしゃがみ込んだ。
「ママ、大事なお話がまだ終わってないから……」母の生臭い息が鼻を突いた。「もう少し二階に上がっていて?」夕日を真横から浴びた母の顔が傾き、目鼻の陰影が際立った。「ね……」金光の差し込んだ母の黒目がガラス玉のように輝き「さ……」俺の背中を階段に押した。
階段を上る自分の影が、前方の段に添って折れ曲がる。母は上り口で俺が上り切るのを見届けると、リビングの方に歩いて行った。俺は最上段に腰かけた。
階段の上り口に見える廊下の床板が、その境目を曖昧にしながらまぶしく金色に輝いている。その最も明るい部分は溶鉱炉でドロドロに溶けた鉄のように流動的に輝いている。
何これ……階下から母の声がした。……何のつもり……「いい加減にしてよ!」ドアの開く音がした。
「それじゃあ不足か!」男の怒鳴り声が廊下に響き渡った。「もっともっと金を出せ、か!ハハハ!そりゃあそうだ!そのために俺に『またがった』んだからな!」
「だから!違うって言ってるでしょ!」
「何が違う!」
「何から何まで違うわよ!」
「はん……」廊下のきしむ音がして「……何が『結婚しない?』だ……ハッ……最初からおかしいと思ってたんだ……」階段の上り口の前を男の足が通り過ぎ、すぐに母の足が続いた。
「……ねえお願い……本当に違うのよ……」布の擦れる音がした。「どう言えば分かってくれるの……」
廊下のきしむ音がした。「じゃあ、あれは何だ?ん?……あの紙は、何だ!」「だからあれは……前の主人が借りた……」「離せ!」布のはためく音がした。
「……何が前の主人だ……」廊下がきしみ、靴音がした。「……今朝、電話で話してたことも嘘なんだろ?」「何のことよ……」「職を見つけたとかどうとか、あれはつまり俺のことなんだろ?……そうなんだろ!」
「違うわよ!」
「じゃあどんな職に就いた!ああ!どんな職に就いたか言ってみろ!」
「銀行の……経理よ」
「言ってろ……」カツカツと靴音がして「待ってよ!」母の声とともに玄関の外へ遠ざかって行った。
入れ替わり、ヒグラシの声が金色の階段を涼しく上って来た。日に焼けた砂の匂いが吹き抜け、ドロドロに溶けた鉄の輝きは、最下段のへりにまで達していた。荒々しく玄関に靴音が戻って来て、俺は気づかれないように部屋に入ろうと、そっと腰を上げた瞬間、上り口に母の目が見えた。
「……盗み聞き、したね?」
母は寒気がするほど冷酷な目で俺をじっと見詰めた。俺は首を横に振った。「そうなんだね?」母の片足が階段に乗せられた。俺は首を横に振った。「怒らないから、正直に言いなさい?」母の膝が一段一段上って来る。俺は首を横に振った。「ママの話、聞いてたんでしょう?」白いワンピースの腿がしわを立てながら片方ずつ持ち上がり、わずかに血管を浮き上がらせた両腕が前後に揺れ、母が一段一段上って来る。俺は恐怖で後退さった。
「……どうなの?ん?」母の身体が鼻先で静止し、そしてゆっくり、俺の正面で正座した。「本当は、聞いてたんでしょう?」
俺は目を伏せながら、ゆっくりその場に正座した。「ごめん、なさい……」
パーン!母が強烈に頬を張った。「嘘を、ついたね?」頬を張った。「ママ、いつも言ってるでしょう?」頬を張った。「嘘をついちゃ……」頬を張った。俺の鼻腔を熱いものが伝った。「だめだ、って」頬を張った。拍子、俺の鼻から鮮血が飛び散った。鮮血は金光の中、宙を舞い、パラパラと母のワンピースに降り注いだ。
母の頭がゆっくりとそれに傾いた。そして、しばらく自分の白いワンピースに付着した数滴の血痕を凝視した。「あんた……」母の頭がゆっくり上がり、完全に立ち上がった鋭い眉が現れ、完全に見開いた三白眼が現れ、激しくひきつった口もとが現れた。
「……何てことするの!」母は両手を上げ、俺の短い髪を非常な強さでつかみ上げると、怒り狂って立ち上がった。「どうするの、これ!」そのまま高々と引っ張り上げた。「ええ?どうしてくれるの!」引っ張り上げ、大きく揺すった。「ママの大切なものを!」床に叩き落とした。「どうしてくれるの!」伸しかかって首を絞めた。「返してよ!」覆い被さって首を絞めた。「ほら!返してよ!」首を絞めた。「返して!」首を絞めた。「返して!」首を絞めた。「返して!」首を絞める手が緩んだ。「……」頭上の母の顔が真っ赤に歪んだ。
「返してよぉ!」俺の胸にうずくまり、声を上げた。
陰になった母の肩から金色の光の筋が何本も伸び、それは肩が震えるたびに本数を変えた。胸を締め上げる非常な声が響き渡り、合間にヒグラシは鳴き、母の熱い水が俺の首筋に止めどなく滴り落ちた。
36(近)
文香はベッドで仰向けになったまま、人形のように動かなかった。両目は瞬きもせずに天井を見詰め、唇は力なく半開いていた。
今日で……二日になる。
俺は文香を座らせようと、前から両脇に手を差し入れて上半身を抱え起こした。二本の鎖骨の向こうで文香の首が人形のように垂れ下がり、さらにその向こうで、シーツに広がっていた黒髪が寄り集まった。文香の上体が起き上がり、頭が振り子ように前に垂れると、サイドテーブルにナイフが見えた。俺が昨日買って来たサバイバルナイフだ。
早く来い……そのとき俺は奴と刺し違える。
ベッドに座る文香の背中は力なく丸まり、腕は垂れ、艶を失った長い黒髪はボサボサに乱れて顔を覆っている。俺は棚からブラシを取り出し、電話のプラグが差し込まれているのを確認し、文香の髪に差し当てた。
奴を文香の目前で惨殺する。
文香の頭頂部を綺麗に七三に選り分けた。鋭利な刃と溝で奴の脇腹をえぐり、文香の毛先を手に取ってとかし、陰茎を切り取り、真ん中をとかし、眼球に突き刺し、根もとから真っ直ぐにとかし下ろし、グチャグチャと掻き回す。
その後、切り刻んで肉片になった奴を掻き集め、前髪を横に流し、便器にぶち込み、耳にかけ、その上に俺は脱糞し、背後に廻り、渦を巻かせて流し去り、後ろ髪をとかした。
そして、溜まった水の表面が透明に揺らめいた時……その時こそ……少なくとも俺の……丸まった文香の背中に、背骨が点々と浮き上がっている。
ジュ、ザザ……キッチンで土鍋が噴きこぼれた。俺はタバコを口にくわえ、コンロのつまみをひねって消すと、白濁した汁が土鍋の表面で泡立っていた。
俺はタバコに火を点けた……人間は飲まず食わずでは三日しか生きられないと聞いた憶えがある。
土鍋の蓋を外し、湯気立つ卵雑炊にレンゲを挿した。窓に煙を吐き出して、文香の隣に腰かけると、ベッドが沈み、文香が軽く傾いた。俺はレンゲに雑炊を取り、息を吹きかけてよく冷まし、力なく緩んでいる文香の口に差し出した。
「口、開けろ」だが、文香の唇は動かなかった。
俺は文香のあごをぐっと押し開け、雑炊をそっと流し込んだ。
ゲホッ……文香がむせ込んだ。ゲホッ、ゲホッ……そのたびに雑炊の米粒やグチャグチャの卵が噴き出し……ゲホッ……俺の顔に真っ直ぐ飛来し……ゲホッ……文香の脚やシーツに飛び散り……ゲホッ、ゲホッ……床や壁や……
ゲ、ボォッ……そして嘔吐した。
文香の身体が腰から深く折れ曲がった……ゲホッ、ゲホッ……むせ込むたびに文香の背中の筋肉がピンと張り詰め……ゲホッ……弛緩し……ゲホッ、ゲホッ……張り詰め……
ゲホッ……そして、そのまま動かなくなった。
俺は文香を抱え起こした。文香の膝の間のシーツにはグチャグチャの液体が広がっていて、それと同じ液体が文香の身体の表面でも流れていた。俺はウェットティッシュを引き出した。文香の口の周りには汚物がドロリと流れていて、そこに髪が付着していた。顔から髪を剥がし取り、ティッシュで口の汚物を拭うと、文香の半ば開いた唇や青白く透き通った頬が、そのたびごとに瑞々しく震えた。
俺は文香の頭を抱き寄せた。「頼む……」文香の頭に頬を着けた。「頼む……」腕の中の文香のまぶたは人形のように瞬かなかった。「頼む……」その時……
トゥルルルル!背後で電話が鳴った。トゥルルルル!俺はゆっくりと振り向いた。トゥルルルル!電話機から発せられる着信通知の赤い光が、閉め切った白いカーテンを点滅させた。トゥルルルル!垂れた髪に透けて見える文香の頬が、うっすら微笑んでいるような気がした。
トゥルルルル!俺はゆっくり立ち上がった。トゥルルルル!ローテーブルに置いてあるナイフに映り込んだ白壁が、俺の頭で真っ赤に染まり「くそっ……」奴に一方的に刺し殺される自分が目の前で繰り返しシミュレートされた。トゥル……
「あい……高沢、です……」「俺だ」
……『俺』?
「お前、最近、全然電話に出なかったなあ?んん?さぞ勉強に忙しかったんだろうなあ?ええ?おい……」
「……てめえ」俺は受話器を持ち替えた。「こんなときにかけてくんじゃねえ!」受話器を叩きつけた。するとまたかかって来た。俺は受話器を上げて叫んだ。「かけてくんなって言ってんだろ!」
「……みいちゃん?」トゥルルルル……受話器の中で、キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。
「……どうしたの?」「……いや」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「……何だ」「ああ……あのさ……これから、出てこない?ちょっと話があるんだけど」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「今は無理だ」「どうして?」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「今度にしてくれ」「今度じゃだめなんだよ……今じゃないと……でないと……」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「じゃあ無理だ」「お願い、大事な話なの」キャッチフォンのコールが遠く聞こえた。「私にだけじゃない、みいちゃんにとっても大事な話だから」
……受話器の中で、キャッチフォンのコールが消えた。
「……だから、ちょっとでいいから出てきてよ」文香は力なく背中を丸めたまま、瞬きもせずに一点を凝視し「いいでしょう?」キッチンの窓はぼんやり白く光っている。床に落ちた俺の影は淡く、「ねえ、みいちゃん……」ユニットバスのドアは開かれている。
「……場所は?」
246を歩き、山手通りとの立体交差を越え、急勾配の細い階段を下りた。階段は両側を高いビルに挟まれ、そこに車のエンジン音やクラクションが無機質に反響していた。突き当たりにはBALZACに通じる赤いアスファルトの車道があり、それを越えて向こうには、ガラス張りのビルの腹が見えた。
俺は階段の中程に腰かけた。頭上には左右のビルによって長方形に囲われた青空があり、トンボが……トンボがそこに浮いていた。
俺はタバコに火を点けた。かすかにカツカツと靴音がビルに響き、見ると、下方遠く、陽子の姿が階段を上って来るところだった。赤いターバンを巻き、デニムのシャツを着て、腰骨を左右交互に上下させる艶っぽい歩き方で上って来る。俺は煙を吐き出した。煙はビル風に巻き込まれて素早く上昇し、上空で消えた。
「ごめんね、呼び出して」陽子の腰が隣に座った。階段の左側に張り渡されたフェンスは排ガスによって黒ずみ、その足下では色味の薄い雑草が低く生い茂っている。フェンスよりさらに左には煉瓦を模したビルの外壁があり、外壁の向こう端では螺旋階段が縦に渦巻いている。
陽子がタバコに火を点けた。「……このあいだ、THREEにきたお客さんで写真家の人がいて」陽子の唇から吹き出した煙が細く回転しながら消え広がった。「その人、すごいいい空気漂わせてる人なんだけど」陽子の黒いサンダルの先端から鮮やかな紫色の爪が見える。「今度、私を撮らせてくれって言ってきて」俺はタバコの煙を深く吸い込んだ。「そのギャラが、また、すごいの……」正面のビルのガラスに、薄雲の棚引く空が映り込んでいる。
俺は煙を勢いよく吐き出した。「……それで『大事なこと』は?」
陽子の唇がタバコをくわえた。「……んん……」陽子のシャツの襟がはためき、吹き抜ける風が煙を巻き込んで目に見えた。「私……」
ガァー!カラスの鳴き声がした。
「色々考えたんだけど……」その瞬間、俺の頭のつむじの付近で、火花がパーンと弾けるように、極めて嫌な感覚が閃いた。「引っ越し、しようと思って……」感覚はそれを避けるかのように形状を曖昧にしたまま、ぐんぐんと俺の体内で膨脹し「今、どこがいいか、いろいろ考えてて……」ついに、はっきりと、その姿を網膜に現した。
俺の心臓が高鳴った。「……つまり?」
「んん……二人には悪いけど……」心臓が激しく高鳴った。「私、一人になろうと思って……」だが、それが原因ではなかった。
「それがいい」俺は立ち上がり、走り出した。「ちょっと……なんなの!」
渋滞の246を横断し、人混みの歩道を薬局で曲がり、閑散とした袋小路を駆け抜けた。アパートの折り返し階段を駆け上がり、息を切らし、震える指先で鍵を差し込み、回転させた。勢いよくノブを回し、ドアを開いて見た瞬間、俺の膝が脱力した。
なぜ……なぜこんなことに気づかなかった!