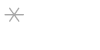こんなものを書き続けて何になる?
2001年 木戸隆行著
こんなものを書き続けて何になる?と問う者もいるだろう。僕のなかに。だがそれはすでに前提のなかで否定されているはずだ。にもかかわらず、この問いは繰り返される。まるで生きる僕のように。僕は巣と餌場との間を弦を描いて往復する焦っている少年だ。地面にじっと目をこらし、背を丸めながらいそいそと足を速めている。そのときに背後に拡がるのは無情で素朴な空なのだ。いつしかそれは決定的な壁となって僕の耳のなかにホーンのような形をしながら吸い込まれるだろう。僕の耳のなかは限りない広がりをもって忽然と消え去る。レースのナイトドレスの裾はあたたかなカーペットの毛足を撫でながら歩く。それは一途なコウノトリの群れだ。コウノトリはその胃袋のなかで、飛びながら、数知れぬ子供たちを溶かしている。その消化が終わる前に奴らの首に縄を投げ、腹を見るからに太いナイフでかっ捌いて出てきたのが僕たちだ。僕たちは血塗られている。生まれながらに罪深い僕たちが、罪というものをこれっぽっちも理解することができないのはこのためだ。例えばイエスキリストが張り付けにされた十字架は、今ではコピーされて世界中に出回っている。例えばユダヤの黒いスーツに身を包んだ白髭の老人たちは、嘆きの壁を聖地とする。嘆き、それが聖なるものなのだ。ハイデガーは絶望こそが死に至る病だと説いた。だが死に至る病は僕たちのなかに生まれながらにして住み着いている。
灯されたランプのもとに暗闇の虫が疼いているのが見えない。圧倒的多数の女の足首が僕の顔の周りを歩く。くるぶしの数が異常だ。それを大きな蓮の葉で一つ一つ包み、蒸し焼きにして、ぼろ布の屋根の広場の市場で売るのだ。行き交う男の太った首が汗ばんでいる。汗はくたくたのシャツのカラーを浸し、黄ばんだ帽子を脱いで汗を拭うその姿が非常に好ましい。深夜の暗闇で木々がざわめくのは、実はその木の根元に干乾びた赤いドレスが埋まっていることを教えているのだ。僕はそれを掘り起こす。その土まみれのボロに頬擦りをすると、僕のなかに果てしない感触の喜びが拡がる。このドレスをかつて着ていたであろう一つの体をあてもなく思い描くと、曖昧さは曖昧さのまま神々しい光を帯びる。そこに全てを見出だせる人は限られている。その限られた人のなかの一人である僕は、時を忘れて二十年以上そうしているつもりだ。洗濯ばさみをそこここにはさみながら。
さて、全ては終わりに近付いていた。なぜなら全てを覆い隠していた夜が、もはや堪え切れなくなって告白めいてきたからだ。その告白は地上にいる全ての頭のうえに降りかかるだろう。道なき道を転げ落ちる一つのいびつなオレンジと、石畳の道を悠々と歩いて下る青年のあいだに、一本の鋭い稲妻が落ちる。彼は一体何を見ただろう?道端にある水桶は波紋をいつまでも波立てている。それは限りない真円だ。月は見るからに痩せ細り、いまだに太陽を待ち侘びている。だが無情にも、太陽はそんなことを少しも気に掛けてはいない。彼は無頓着さの塊であって、それを燃やして生きている。大きな瑪瑙石の柱が今にも倒れかかってくる。きらきらと輝きながら。レオナルドダヴィンチの描いた夢は、夢のまま終わる。また、ノーベルの作った世界貢献の代名詞であるあの賞が、ベトナムの空を焼き、ロシアの炭鉱を削り取る。その巨大な人造のクレーターは、カルデラの存在を見違えるほど陳腐にした。動物実験のラットは檻のなかで鼻をひくつかせながら餌を待っている。もしかしたらエロスは存在しないかもしれないなどと今は思えないが、ジキルとハイドを読みたいと突然思っても、決して読みはしないだろう。軒に干された百枚のブラジャーが風に揺れる。目を遣ると、町の窓という窓にはブラジャーが干されているではないか!こんな異常な町に住む僕は、何という興醒めな真珠貝だろう!腿にタバコの焼け焦げのあるズボンを履きながら、ポマードで髪を固めて、さて行くところは町の穴だ。暗く、深く、狭く……それでいて湿った、生暖かい、息の詰まるほど甘い世界、そのなかにあの団栗が落ちている。
灯されたランプのもとに暗闇の虫が疼いているのが見えない。圧倒的多数の女の足首が僕の顔の周りを歩く。くるぶしの数が異常だ。それを大きな蓮の葉で一つ一つ包み、蒸し焼きにして、ぼろ布の屋根の広場の市場で売るのだ。行き交う男の太った首が汗ばんでいる。汗はくたくたのシャツのカラーを浸し、黄ばんだ帽子を脱いで汗を拭うその姿が非常に好ましい。深夜の暗闇で木々がざわめくのは、実はその木の根元に干乾びた赤いドレスが埋まっていることを教えているのだ。僕はそれを掘り起こす。その土まみれのボロに頬擦りをすると、僕のなかに果てしない感触の喜びが拡がる。このドレスをかつて着ていたであろう一つの体をあてもなく思い描くと、曖昧さは曖昧さのまま神々しい光を帯びる。そこに全てを見出だせる人は限られている。その限られた人のなかの一人である僕は、時を忘れて二十年以上そうしているつもりだ。洗濯ばさみをそこここにはさみながら。
さて、全ては終わりに近付いていた。なぜなら全てを覆い隠していた夜が、もはや堪え切れなくなって告白めいてきたからだ。その告白は地上にいる全ての頭のうえに降りかかるだろう。道なき道を転げ落ちる一つのいびつなオレンジと、石畳の道を悠々と歩いて下る青年のあいだに、一本の鋭い稲妻が落ちる。彼は一体何を見ただろう?道端にある水桶は波紋をいつまでも波立てている。それは限りない真円だ。月は見るからに痩せ細り、いまだに太陽を待ち侘びている。だが無情にも、太陽はそんなことを少しも気に掛けてはいない。彼は無頓着さの塊であって、それを燃やして生きている。大きな瑪瑙石の柱が今にも倒れかかってくる。きらきらと輝きながら。レオナルドダヴィンチの描いた夢は、夢のまま終わる。また、ノーベルの作った世界貢献の代名詞であるあの賞が、ベトナムの空を焼き、ロシアの炭鉱を削り取る。その巨大な人造のクレーターは、カルデラの存在を見違えるほど陳腐にした。動物実験のラットは檻のなかで鼻をひくつかせながら餌を待っている。もしかしたらエロスは存在しないかもしれないなどと今は思えないが、ジキルとハイドを読みたいと突然思っても、決して読みはしないだろう。軒に干された百枚のブラジャーが風に揺れる。目を遣ると、町の窓という窓にはブラジャーが干されているではないか!こんな異常な町に住む僕は、何という興醒めな真珠貝だろう!腿にタバコの焼け焦げのあるズボンを履きながら、ポマードで髪を固めて、さて行くところは町の穴だ。暗く、深く、狭く……それでいて湿った、生暖かい、息の詰まるほど甘い世界、そのなかにあの団栗が落ちている。