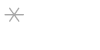鉄格子
2000年 木戸隆行著
「SPEAK CD MAG 2000」収録 CGムービー原作
「SPEAK CD MAG 2000」収録 CGムービー原作
僕たちが向かったのは鉄格子のなかに違いない。それはむやみに暑い夜のさなかだった。月は月食のため満月から新月まですべてを見せていたし、僕たちもまた何も隠すものがなかった。すべて……そう、僕たちは、自らの胸と背中とを同時に夜に顕わしたのだ。ただ、僕たちは果たして真実から言葉を生み出しているのか、それとも言葉から真実を作り上げているのか、いまだに分からないままだった。枯れた巨木に繋がれたいたいけな少女たちがぐるぐるとその周囲を廻りつづけていたし、また、一瞬にして百年が過ぎたために、都営の団地はボロボロの単なるコンクリートのかたまりと化してしまったからだ。だがそこは新たなる野鳥たちの住みかだった。カラスはもちろんのこと、シジュウカラやツグミがそのなかで社会的階層(ヒエラルキー)を形成し、棲み分けていた。その一方で、竹で作られた家々は守られた。おびただしい数の人間たちがその周囲を取り囲み、今まさに土台から持ち上げるところだ。だが、人々の顔は単なる灰色の球体でしかない。服を着て(僕たちはもちろん裸だった)近くのスーパーまで行こうとすると、ビルの隙間の日陰から痩せた猫が僕たちを振り返って見ていた。メス猫だった。それは見せ付けている生殖器で分かった。メス猫は生殖器の横から僕たちをじっと見ていた。じっと、じっと、じっと。そのすぐ後だった、僕たちが人間だと気が付いたのは。二階構成のスーパーの、繋いでいるその階段を、老人が一段ずつ慎重に下りてきた横を抜け、僕たちは二段ずつ上がって行くのだった。冷凍庫のガラス戸を開け、血眼でハーゲンダッツを買い占めた後、レジ待ちの行列のさなかでそれをことごとく解かすのだった。僕たちは何をしているのだろう?日々このような青空の下、軍人のように水面下に身をひそめ、自衛官とは軍人に他ならないのに、その類いの表明は身の安全から努めて無関心を装っているのに、しかも職業軍人であり、すると職業軍人ではない軍人とはなにか、その仮想敵国とはなにかという問題を日々抱えているような気分になる。また、夕日の差し込む疲労した部屋の隅に差された小さな一本のバラの、あの真剣に演じるもののイメージを手づかみにしたいと熱望したり、香港の街角に聳え建つあの古びたビルを夢見たりする。腰をくねらせて踊りながら、ダンサー・モアは架空の赤い帯の上を歩いてきたし、その横から、ニジマスがアーチを描いて飛び出していた。もちろんその尾びれの先から虹を伸ばして。ようするに虹色なのだ。僕たちの過去も、未来も。この目にもはっきりと見える。だが終点には鉄格子が……やはり始点にも……実は虹の左右にも……つまりすでに鉄格子のなかですべては行なわれていたのだ。あるいはこの僕たちを囲む鉄格子の外側は、実は鉄格子の内側で、僕たちはつねにその外に解放されていたのだ。だが内と外の違いなど、このような状況の下ではほとんどないに等しいはずだ。飲み干した牛乳が僕の内部に吸収されたのか、それとも僕の内部に放出されたのか、などは取るに足りないことに違いない。重要なのは、絞り上げられた人の腕の筋肉が、サラブレッドのそれのような黒光りする流線のうごめきに感じられたとき、あるいはその感覚をBMWのボンネットに感じたとき、僕は開かれた狂人の頭を理解する。それが重要だ。昼の人間と夜の人間がくしくも朝日と夕日、つまり赤い時間にのみ手を握り合うのはそういうことだ。今僕のマンションの階段を四人の女が上っていったのは、そうした不思議な現象の証明に他ならない。僕は部屋を飛び出し、彼女たちの部屋に駆け込むだろう。そしてドアを開けた向こうでぽかんと開かれている彼女たちの口に、先月買って熟すまで置いておいた大石産のプラムを一つずつはめこむだろう。すると、彼女たちの顔から疑問の表明が一つずつ外れ、滑稽な無言の能面が残る。その目は文字通り節穴だ。僕は僕の右ポケットから、宝物の、いびつで澄んだガラス玉を差し出す。
「これ、僕の宝物」
それを拾ったのは母方の祖父の家の裏庭の、竹林のなかだった。年中ジメジメしているその中に、その家の飼い犬の白い毛をしたポチが、幼い僕を引き連れて「ここを掘れ」と本当に言ったのだった。ポチはその後すぐに死んだ。そのガラス玉を掘り出したために。僕は彼女たちの前でとつぜん恐怖のために泣き崩れる。ポチの命の入ったそのガラス玉に、今度は僕の命が吸い込まれようとしている。
「これ、僕の宝物」
それを拾ったのは母方の祖父の家の裏庭の、竹林のなかだった。年中ジメジメしているその中に、その家の飼い犬の白い毛をしたポチが、幼い僕を引き連れて「ここを掘れ」と本当に言ったのだった。ポチはその後すぐに死んだ。そのガラス玉を掘り出したために。僕は彼女たちの前でとつぜん恐怖のために泣き崩れる。ポチの命の入ったそのガラス玉に、今度は僕の命が吸い込まれようとしている。