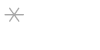とにかく書き始めるんだ
2001年 木戸隆行著
とにかく書き始めるんだ、何だか今日は書けそうだ。渋谷クラブミックスショーがノイズ混じりで流れているなかを僕は書いていた。ここで何かを作り出そうなどと考えまい。とにかく書いていることが今は大事なのだ。何を書くかではなく、書いているか書いていないか、だ。ニューヨーク・パリで好評だったプログラム、DJミックスショーケースが始まった。まずは小気味よいリズムのループ、そして遠い海豹の声と古めかしい、あるいは古くさいエレキピアノの柔らかな音が始まる。いや駄目だ、巧く書こうとするな。何が駄目って、変換するときに理性が働いてしまうのが駄目だ。いや、それだったら、一度平仮名で全部書いてしまって、その後から変換すればいいだけの話だ。ああ変換してしまった。これはクセだ。こんなクセは早いところ縛り上げて空に泳がせなければならない。ああ、アフリカのリズムにホイッスル、いや、これはサンバだ。とにかく書き続けよう。至る所から音が聞こえてくるのは空耳だろうか?なぜなら空耳は空にある耳のことではなく、耳が空だという意味なのに対して、僕はある一輪の赤い花のなかのめしべとおしべを分解しようとする。天の川だと思っていただいて結構。その意味で僕は忠実な星々の下僕なのだ。ああ、巧く書けないなどと思うんじゃない!それはいつもコップの淵からあふれ出るトマトジュースのどろどろとした感じに等しい。ある意味盲目だ。全てはパクられている僕の、いついかなるところでも不埒なアンドレブルトンのような絵を描いたゴッホという画家がいたとすれば、恐らく公園に行く暇もないくらいに部屋に篭もりきりのはずだ。この手法はまさしくシュルレアリスムの初期の方法だろう。だがそれでいい。なにも悪くない。それがそうだとはっきりしてもいないのに何かが悪いなどと考えるから答えもなく口をつぐむ鳥の嘴に目を奪われるのだ。見ろ、外灯は灯る、人の手によって。彼は非自然的な命を燃やし尽くす。僕はどうだ?自然は人工の対義語なのか?いつから?……今この瞬間から。どうやら僕は黙りすぎたらしい、もっと軽率にぺらぺらと喋るべきだったのだ。ボディビルダーの体が美しい?そんなはずはない。美は必然の運動のなかで培われた極めて無駄のない形態にこそ宿る、いやそれは間違いだ。いつの頃からか毛の柔らかなブラシを前にして、僕はそのなかにいることに気付く。お父さん、ありがとうございました。僕はこんなに立派になり、お母さん、僕はこんなに男らしい優しさを身につけました。それがあなたたちの望んだ姿でないにしても。見てください、この勇姿。フランス仕込みの日本語と、アジア仕込みの金髪で、僕はもうタジタジです。金魚、あの金魚が見えますか?愛、覚えていますか?思想もジョークも芸術ではないけれど、僕はそれをあえて避けるべきだったのです。もう敬語はやめましょう、そろそろ。いつまでもこんな口調では、美がその足の裏だけを僕に見せて、僕はそれを腰のくぼみだと勘違いしてしまう。勘違い、それこそが大切なのです。僕は今、自分のなかから勢い、いや、言葉の流れる川の涸れるのを見ました。それはとても寂しいものです。だがそれでいいのです。ああまた敬語だ。とにかく暗闇のなかにふと、女の柔らかな羽根つきの衿のセーターを見たら飛び上がらなければならない。まあいいじゃないか、だんだん自責の流れになってきた。これを乗り越えたところには、再び自己肯定が始まるのだろうか?いや、分析などするんじゃない。特に行動主義は禁物だ。以前は人間は決して知り得ないガラス玉である、という奇蹟的な少年の勉強机の引き出しだった。少年は蟋蟀の死骸を夜毎取り出しては眺めていた。その干乾びた腹には、もはや針のような足が一本残っているだけだった。別に食べたわけではない。左手の薬指がまず力を失ってくる。いい前兆か?明日の仕事にひびきそうだ、実際はそんなことを考えたことなど一度もないのに。今まで一度も。僕は過去を振り返ることをしなかった代わりに、未来を考えることもなかったように思う。いや、そんなことはない、なぜなら今をも考えていないので、僕は何も考えていないことになる。……未来予想図。その航海図の中央に羅針盤を乗せて、右目に黒い眼帯をした航海の男が、地図のうえに人差し指を滑らせている。髪は短く、透き通るエメラルドグリーンだ。その背後を二羽のカモメが飛び交っている。その口に細長い黄色いタンポポをくわえて。タンポポの花びらは赤ちゃんの被るタオル地の帽子の淵だ。淵は何度もお下がりを繰り返したために茶ばんでいる。まるで古い画布のように。画布の目はほころび、素敵な影を画面に飛び出させている。まるで煉瓦造りの家のように。その家の三階の窓には、さっきから道を見下ろしている頬杖をついた少女がいる。少女はなかば失った意識を道のうえに捜している。道にはしかし何もないのだ、往々にして。僕はその中を歩く。歩かなければならないのだ、なぜなら道があるから。道は歩くためにあるのであって、それ以外でもある。つまり僕には何も言えない、いや、言える何かなど見たことがない。あるのはつまらない言葉と引き入れられる言葉だけだ。その背後に矢を引いて身構えているオリオンがいるかいないかに過ぎない。西郷山公園の入り口からは空だけが見える。小高いのだ。それが非常な重要性を帯びて僕の脊髄の首の辺りに迫ってくる。延髄ではないので間違いのなきよう。歩くといえば、ある男が正立方体の大きな旅行カバン、それも皮張りの鞄を提げて歩いていた。その横から配達のホンダスーパーカブが飛び出してきてそのまま過ぎ去っていった。何もないのだ、ようするに。何かが起きるには、何かを起こさなければならない。例えば僕の脳だ。それさえいじれば、ほんのちょっとでもいじれば、全ては奇想天外になる。誰か僕の脳をいじってメチャクチャにしてくれるものはないか?……芥川風に。