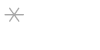MICROMANCE
1998年 木戸隆行著
2
私たち三人は、近所のスーパーマーケットに買い物に出かけた。KIDOくんにはもう少しガマンしてもらって、夕食を先に作ってから飲もうってことになったの。
今夜のメニューはペンネ・アラビアータ、セロリとニンジンのサラダ、あとはチーズとかポップコーンとかヨーグルトとか、いろいろ。
ペンネの当番はあいつとKIDOくん。私はサラダ。あいつに持たせたグレーの買い物カゴに、つぎつぎ材料を入れていく。
まんまるタマネギ、ニョキっとセロリ、ぴろぴろサニーレタス、オレンジニンジン。あいつがカゴをのぞき込む。
「……ん? あれ? うちにニンジンあるよ?」
カゴのなかでニンジンが転がる。
「そうだったー?」
「ねえー、KIDOくん? いかに俺ばっかりメシ作ってるか分かるでしょー?」
「ははは」
「バーカ」
私はニンジンをカゴからとり出して、あいつをにらんで、棚に戻した。
天井からまっ白な明かり。蛍光灯が走ってる。棚から冷たい空気。乳製品のコーナー。ミルク、バター、マーガリン、チーズ。その次はヨーグルト、プリン、ゼリー。曲げたウデにカゴをかけて棚をのぞき込んでる買い物客の列。その後ろから棚に手をのばす列。そのなかの私たち三人。
卵のコーナー。トウフのコーナー。コンニャク。ハムにソーセージにベーコン。表示よりさらに二割引き。
「私、ちょっとお出かけしてくる」
あいつがベーコンを手にして答える。
「いってらっしゃい」
私はこっそりアイスのコーナーへ。
人込みのすきまを通り抜ける。パーマのおばさん、香水の女の子、スウェットパンツのおばさん、エプロンの女の子、リュックの男の子、パーマのおばさん。体を横に向けて、すり抜ける。ぶつかる。「ごめんなさい」立ちどまる。
……見ちゃった。
スーツ姿のキレイな女の人。シゴト帰りのOL。短い栗色のストレートヘアー。肩にかけたバッグに化粧水を入れた。きっと、これがマンビキ。はじめて、見た。
でもどうして?
女の人が振り向いた。めちゃめちゃやつれた顔してる。
だからなの?
女の人は歩き出して、立ちどまった。目が、あった。感情をなにも込めてない目。じっと私の目を見つめてる。私は目を背けた。
どうすれば、いいの?
向こうからあいつとKIDOくんが歩いてくる。私はその場から逃げ出した。
「どうしたんだ?」
「どうしたんですか?」
二人は顔だけ振り向いて、自分たちの後ろにかくれた私を不思議そうに見た。二人の肩のあいだから、あの女の人が立ち去るのが見えた。キレイな足が遠ざかる。
「どうしてー?」
私たちも歩きだす。
「なにが?」
「うんー……あのね、いまそこで……」
「痛てっ」
あいつが頭を押さえてかがみ込んだ。天井から吊りさげられた「大売り出し」の赤い看板が揺れてる。バカ。頭をぶつけた。あいつはかがんだまま看板を見あげた。
「なーんだよこれー」
「ははは」
「バーカ」
あいつは後ろ頭をなでながら立ちあがった。
「KIDOくーん、これ、ひどいよなぁー?」
「ははは、そうですよね、ははは」
KIDOくんは両手でお腹を抱えて笑ってる。
「ったく、あ、ほら見てよー、血が出てるよー」
あいつはなでてた手を広げて見せた。ごつごつした手。指先にちょっとだけ、血がついてる。
「はは……」
「BAKAがむやみにおっきいから悪いんだよー」
「違ーうよ。こーれ、絶対チビな奴が吊したんだよ、しかもバカの。あー痛てえー」
「はは、男子禁制の店なのかもしれないですね、はは」
自分の手についた血を詳しく調べるあいつ。
「BAKA、キズ、見せて?」
「いーよ、こんぐらい」
「見ーせーなーさーいー!」
あいつが頭をつき出した。黒くて長い髪をかきわけたら、白い頭皮に赤黒い切り傷がちっちゃくできてた。そこから血がにじんでる。
「いたいのー?」
「痛い、ですか?」
「痛い、で、す」
つき出した頭から聞こえる声。
「バンソーコ、はる?」
「え、でも、髪剃らなくちゃいけませんよね?」
「あ、いや、痛くないよちっとも!」
あいつは私の手からサッと頭をひっこ抜いた。ずっとさげてたから顔に血がのぼってまっ赤になってる。
「お、あぶねー! またぶつけるとこだった」
「ほんとにだいじょうぶなのー?」
「はい! ほんとーに、大丈夫、です!」
見あげると、看板がまだ小さく揺れてた。私たちはまた歩きだした。
「あの看板さー、魚のコーナーの前にあるってことは、魚の大売り出しってことだよねぇ?」
「そう、ですね」
カゴにトマト缶を入れる。
「俺たちって今日、魚使わないだろ? ってことはさー、俺は、自分にはなーんの意味もない看板に、頭をぶつけたってことだよなー?」
「そういうもんですよ、セラビーセラビー」
ペンネを入れる。
「まあ買い物に来るのが俺たちだけじゃないのは分かるけどさー、せめてもう少し高く……あ、でもあんまり高いと目立たないかー」
冷凍食品の棚、そのとなりにアイス。どうでもよくなっちゃった。
「要するに、俺がもっと注意してればよかった……のかぁ? いや、そもそもこのスーパーに来たってこと自体が……いや、それよりも生まれてしまったこと……」
「SATOさん、あんまり原因を辿り過ぎるとビッグバンまで行っちゃいますよ」
パンの棚。食パンを入れたらカゴがいっぱいになった。
「んー、まあねー。確かにそこまで時間を溯っちゃったら、いいとか悪いとかわけわかんなくなるけどさー……でも、あれじゃない? 時間を溯らないであの瞬間だけを考えるにしてもさ、食欲とか金銭欲とか、さらには生きることの原因、みたいにどんどん小さくミクロになってって、結局おんなじことに……」
レジのおばさんはときどき上目遣いで二人の顔をうかがってた。
「……でさ。だからほんと、いろんなことをごまかしながら……」
カゴのものを袋につめかえながらも、ずっと話し続けてる二人の後ろ姿。なんだかさみしい。袋につめかえ終わってカゴを重ねて、スーパーを出る。そう言えば、あのキレイな女の人はどうなったのかなあ。
一方通行の細い路地。ゴチャゴチャにぎやかな商店街。通りの両側には、うじゃうじゃ自転車がとめられてる。
コンビニ、ディスカウントショップ、立ち食いソバ屋、居酒屋、カラオケ。お店からもれた明かりが照らす人込み。向こうの山手通りまで続く、二列の赤白ちょうちん。途中のアーチに書かれた商店街の名前。
「……それであいつ『お前がそんなに懐の狭い奴だとは思わなかったよ!』なーんて、無意味な言葉を連発して感情とかプライドに訴えかけようとするんだけどさ、そいつがまた……」
買い物袋を携えて、まえを歩く二人の背中。
なんなのこれ? もしかして私、仲間ハズレ? ……なんてひどい人タチだー。
あいつの笑い声。KIDOくんの笑い声。人込みから笑い声。さみしいなあー。
見あげると、電線が網の目みたいに張りめぐらされてる。雑居ビルにはさまれた細い空が青く、暗く、高く、落ち着いてる。
そう言えば……お母さんも、こんな気持ちで帰って行ったのかなあ。
ガタンゴトン、東横線の電車の音。シャッターがおろされたお店。おそるおそる進むシトロエン。そのまえを横切るおじいちゃん。山手通りをうずめるタクシーの列。「……なんだよー」と笑ってあいつが振り返る。
「ところでGUU、どっちが先に作る?」
私は口をぐっと閉じて答えなかった。私を一人にしたバツとして、しばらく二人をムシすることに決めたの。
「なあ、GUU」
電柱にはいろんな貼り紙がされてる。ライブ、イベント、自民党、粗大ゴミ回収、それに……
「あ……」
「なに?」
「なんですか?」
早くも口をきいちゃった自分の意志の弱さにため息がでた。でも、こんなの見せられたらしかたないよ。
「……見て、これ」
迷い猫の貼り紙。「探しています!」の文字。行儀よく座ってこっちを見てる子猫の白黒写真。
(特徴)現在二歳のオス猫。全身黒毛。目は緑色。尻尾は長くてまっ直ぐ。見かけた方は……
「ALに、似てない?」
「まさか。だってALはEIJIからもらったんだぞ?」
「EIJIだってALのことひろったのかもしれないでしょ?」
あいつは口ごもった。
「そうかもしれないけど……じゃあこの猫がもしALだったら、返すのか?」
「それは……だって、ALは私たちの家族なんだよ? ALだって、きっと、私たちと一緒にいたいと思ってるはず!」
あいつがうつむいた。
ALが家にきたのは一年前。EIJIの家から子猫を連れて、帰りの道で私たちは名前を考えた。
「ALってのはどう?」
「なんなの、ALって?」
カゴのなかで眠る子猫。
「AL・GREENだよ。こいつは黒猫で、目が緑だろ? それで、AL・GREENは黒人で、ファミリーネームがグリーン。な? ぴったりじゃん」
家に着いて目を覚ますなり、見慣れない場所におどろいて子猫のALは毛を逆立てた。走り回って隠れたALを二人であちこち探し回った。
「いた! ここにいたよ、YASUKO!」
やっと見つけたALの緑色の目には、手を差しのべてる私たちが小さく映ってた。
それからしばらくはおびえてたALも、だんだん私たちにも私たちの家にも慣れてきて、いまでは毎日イタズラばっかりしてる。
花は食べるわ、キッチンは荒らすわ、ティッシュは引っかき回すわ、もう大変。いまのパキラも四代目。
あんまりひどいイタズラをしたときは、トイレに閉じ込めたり段ボールに閉じ込めたりしてしかるの。「AL、そこで少しは反省しなさい!」って。そうすると、なかから「にゃー」って声がする。「ごめんなさいー、ボクが悪かったよー」って。
しばらくそのままにしてからのぞきこんで「もうあんなことしちゃダメだよー?」って言うと、ALは目を閉じてほんとに反省してる声を出すの。でも、出してあげるとすぐにおんなじイタズラをしてまた怒られる。ちっともこりない。
でも、ほんとはALはめちゃめちゃやさしいやつなの。
いつだったか、あいつがケンカして出て行った夜、部屋で一人泣く私の横にそっと座って「どうしたんだよー」って涙をなめてくれた。
「……私、ALがいない生活なんて考えられない」
「俺だって」
でも、まえの飼い主も私たちみたいな気持ちでALのことを思ってたら……おんなじ気持ちで一年間ずっと探してたんだとしたら……なんて辛いんだろう。
山手通りに出た。遠くでクラクションがなった。
「ねえ、EIJIに、ほんとのこと、聞いてみよ?」
「……」
あいつは答えなかった。
わかってる。ALはALだけのもの。私たちのものでもまえの飼い主のものでもない。でも、でも……
ALとずっとずっと一緒にいたいの。一緒に寝たり、一緒にご飯を食べたり、じゃれたり、ケンカしたり、そういうことをずっとしてたいの。BAKAやお父さんやお母さんやおばあちゃんや、KIDOくんやAKIさんやMANABUさんやMIKAちゃんやMONKEYや、私が大好きな人たちとおんなじように。
気がつくと私たちは速歩きしてた。早くALに会いたくて会いたくてしかたなくなってた。
あいつが先頭をきって次にKIDOくん、そして少し離れて私。中目黒駅前の人込みをすり抜けて、思いきって私は走りだした。二人を抜いて、いちばん先頭に。ガードの向こうから空が開けた。広い、夕闇。
二人は私に抜かれると、自分たちも負けずに走りだした。後ろから足音が迫ってきて、BAKAとKIDOくんの後ろ姿が私を追い抜いてった。茶色と水色のソールが夕闇に瞬く。
「ずるーい!」
私の声が響いた。KIDOくんは首をちょっとだけ私に向けると、足をゆるめてBAKAと私の中間くらいを走った。山手通りをうずめるヘッドライトの渋滞。空にはまっ青な闇が、じっと月の出を待ってた。
汚れて黒ずんだ白カベにまっ黒なドア。二階建ての古アパート。その二階が私たちの家。息をきらしながら私が階段をのぼっていくと、あいつとKIDOくんはドアのまえでタバコをふかしながら私を待ってた。
「早く、鍵」と、あいつが言った。
そうだ、私がカギを持ってたんだー!
二人を背にしてカギを差し込む。ドアの向こうからALの声がする。私は先を越されないように注意深くカギを回して、ドアを素早く開けてなかにもぐり込んだ。すぐにドアを閉めてカギをかけた。
「おーい!」
「ははは」
あいつはさけびながらノブをガチャガチャさせてる。振り返ると、ALが座って私を見あげてた。
「ALー!」
「にゃー」
ALをぎゅっと抱きしめてキスした。
「GUU! 汚ねーよ!」
ドアをドンドンたたいてうるさいから、しかたなく開けてあげた。
「あぁー、ALくぅーん! 会いたかったよぉーう! だっこさせてよぉーう!」
あいつは泣く振りをしながら両手をさしのべた。かわいそうだから抱かせてあげた。
あいつはALを高くあげたり抱きしめたりして、キスした。KIDOくんはその後ろで順番を待ってる。突然訪れたキスの嵐にALはキョロキョロびっくりしてる。
「BAKA、ほんとに、EIJIに、聞いてね……」
「……分かってる」
KIDOくんは控えめにキスすると、ALを私に手わたした。体をダラーンとたらしてされるがままのAL。
「じゃあ俺、先にペンネのほう作りますね」
「うん」
私はALを抱いてまっ赤なソファーに座り、ヒザにのせてタバコに火をつけた。あいつの電話してる声が小さく聞こえる。キッチンからトントンまな板の音がする。
青いローテーブルにはオレンジ色の灰皿だけがポツンとのってる。クリップライトで照らされたパキラの影が私の足もとまでのびてる。
となりの部屋にはベッドが見える。ベッドにはリンゴの柄が入った白いカバーがかけられてる。その脇にはあいつのギターが三本立ってる。ALが私を見あげてないた。
だめ……やっぱりALはわたせない。どんなこと言われてもいい。私が守ってみせる。だれよりも愛してみせる。だから……お願い。
白い冷蔵庫が「ぶおおおーん」ってさけんだ。なんだかいつもより高くて長い声。ため息と一緒にはいた煙は、かすれてのびた。その先にあらわれた、あいつの顔。
あいつは伏目がちに立って、両手を力なくたらしてる。
「GUU……」
悲しげにつぶやいたあいつの声。私はALを抱く手に力を込める。
「やっぱりALは……」
KIDOくんも手を休めてこっちを見てる。ぐつぐつナベの音。漂うトマトの匂い。
「……EIJIの飼ってる猫の子供だってさぁ! ALくぅーん、おいでぇぇ! これからもよろしくねぇぇ!」
あいつは私のヒザからALを抱きあげると、何度も何度もキスをした。
「……ばか……バカー!」
私はALごとあいつに抱きついた。涙が出た。あいつも笑いながら泣いてた。KIDOくんは笑いながら鼻をすすり、また作りだした。
「……みんな、みんな大好きー!」
抱きあったままぐるぐる回る私たちにはさまれたALの後ろ頭。ピンと立てた耳。あいつの肩をつかむ両ウデ。
「今日はお祝い、ですね?」
「うん、ALを囲んでパーティー!」
「戸籍などという拘束を全く必要としない、愛を分かつ家族、という死ぬまで外れることのない首輪をつけた記念日として……」
「ははは、やたら聞こえが悪いですね」
あいつがまたALにキスした。
「ALと俺には違う血が流れていようとも、同じ家族という意識が流れている。意識は確実に血を越える! いや、血とは意識のことだ! 刷り込みは両方向に働き……」
「いつまでもALと愛しあいます記念ー」
「そう端的に言うなよ。俺だってなぁ……」
「あ、YASUKOさん、できましたー」
KIDOくんがナベをかき混ぜながら火をとめた。
「あー、ひどーい。BAKA、なんにもやらなかったー」
「あ……KIDOさん、ごめんな、さ、い」
「ははは、いいんですよー」
水の流れる音。KIDOくんが手を洗ってる。
「ダメだよー」
「あ……じゃ、じゃあ俺……そ、そうだ! セッティングから後片付けまで、全てやらせていただきます! それも完璧なる手際で!」
KIDOくんは笑顔で手を拭いてる。
「ほんとに、いいですよー」
「ダーメー。じゃあBAKA、それでいいからしっかりやりなさい」
「はっ。仰せのままに!」
私はサラダにとりかかった。
セロリの筋をとり、ニンジンの皮をむく。それを千切りにして、お皿に敷いたサニーレタスにのせる。ガリガリ、トントン。
今度はドレッシング。ボウルに塩、コショウ、赤ワインビネガーを入れてよく混ぜる。そこに、オリーブオイルを少しずつ加えながらとろっとするまでさらにかき混ぜる。シャカシャカシャカ。
できあがったドレッシングをさっきの野菜にかけて出来あがり。
「BAKA、できたよー」
「はいっ、後はお任せを!」
あいつはわざとらしく忙しそうに働いた。
冷蔵庫から飲みかけの白ワインをとり出して、料理をローテーブルに運ぶ。ときどきヒタイの汗を拭くマネをしながらせっせと運ぶ。
KIDOくんは落ち着かない様子で座ってる。私はタバコの煙をあいつの顔に吹きかける。
「遅ーい!」
「は、はいっ。申し訳ございません!」
ALが私のヒザのうえで体を震わせるほど大きなあくびをした。
「王様も待ちくたびれてるよー!」
「……只今、完了致しました!」
あいつはソファーに倒れ込んだ。その向こうでKIDOくんが「お疲れさまでした」とささやいた。
「疲れたー!」
「KIDOくんのほうが疲れてるんだよー?」
「ははは、そんなことないですよー」
「ま、とにかくALの出所が分かってほっとしたことを祝して……」
私たちはグラスをかかげた。
「ははは、急にチープになりましたね」
「そうだよー」
「まぁまぁまぁ、いいじゃあないの。とにかく、チァーズ、乾杯!」
私たちはグラスをカチンとあわせた。ALは自分のお皿にのせられた山盛りの夕食にかぶりついた。ほんとはダイエットちゅうだけど、記念日だからめちゃめちゃ多い。
「でーも、不思議だよなー。ALがいるだけでさ、全然家の雰囲気違うんだよ。見てるとなーんか、なごむって言うかさ。ALが来る前はGUUとケンカばっかしてたけど、今はほとんどしないしなー」
あいつはすぐに飲み干して、グラスにワインをつぎ足した。
「それに最近、やたら生活が規則正しいんだよー。朝は朝メシやんなきゃないから早起きするし、外に出かけるときも晩メシやんなきゃとか、遊んであげないとストレスたまるかなぁとか思うから、ちゃんと帰るようになるんだよねー」
サラダもワインもペンネも、めちゃめちゃおいしい。KIDOくんもワインを飲み干した。
「子供ができた、みたいなもんですか?」
「うーん……子供でもあり、友達でもある……両方、かなぁ。KIDOくんも飼ったらー?」
「ははは」
ALはご飯を食べきれずに残して、ゴロンと横になって、ペロペロ毛づくろいしはじめた。
「おっきくなったよねー」
「そうだなー」
「そうですねー」
ALは三人に見られてるのに気がついて「みゃー」とないた。
「AL、みーんなに見られて恥ずかしいんでしょー?」
「どれどれ」と、あいつはALを抱きあげてヒザにのせた。
「やっぱり、ちょーっとデブかなぁー」
「明日からまたダイエットだねー」
「ダイエットしてるんですか?」
あいつは片方の手でヒザのうえのALの背中をなでて、もう片方の手でワインを飲んだ。
「俺もGUUも、デブ猫嫌いだからねぇ。体にもよくないらしいし。ALってさ、家猫だろ? だから余計、運動不足になりやすいらしいんだよね」
「……なーんか、私のこと言われてるみたい」
確かに、このあいだお腹にさわったとき、ちょっとやばいかなーって思った。たぶんシゴトをやめてから一日じゅう家でALとごろごろしてることが多くなったからだと思う。ほんとに家猫みたいなの。
このあいだなんか、あんまりヒマだったから雑貨屋さんでも見に行こうと思って準備したの。でも、玄関のドアを開けてびっくり。
太陽が高い時間に外に出るのがあまりに久しぶりすぎて、太陽ってこーんなにまぶしいものなのかあーって。後ずさりしてやめちゃった。
そう言えば、ちっちゃいころ、テレビで見たアメリカの太陽があまりにも大きくて、自分が見てるのとおんなじ太陽だなんて信じられなかった。だからずっと日本とアメリカでは違う太陽がのぼるんだと思ってた。
「ねえ、月よりも太陽のほうがおっきいって、実感できる?」
「はあ?」
「私、頭ではわかってるんだけど、いまだに信じられないの。それと地球がまるいってことも」
KIDOくんはサラダをさしたフォークをとめた。
「……確かに、近過ぎたり、遠過ぎたり、小さ過ぎたり、大き過ぎたりするものは、実感として把握できないかもしれないですね」
あいつがタバコに火をつけた。
「触れることのできない真理。科学的真理。でもすごいよねえ、最初に太陽と月の大きさと距離を三角関数で測ろうなんて考えついたやつ」
「でも、怖いですよね。何か最近、知りたくなかったことまで知らされてしまうって言うか」
「そうだよなー」
KIDOくんは思い出したようにフォークを口に運んだ。あいつの口から煙がのびた。
「あのさ……もし、もしだよ、脳とか遺伝子とか人間の構造が科学的にどんどん解明されてってさ、例えば『人間は食と生殖のために生きるのである』とかって結論が出たとしてさ、それを基にして人間を教育したり法律を制定したり、そんなことになったらどう思う?」
「人間が生きる目的の発見、みたいなものですよね……抗いたいような、従いたいような……わけ分かんないです」
あいつが灰皿に灰を落とす。
「GUUはどうなの?」
「うーん……言ってること、よくわからないけど……」
「けど、なに?」
私はフォークをかみながら思い出す。
「いまの話にぜんぜん関係ないかもしれないけど……私が新潟のおばあちゃんに『幸せになるにはどうしたらいいのー?』って聞いたら『やっちゃんは幸せになりたいの? それだったらいっぱい笑いなさい』って言われたことを思い出したの」
「いっぱい笑え、ねえ……そう言えばさ、幸福の対義語ってなにかなあ? 不幸は対義語って言うよりも幸福以外のものを指す言葉だろ? そうじゃなくて対極を表す言葉……いや、それよりも、幸福には三つの段階があって、無、定義、獲得、その意味枠が……」
またはじまった。KIDOくんはペンネをほおばったままワインを飲んだ。
「おばあさんって、どんな人なんですか?」
「おばあちゃん? おばあちゃんはねー、もー、めっちゃめちゃかわいい人なの。サイって名前で、いま……八十六、かなあ。ちっちゃくって、いーっつも笑ってて、遊びに行くと『やぁーっちゃん、ほーれ、こんげおっきょなってぇー。まーずながまらしぇー』って言うの」
あいつが首をかしげた。
「それ、どういう意味?」
「うーんと……『やっちゃん、大きくなったね。とりあえずくつろぎなさい』って意味」
「ながまらしぇー、が、くつろぎなさい、なんですか?」
「うん。ながまる、って横に長くなる、寝転ぶって意味なの。そう言えば、去年はおばあちゃんちに行かなかったなあー」
ALが顔をくしゃくしゃにしてあくびをした。
「よく行くんですか?」
「うん。私、小学校三年生までおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に住んでたの。おじいちゃんはもう死んじゃったけど。……それでね、おばあちゃんちのまわりには田んぼがずぅーっと広がってて、ちっちゃいころはよくおじいちゃんとドジョウとかザリガニとかとって遊んでたの。だからかなあ。私ね、山とか海にいるよりも田んぼのあぜ道にいるほうが落ち着くの」
「YASUKOさんって新潟出身なんですかー。へえー」
あいつがタバコをもみ消した。
「GUU、あの話もしてあげれば?」
「あの話? あー、あれね」
私はタバコに火をつけた。KIDOくんは目をパチクリさせた。
「あのね、おばあちゃんちは農家なんだけど、農業だけじゃなくて養鶏もやってるの。それでね、卵を産まなくなったニワトリを肉にするじゃない、そういうニワトリのお腹には卵の黄身みたいなのがふさになって入ってて、それをとり出して水炊きにして食べると、もうめっちゃめちゃおいしいの。いま考えると気持ち悪いけど、私、黄身が大好きだったから、おじいちゃんと一緒によくニワトリを殺してた」
「ねー、KIDOくん。GUUには気をつけたほうがいいよ」
「ははは」
タバコの灰を落とすと、オレンジ色の光があらわれて、ゆっくりもぐった。
「でも、そのときはかわいそうだとか残酷だなんて思わなかったなあー。ただあのふさになった黄身が食べたくて、いっしょうけんめい殺して、羽をむしって……でも、肉は嫌いなの。鳥だけじゃなくてぜんぶ」
ALが後ろ足であごのところをかいてる。
「好き嫌いとか、激しいほうなんですか?」
「いまはそうでもないけど、ちっちゃいころはすーごかった。放課後まで給食が机にのってる子だったから。でもね、私、保健室の先生が大好きで、よくお昼休みとかに遊びに行ってたんだけど、その先生に『食が片寄ると性格も片寄るよ』って言われたのがめちゃめちゃショックで、それから、いじでも給食を残さないことにしたの」
いつのまにか冷蔵庫が静かになってる。
「俺、スイカがだめです。何て言うか、あの赤いところに黒い種がツブツブーってなってるのを見ただけで寒気がして」
「俺は……別にないなー」
ALがあいつのヒザでまるくなって眠ってる。手をのばしてALの足をひっぱってみた。かわいいなー。熟睡してる。私は煙をはき出した。部屋がもくもく煙ってる。霧のロンドン。
部屋を満たした青白い煙をローソクの炎がのび縮みしながら揺らしてる。空になったワインボトルをすてに行ったKIDOくんは、帰りにハイネケンと梅酒を手にしてた。
ごちゃごちゃしたローテーブル。サラダもペンネもほとんどなくなってる。もう十一時。早いなあー。起きてからもう九時間。
「SATOさん、最近音楽のほうはどうですか?」
あいつは窓を少し開けて換気した。
「よくないねー。ドラムのやつがぜんぜんやる気なくてさー。あいつ、クビだよ、ほんっとに」
「一人でやることじゃないぶん、大変ですよね」
「まぁそのぶん、うまくいったときの気持ち良さは大きと思うけどね。でもあいつはクビ」
あいつはハイネケンを口にした。
「その人、かわいそう」
「かわいそうなんかじゃないよ。俺たちが一生懸命練習して、曲作って、さあライブ前最後のスタジオだって日に、あいつなんて言ったと思う? ゲンチャで酔っぱらい運転してコケて骨折した、って言ったんだぞ? 考えられるか? なんでこんな大事なときにそんなことしてんだ?」
「その人だって、骨折したくてしたんじゃないよ?」
「そんなこと言ってんじゃないよ。なんで事故る可能性のあることを、こんなときにやってんのかって言ってんだよ。分かるだろ? 今回だけじゃない。あいつ、ライブ前になると必ずと言っていいくらい、どっかケガすんだよ。それでいかにも不幸だったみたいに弁解してさ。不幸なんかじゃない、お前のコンディション作りが悪いんだっつうんだよ」
あいつはタバコに火をつけた。
「でも、やっぱりかわいそうだよー。だってその人、友達なんでしょー?」
あいつは勢いよく煙をはき出した。
「友達だけどさ、それとこれとは別問題だよ。俺たちは友達と仲良くするために音楽やってんじゃない。やりたい音楽があって、そこに集まった結果として友達になるんだよ。だからそれができないんだったらやめてもらう。友達としては続けられるかもしれないけど、一緒に音楽やってくことはできない」
「その人、それで納得するのー?」
あいつはせわしなく灰を落とした。
「しなくてもやめてもらう、たとえ友達じゃなくなったとしても。冷たいようだけど、俺にはあいつと付き合ってくことよりも、音楽のほうが大切なんだよ」
私と音楽だったら、って聞こうとしてやめた。バカみたい。
私はあいつに音楽をすててほしいなんて思ったことないし、それどころかあいつがキーボードに向かっていっしょうけんめいやりはじめると、遠くからALと一緒に「がんばれー」って応援してる。
あいつには世界中のステージに立つような人に絶対なってもらいたいし、それにくっついて世界中を旅行するのが私の夢。
「あのー……俺、ちょっとタバコ買ってきます」
KIDOくんは目を伏せたまま立ちあがると、ライターをポケットに入れて出て行った。あいつは自分のタバコの箱を開けて「俺のも頼めばよかったなー」って言った。
「ところでGUU、なにか考えてんの? そのー、なんだっけ? MICROMANCEの内容をさ」
私は梅酒を飲んだ。あー。顔がカアーって熱いー。
「言わなかったー? ALがかぁわいいー、とかー……」
「ロマンスとか、だろ? それは分かってんだけどさ、テーマだよ、テーマ」
「テーマ? MICROMANCEだよー?」
「いや、それはタイトルでしょ」
ALがあいつのヒザのうえで寝返りをうった。
「うーん、それじゃーあー……ささいでー、ロマンチックなー、ことー?」
「いや、それは……表現方法、でしょ? そうじゃなくてさ、その方法を使ってなにを表現するのか、だよー」
あいつの手に握られたハイネケンの缶。
「表現って……例えばー?」
「例えば……そうだなあ……喜びとか、悲しみとか、怒りとか、絶望とか、いろいろあるじゃん。感情じゃなくても、例えば愛についてとか、美についてとか、社会構造の仕組みについてとか、なにか自分の内で考えたり感じたりしたものを形にして外に表すことだよ」
「じゃあー、やっぱりー、ALがめちゃめちゃかわいい、とかじゃなーい?」
私はグラスをローテーブルにおいた。
「うーん、いやー、まぁそうなんだけど……でもさー、それだったら小説なんてめんどくさいことしないでさー、ALはこんなにかわいいんだよって話して歩けばすむことじゃないかー? まあ話せる人数には限りがあるだろうけどさー」
「でも、それじゃあシゴトにならないじゃなーい」
「仕事って言うけどさ……なんだよ、もしかして、仕事がないから小説書こうって思ったのか?」
「そうだよー。だってー、寝転んでー、好きなこと書くだけでいい、って言うからー」
おいたグラスの周りに水たまりができてる。
「……それじゃあ、ダメ、なのー?」
「いやぁ、だめって事はないだろうけどさぁ……」
足もとにのびてるパキラの影。五枚の葉。
「じゃあー、BAKAはー、どーして音楽やろうって、思ったのー?」
「俺? 俺が音楽やりたいって思ったのはさ、レコード聞いてて『ああ、ここはもっとこうしたほうがいいのになー』とか『どうしてこういう曲がないのかなー』って思ったからなんだよ。それでそのうち頭の中で曲が浮かぶようになって『ああ、これいい曲だな』って思うと、それを形にして何度も聞いてみたくてしょうがなくなってさ。だから俺の場合、表現することに必要性がある、わけだよ。うんうん」
のばしたまえ足を交差させて眠ってるAL。
「お金はほしく、ないのー?」
「そりゃあ金は欲しいけどさ、目的ではないんだよ。目的は、自分にとってこれ以上ないって曲を書くことだから。売れる売れない、じゃなくて」
スリッパからのぞく、私のパープルの足のツメ。動かしてみる。
「でも、売れたら、嬉しいんでしょ?」
あいつはALのしっぽをつかんで、はなした。
「そりゃあ、売れたら素直に嬉しいよ。売れるってのはさ、例えば音楽なら、その曲を何度も聞いてみたい、じっくり一人で聞きたい、自分の手元に置いておきたいって思うから買うわけだろ? それってさ、自分が認められてるってことだからやっぱり嬉しいんだよ。でもさー、使い古された言葉だけど、自分が好きで書いた曲が売れるのは嬉しいけど、好きでもない曲を書いて売れても嬉しくないんだよなー。例えばさ、自分の顔で女にモテんのは嬉しいけど、こういう顔がモテんだろうなって整形してモテても嬉しくない、みたいにさ」
「でも、売れなかったらバイトしなくちゃいけないんでしょー? だったら、そーゆー曲でも少しは練習になるんだからー、作ったほうがいいんじゃなーい?」
「確かにさ、そういうふうに使い分けてもいいとは思うよ。でも俺にはそれが割り切れないっていうかさ、なんか、自分の好きなことを冒涜してるような気がして嫌なんだよなー」
食べかけのチーズ。あいつの歯形。
「ふうーん、難しいんだねー。私なんか、なあーんにも考えてないのに」
「うーん……でもさ、意気込みで作品が評価されるわけじゃないし、されちゃいけないんだよ。意気込みだけじゃない。作者が誰だとか、その作品の作られた背景がどうだとか、そんなのは作品の評価にはぜんぜん関係しないことなんだよ」
ドレッシングまみれのサニーレタス。トマトのソースにもぐったフォークの頭。私は足をバタつかせる。
「……なーんか、めんどくさくなっちゃった」
「あ……いや、そう言われると困るん、で、す、け、ど」
ALがゆっくり目を開けて、まばたきして、立ちあがって、のびをした。
「まぁ、ほら、GUUはALのかわいさとか表現したいんだろうから、その……やっぱりそこにも必要性があって……だから、そのー、やるだけやってみたら? もしかしたらすごいのが出来るかもしれないし。ビギナーズラックってのが……」
ALがあいつのヒザからおりて、こんどはKIDOくんのいた場所でまるくなった。ゆっくり、目を閉じた。
「KIDOくん、遅いねー」
「もしもし? 聞いてる?」
私はタバコに火をつけた。ローテーブルに並ぶ三つのグラスと二本の缶。梅酒の入ったグラスに浮かぶ、とけて小さくなった氷。ビールの入ったKIDOくんのグラスの底からは、細かい泡の隊列が消えてしまいそうにのぼってる。
「そう言えばKIDOくん、辛いことあったって言ってた」
あいつが黙り込んだ。時計が一時を回ってる。私のタバコの先から流れる青白い煙があますことなく滞る。ローソクがALの寝顔を揺らしてる。あいつはハイネケンの缶を一気に口に傾けて立ちあがった。
「ちょっと、見てくるわ」
ローテーブルを回って歩く、きゃしゃな巨人。煙に頭をつっ込んだ。ALは眠そうに目を開いて、また閉じた。
巨人の長い影が私の体を通り過ぎる。スリッパの足音がとまり、ドアの開く音がする。タバコの灰を落とそうとして、吸い殻があふれそうになってるのに気がついた。
片手でタバコを吸いながら灰皿をキッチンに持って行くと、玄関のドアの向こうからあいつの声がかすかに聞こえてきた。
「……なにやってんだよ!……いいから、とにかくやめろ!……」
灰皿をとりあえずコンロのうえにおいてドアからのぞいてみた。すぐ近くであいつが、うつむくKIDOくんの正面に立って、なにか話してる。
パープルのツッカケに足をつっ込んで、ツカツカ歩いて近づくと、あいつは私に気がついた。タバコを吸ってはき出すと、澄んだ夜空が汚れたみたいだった。
「どうしたのー?」
「……ちょっと、な。KIDOくん、とにかく家に入ろう」
あいつはうつむくKIDOくんの肩を抱いて歩きだした。私はもう一度煙をはいてみた。こんどは風にのって高く混ざって行った。
玄関のドアを開いたら、ドーッって水の音がする。あいつがキッチンでなにかを水に流してる。近づいて横からのぞくと、透明な包みから白いさらさらの粉を流してた。
「なに、してるの?」
「KIDOくん、これやろうとしてたんだよ」
「なあに、これ……もしかしてー!」
あいつはうずを巻いて穴に流れてく白い粉を見つめたまま、ゆっくりとうなずいた。
「ちょっとKIDOくん! どうしてこんなことするの!」
KIDOくんはうつむいたまま「は、はは」と力なく笑った。
「笑えるようなことじゃないでしょ! ちょっとここに正座しなさい!」
「GUU、なにもそこまでしなくても……」
「BAKA、これは大変なことなんだよ! 一人の友達がダメになるか、ならないかのせとぎわなんだよ!」
私があいつを黙らせると、KIDOくんは私の正面にゆっくり正座してうつむいた。
「いーい! KIDOくん、君、ロクデナシだよ! どうしてこんなことするのか、ワケを話しなさい!」
なぜか吹き出したあいつをにらんで黙らせた。KIDOくんはためらいながらゆっくり静かに話しだした。
「俺……大月先生のアシスタント、クビになったんです」
「写真の?」
KIDOくんは小さくうなずいた。
「……先生は、アシスタントのプロが欲しかったんです。アシスタントって、いかに先生が気持ちよく撮れるか、そのことをいつも考えていなければいけないんです。安い手当で、毎日毎日、ほとんどの時間をそれにつぎ込んで。だけど……だけど俺は、アシスタントのプロになりたいわけじゃない、写真のプロになりたくてアシスタントになったんです! 大月先生につけばその道が開ける可能性が高いから、だから先生のアシスタントになりたくて……それでやっとの思いでなれて……確かに少しは技術を盗むこともできました……だけど、分からなくなったんです。自分はプロの写真家になりたいのか、それとも……とにかく何も、かも」
キュッと蛇口をひねる音がした。
「……でも、だからって、こんなことしていいことにはならないんだよ?」
私の言葉をさえぎって、あいつが話しだした。
「GUU、KIDOくんはさ」
「BAKAは黙ってて!」
「黙んねぇよ! あ、ごめん……でもさ、俺、分かる気がするんだよ、KIDOくんが悩んでることって。俺も悩んだことあるよ。自分は表現をしたいのか、認められたいのか。初めはいいものを作れば売れるって思うんだけど、やってるうちにさ、売れるものといいものが必ずしも一致しないって気付くんだよ。それって好みとか売り出し方とかだけの問題じゃなくて、受け取る側の無知とか鈍感とか、そういうのもあってさ。だから、結構売れたものと爆発的に売れたものとの間の差ってそんなに問題じゃなくて、どういう人たちに売れたのか、そっちのほうが重要で。でもね、KIDOくん。売れたものが必ずしもいいものとは限らないけど、いいものは必ず売れるんだよ。いいものっていうのはね、それを手にした者に世に広げる使命を負わせるものなんだよ」
KIDOくんは正座してうつむいてる。モモのうえで握った手を見つめてる。
「分からないんです……いいものって、何なのか……誰にとって、いいものなのか……誰に向かって表現するべきなのか……」
「それは、自分だよ。自分にとっていいものだよ。人にとっていいものなんて、分かるわけないだろ? 表現だって、本当は自分に向かうものなんじゃないのか? 例えばさ、音楽とか写真とかは同じものがコピーできるからいいけど、もしそれが陶磁器だったりしたらさ、最高の出来のものは手放したくないわけだろ?」
「……だけど、自分に向かうものだったら何も、形にしないで自分の中にしまっておけば済むことじゃないですか」
「いや、形にすることで、自分は自分とはっきり向き合えるんだよ。瞬間的には自分は一つしかない。つまり、過去の自分に今の自分が運動をもって同時に向かい合うためには、やっぱり形にすることが必要なんだよ。だから、どれだけありのままの自分を形にできているか、そこに表現の優劣が生じると思うんだよ。そのためには当然、技術も必要だし、自分自身の考察……」
「ねえ! どうしてこんな話になってるの?」
あいつがキッチンに寄りかかってる。
「あ、いや、だから、KIDOくんの前にはそういう状況があってさ……」
「それでも、こんなことしていいことにはならないよ」
「ちょっと待てよー、それじゃあ追い詰められたネズミが猫を噛んじゃいけないって話になるじゃないかー」
「なあに、それじゃあBAKAはKIDOくんがダメになってもいいって言うのー?」
「いや、そういう意味じゃなくてさ……」
KIDOくんが顔をあげた。
「SATOさん、俺が悪かったんです……どうもすみませんでした」
「じゃあ、もうしないって約束しなさい!」
「絶対に、もう、やりません」
「約束だよ!」
「はい」
正座したKIDOくんを立ちあがらせて、今度は「もうドラッグをしません記念パーティー」をした。時計は二時を回ってた。
白い冷蔵庫は静かに眠り、ちっちゃいパキラは薄い影をのばしてる。青いローテーブルではローソクが揺れ、耳を澄ませばまっ赤なソファーでまるくなってるALの寝息が聞こえそうな気がした。
ソファーの背中の窓からは、まっ黒な夜空が差し込んでた。私はタバコをふかしながら、今日という一日が自分にとって、とても意味のある日だったに違いないって思った。
私たち三人は、近所のスーパーマーケットに買い物に出かけた。KIDOくんにはもう少しガマンしてもらって、夕食を先に作ってから飲もうってことになったの。
今夜のメニューはペンネ・アラビアータ、セロリとニンジンのサラダ、あとはチーズとかポップコーンとかヨーグルトとか、いろいろ。
ペンネの当番はあいつとKIDOくん。私はサラダ。あいつに持たせたグレーの買い物カゴに、つぎつぎ材料を入れていく。
まんまるタマネギ、ニョキっとセロリ、ぴろぴろサニーレタス、オレンジニンジン。あいつがカゴをのぞき込む。
「……ん? あれ? うちにニンジンあるよ?」
カゴのなかでニンジンが転がる。
「そうだったー?」
「ねえー、KIDOくん? いかに俺ばっかりメシ作ってるか分かるでしょー?」
「ははは」
「バーカ」
私はニンジンをカゴからとり出して、あいつをにらんで、棚に戻した。
天井からまっ白な明かり。蛍光灯が走ってる。棚から冷たい空気。乳製品のコーナー。ミルク、バター、マーガリン、チーズ。その次はヨーグルト、プリン、ゼリー。曲げたウデにカゴをかけて棚をのぞき込んでる買い物客の列。その後ろから棚に手をのばす列。そのなかの私たち三人。
卵のコーナー。トウフのコーナー。コンニャク。ハムにソーセージにベーコン。表示よりさらに二割引き。
「私、ちょっとお出かけしてくる」
あいつがベーコンを手にして答える。
「いってらっしゃい」
私はこっそりアイスのコーナーへ。
人込みのすきまを通り抜ける。パーマのおばさん、香水の女の子、スウェットパンツのおばさん、エプロンの女の子、リュックの男の子、パーマのおばさん。体を横に向けて、すり抜ける。ぶつかる。「ごめんなさい」立ちどまる。
……見ちゃった。
スーツ姿のキレイな女の人。シゴト帰りのOL。短い栗色のストレートヘアー。肩にかけたバッグに化粧水を入れた。きっと、これがマンビキ。はじめて、見た。
でもどうして?
女の人が振り向いた。めちゃめちゃやつれた顔してる。
だからなの?
女の人は歩き出して、立ちどまった。目が、あった。感情をなにも込めてない目。じっと私の目を見つめてる。私は目を背けた。
どうすれば、いいの?
向こうからあいつとKIDOくんが歩いてくる。私はその場から逃げ出した。
「どうしたんだ?」
「どうしたんですか?」
二人は顔だけ振り向いて、自分たちの後ろにかくれた私を不思議そうに見た。二人の肩のあいだから、あの女の人が立ち去るのが見えた。キレイな足が遠ざかる。
「どうしてー?」
私たちも歩きだす。
「なにが?」
「うんー……あのね、いまそこで……」
「痛てっ」
あいつが頭を押さえてかがみ込んだ。天井から吊りさげられた「大売り出し」の赤い看板が揺れてる。バカ。頭をぶつけた。あいつはかがんだまま看板を見あげた。
「なーんだよこれー」
「ははは」
「バーカ」
あいつは後ろ頭をなでながら立ちあがった。
「KIDOくーん、これ、ひどいよなぁー?」
「ははは、そうですよね、ははは」
KIDOくんは両手でお腹を抱えて笑ってる。
「ったく、あ、ほら見てよー、血が出てるよー」
あいつはなでてた手を広げて見せた。ごつごつした手。指先にちょっとだけ、血がついてる。
「はは……」
「BAKAがむやみにおっきいから悪いんだよー」
「違ーうよ。こーれ、絶対チビな奴が吊したんだよ、しかもバカの。あー痛てえー」
「はは、男子禁制の店なのかもしれないですね、はは」
自分の手についた血を詳しく調べるあいつ。
「BAKA、キズ、見せて?」
「いーよ、こんぐらい」
「見ーせーなーさーいー!」
あいつが頭をつき出した。黒くて長い髪をかきわけたら、白い頭皮に赤黒い切り傷がちっちゃくできてた。そこから血がにじんでる。
「いたいのー?」
「痛い、ですか?」
「痛い、で、す」
つき出した頭から聞こえる声。
「バンソーコ、はる?」
「え、でも、髪剃らなくちゃいけませんよね?」
「あ、いや、痛くないよちっとも!」
あいつは私の手からサッと頭をひっこ抜いた。ずっとさげてたから顔に血がのぼってまっ赤になってる。
「お、あぶねー! またぶつけるとこだった」
「ほんとにだいじょうぶなのー?」
「はい! ほんとーに、大丈夫、です!」
見あげると、看板がまだ小さく揺れてた。私たちはまた歩きだした。
「あの看板さー、魚のコーナーの前にあるってことは、魚の大売り出しってことだよねぇ?」
「そう、ですね」
カゴにトマト缶を入れる。
「俺たちって今日、魚使わないだろ? ってことはさー、俺は、自分にはなーんの意味もない看板に、頭をぶつけたってことだよなー?」
「そういうもんですよ、セラビーセラビー」
ペンネを入れる。
「まあ買い物に来るのが俺たちだけじゃないのは分かるけどさー、せめてもう少し高く……あ、でもあんまり高いと目立たないかー」
冷凍食品の棚、そのとなりにアイス。どうでもよくなっちゃった。
「要するに、俺がもっと注意してればよかった……のかぁ? いや、そもそもこのスーパーに来たってこと自体が……いや、それよりも生まれてしまったこと……」
「SATOさん、あんまり原因を辿り過ぎるとビッグバンまで行っちゃいますよ」
パンの棚。食パンを入れたらカゴがいっぱいになった。
「んー、まあねー。確かにそこまで時間を溯っちゃったら、いいとか悪いとかわけわかんなくなるけどさー……でも、あれじゃない? 時間を溯らないであの瞬間だけを考えるにしてもさ、食欲とか金銭欲とか、さらには生きることの原因、みたいにどんどん小さくミクロになってって、結局おんなじことに……」
レジのおばさんはときどき上目遣いで二人の顔をうかがってた。
「……でさ。だからほんと、いろんなことをごまかしながら……」
カゴのものを袋につめかえながらも、ずっと話し続けてる二人の後ろ姿。なんだかさみしい。袋につめかえ終わってカゴを重ねて、スーパーを出る。そう言えば、あのキレイな女の人はどうなったのかなあ。
一方通行の細い路地。ゴチャゴチャにぎやかな商店街。通りの両側には、うじゃうじゃ自転車がとめられてる。
コンビニ、ディスカウントショップ、立ち食いソバ屋、居酒屋、カラオケ。お店からもれた明かりが照らす人込み。向こうの山手通りまで続く、二列の赤白ちょうちん。途中のアーチに書かれた商店街の名前。
「……それであいつ『お前がそんなに懐の狭い奴だとは思わなかったよ!』なーんて、無意味な言葉を連発して感情とかプライドに訴えかけようとするんだけどさ、そいつがまた……」
買い物袋を携えて、まえを歩く二人の背中。
なんなのこれ? もしかして私、仲間ハズレ? ……なんてひどい人タチだー。
あいつの笑い声。KIDOくんの笑い声。人込みから笑い声。さみしいなあー。
見あげると、電線が網の目みたいに張りめぐらされてる。雑居ビルにはさまれた細い空が青く、暗く、高く、落ち着いてる。
そう言えば……お母さんも、こんな気持ちで帰って行ったのかなあ。
ガタンゴトン、東横線の電車の音。シャッターがおろされたお店。おそるおそる進むシトロエン。そのまえを横切るおじいちゃん。山手通りをうずめるタクシーの列。「……なんだよー」と笑ってあいつが振り返る。
「ところでGUU、どっちが先に作る?」
私は口をぐっと閉じて答えなかった。私を一人にしたバツとして、しばらく二人をムシすることに決めたの。
「なあ、GUU」
電柱にはいろんな貼り紙がされてる。ライブ、イベント、自民党、粗大ゴミ回収、それに……
「あ……」
「なに?」
「なんですか?」
早くも口をきいちゃった自分の意志の弱さにため息がでた。でも、こんなの見せられたらしかたないよ。
「……見て、これ」
迷い猫の貼り紙。「探しています!」の文字。行儀よく座ってこっちを見てる子猫の白黒写真。
(特徴)現在二歳のオス猫。全身黒毛。目は緑色。尻尾は長くてまっ直ぐ。見かけた方は……
「ALに、似てない?」
「まさか。だってALはEIJIからもらったんだぞ?」
「EIJIだってALのことひろったのかもしれないでしょ?」
あいつは口ごもった。
「そうかもしれないけど……じゃあこの猫がもしALだったら、返すのか?」
「それは……だって、ALは私たちの家族なんだよ? ALだって、きっと、私たちと一緒にいたいと思ってるはず!」
あいつがうつむいた。
ALが家にきたのは一年前。EIJIの家から子猫を連れて、帰りの道で私たちは名前を考えた。
「ALってのはどう?」
「なんなの、ALって?」
カゴのなかで眠る子猫。
「AL・GREENだよ。こいつは黒猫で、目が緑だろ? それで、AL・GREENは黒人で、ファミリーネームがグリーン。な? ぴったりじゃん」
家に着いて目を覚ますなり、見慣れない場所におどろいて子猫のALは毛を逆立てた。走り回って隠れたALを二人であちこち探し回った。
「いた! ここにいたよ、YASUKO!」
やっと見つけたALの緑色の目には、手を差しのべてる私たちが小さく映ってた。
それからしばらくはおびえてたALも、だんだん私たちにも私たちの家にも慣れてきて、いまでは毎日イタズラばっかりしてる。
花は食べるわ、キッチンは荒らすわ、ティッシュは引っかき回すわ、もう大変。いまのパキラも四代目。
あんまりひどいイタズラをしたときは、トイレに閉じ込めたり段ボールに閉じ込めたりしてしかるの。「AL、そこで少しは反省しなさい!」って。そうすると、なかから「にゃー」って声がする。「ごめんなさいー、ボクが悪かったよー」って。
しばらくそのままにしてからのぞきこんで「もうあんなことしちゃダメだよー?」って言うと、ALは目を閉じてほんとに反省してる声を出すの。でも、出してあげるとすぐにおんなじイタズラをしてまた怒られる。ちっともこりない。
でも、ほんとはALはめちゃめちゃやさしいやつなの。
いつだったか、あいつがケンカして出て行った夜、部屋で一人泣く私の横にそっと座って「どうしたんだよー」って涙をなめてくれた。
「……私、ALがいない生活なんて考えられない」
「俺だって」
でも、まえの飼い主も私たちみたいな気持ちでALのことを思ってたら……おんなじ気持ちで一年間ずっと探してたんだとしたら……なんて辛いんだろう。
山手通りに出た。遠くでクラクションがなった。
「ねえ、EIJIに、ほんとのこと、聞いてみよ?」
「……」
あいつは答えなかった。
わかってる。ALはALだけのもの。私たちのものでもまえの飼い主のものでもない。でも、でも……
ALとずっとずっと一緒にいたいの。一緒に寝たり、一緒にご飯を食べたり、じゃれたり、ケンカしたり、そういうことをずっとしてたいの。BAKAやお父さんやお母さんやおばあちゃんや、KIDOくんやAKIさんやMANABUさんやMIKAちゃんやMONKEYや、私が大好きな人たちとおんなじように。
気がつくと私たちは速歩きしてた。早くALに会いたくて会いたくてしかたなくなってた。
あいつが先頭をきって次にKIDOくん、そして少し離れて私。中目黒駅前の人込みをすり抜けて、思いきって私は走りだした。二人を抜いて、いちばん先頭に。ガードの向こうから空が開けた。広い、夕闇。
二人は私に抜かれると、自分たちも負けずに走りだした。後ろから足音が迫ってきて、BAKAとKIDOくんの後ろ姿が私を追い抜いてった。茶色と水色のソールが夕闇に瞬く。
「ずるーい!」
私の声が響いた。KIDOくんは首をちょっとだけ私に向けると、足をゆるめてBAKAと私の中間くらいを走った。山手通りをうずめるヘッドライトの渋滞。空にはまっ青な闇が、じっと月の出を待ってた。
汚れて黒ずんだ白カベにまっ黒なドア。二階建ての古アパート。その二階が私たちの家。息をきらしながら私が階段をのぼっていくと、あいつとKIDOくんはドアのまえでタバコをふかしながら私を待ってた。
「早く、鍵」と、あいつが言った。
そうだ、私がカギを持ってたんだー!
二人を背にしてカギを差し込む。ドアの向こうからALの声がする。私は先を越されないように注意深くカギを回して、ドアを素早く開けてなかにもぐり込んだ。すぐにドアを閉めてカギをかけた。
「おーい!」
「ははは」
あいつはさけびながらノブをガチャガチャさせてる。振り返ると、ALが座って私を見あげてた。
「ALー!」
「にゃー」
ALをぎゅっと抱きしめてキスした。
「GUU! 汚ねーよ!」
ドアをドンドンたたいてうるさいから、しかたなく開けてあげた。
「あぁー、ALくぅーん! 会いたかったよぉーう! だっこさせてよぉーう!」
あいつは泣く振りをしながら両手をさしのべた。かわいそうだから抱かせてあげた。
あいつはALを高くあげたり抱きしめたりして、キスした。KIDOくんはその後ろで順番を待ってる。突然訪れたキスの嵐にALはキョロキョロびっくりしてる。
「BAKA、ほんとに、EIJIに、聞いてね……」
「……分かってる」
KIDOくんは控えめにキスすると、ALを私に手わたした。体をダラーンとたらしてされるがままのAL。
「じゃあ俺、先にペンネのほう作りますね」
「うん」
私はALを抱いてまっ赤なソファーに座り、ヒザにのせてタバコに火をつけた。あいつの電話してる声が小さく聞こえる。キッチンからトントンまな板の音がする。
青いローテーブルにはオレンジ色の灰皿だけがポツンとのってる。クリップライトで照らされたパキラの影が私の足もとまでのびてる。
となりの部屋にはベッドが見える。ベッドにはリンゴの柄が入った白いカバーがかけられてる。その脇にはあいつのギターが三本立ってる。ALが私を見あげてないた。
だめ……やっぱりALはわたせない。どんなこと言われてもいい。私が守ってみせる。だれよりも愛してみせる。だから……お願い。
白い冷蔵庫が「ぶおおおーん」ってさけんだ。なんだかいつもより高くて長い声。ため息と一緒にはいた煙は、かすれてのびた。その先にあらわれた、あいつの顔。
あいつは伏目がちに立って、両手を力なくたらしてる。
「GUU……」
悲しげにつぶやいたあいつの声。私はALを抱く手に力を込める。
「やっぱりALは……」
KIDOくんも手を休めてこっちを見てる。ぐつぐつナベの音。漂うトマトの匂い。
「……EIJIの飼ってる猫の子供だってさぁ! ALくぅーん、おいでぇぇ! これからもよろしくねぇぇ!」
あいつは私のヒザからALを抱きあげると、何度も何度もキスをした。
「……ばか……バカー!」
私はALごとあいつに抱きついた。涙が出た。あいつも笑いながら泣いてた。KIDOくんは笑いながら鼻をすすり、また作りだした。
「……みんな、みんな大好きー!」
抱きあったままぐるぐる回る私たちにはさまれたALの後ろ頭。ピンと立てた耳。あいつの肩をつかむ両ウデ。
「今日はお祝い、ですね?」
「うん、ALを囲んでパーティー!」
「戸籍などという拘束を全く必要としない、愛を分かつ家族、という死ぬまで外れることのない首輪をつけた記念日として……」
「ははは、やたら聞こえが悪いですね」
あいつがまたALにキスした。
「ALと俺には違う血が流れていようとも、同じ家族という意識が流れている。意識は確実に血を越える! いや、血とは意識のことだ! 刷り込みは両方向に働き……」
「いつまでもALと愛しあいます記念ー」
「そう端的に言うなよ。俺だってなぁ……」
「あ、YASUKOさん、できましたー」
KIDOくんがナベをかき混ぜながら火をとめた。
「あー、ひどーい。BAKA、なんにもやらなかったー」
「あ……KIDOさん、ごめんな、さ、い」
「ははは、いいんですよー」
水の流れる音。KIDOくんが手を洗ってる。
「ダメだよー」
「あ……じゃ、じゃあ俺……そ、そうだ! セッティングから後片付けまで、全てやらせていただきます! それも完璧なる手際で!」
KIDOくんは笑顔で手を拭いてる。
「ほんとに、いいですよー」
「ダーメー。じゃあBAKA、それでいいからしっかりやりなさい」
「はっ。仰せのままに!」
私はサラダにとりかかった。
セロリの筋をとり、ニンジンの皮をむく。それを千切りにして、お皿に敷いたサニーレタスにのせる。ガリガリ、トントン。
今度はドレッシング。ボウルに塩、コショウ、赤ワインビネガーを入れてよく混ぜる。そこに、オリーブオイルを少しずつ加えながらとろっとするまでさらにかき混ぜる。シャカシャカシャカ。
できあがったドレッシングをさっきの野菜にかけて出来あがり。
「BAKA、できたよー」
「はいっ、後はお任せを!」
あいつはわざとらしく忙しそうに働いた。
冷蔵庫から飲みかけの白ワインをとり出して、料理をローテーブルに運ぶ。ときどきヒタイの汗を拭くマネをしながらせっせと運ぶ。
KIDOくんは落ち着かない様子で座ってる。私はタバコの煙をあいつの顔に吹きかける。
「遅ーい!」
「は、はいっ。申し訳ございません!」
ALが私のヒザのうえで体を震わせるほど大きなあくびをした。
「王様も待ちくたびれてるよー!」
「……只今、完了致しました!」
あいつはソファーに倒れ込んだ。その向こうでKIDOくんが「お疲れさまでした」とささやいた。
「疲れたー!」
「KIDOくんのほうが疲れてるんだよー?」
「ははは、そんなことないですよー」
「ま、とにかくALの出所が分かってほっとしたことを祝して……」
私たちはグラスをかかげた。
「ははは、急にチープになりましたね」
「そうだよー」
「まぁまぁまぁ、いいじゃあないの。とにかく、チァーズ、乾杯!」
私たちはグラスをカチンとあわせた。ALは自分のお皿にのせられた山盛りの夕食にかぶりついた。ほんとはダイエットちゅうだけど、記念日だからめちゃめちゃ多い。
「でーも、不思議だよなー。ALがいるだけでさ、全然家の雰囲気違うんだよ。見てるとなーんか、なごむって言うかさ。ALが来る前はGUUとケンカばっかしてたけど、今はほとんどしないしなー」
あいつはすぐに飲み干して、グラスにワインをつぎ足した。
「それに最近、やたら生活が規則正しいんだよー。朝は朝メシやんなきゃないから早起きするし、外に出かけるときも晩メシやんなきゃとか、遊んであげないとストレスたまるかなぁとか思うから、ちゃんと帰るようになるんだよねー」
サラダもワインもペンネも、めちゃめちゃおいしい。KIDOくんもワインを飲み干した。
「子供ができた、みたいなもんですか?」
「うーん……子供でもあり、友達でもある……両方、かなぁ。KIDOくんも飼ったらー?」
「ははは」
ALはご飯を食べきれずに残して、ゴロンと横になって、ペロペロ毛づくろいしはじめた。
「おっきくなったよねー」
「そうだなー」
「そうですねー」
ALは三人に見られてるのに気がついて「みゃー」とないた。
「AL、みーんなに見られて恥ずかしいんでしょー?」
「どれどれ」と、あいつはALを抱きあげてヒザにのせた。
「やっぱり、ちょーっとデブかなぁー」
「明日からまたダイエットだねー」
「ダイエットしてるんですか?」
あいつは片方の手でヒザのうえのALの背中をなでて、もう片方の手でワインを飲んだ。
「俺もGUUも、デブ猫嫌いだからねぇ。体にもよくないらしいし。ALってさ、家猫だろ? だから余計、運動不足になりやすいらしいんだよね」
「……なーんか、私のこと言われてるみたい」
確かに、このあいだお腹にさわったとき、ちょっとやばいかなーって思った。たぶんシゴトをやめてから一日じゅう家でALとごろごろしてることが多くなったからだと思う。ほんとに家猫みたいなの。
このあいだなんか、あんまりヒマだったから雑貨屋さんでも見に行こうと思って準備したの。でも、玄関のドアを開けてびっくり。
太陽が高い時間に外に出るのがあまりに久しぶりすぎて、太陽ってこーんなにまぶしいものなのかあーって。後ずさりしてやめちゃった。
そう言えば、ちっちゃいころ、テレビで見たアメリカの太陽があまりにも大きくて、自分が見てるのとおんなじ太陽だなんて信じられなかった。だからずっと日本とアメリカでは違う太陽がのぼるんだと思ってた。
「ねえ、月よりも太陽のほうがおっきいって、実感できる?」
「はあ?」
「私、頭ではわかってるんだけど、いまだに信じられないの。それと地球がまるいってことも」
KIDOくんはサラダをさしたフォークをとめた。
「……確かに、近過ぎたり、遠過ぎたり、小さ過ぎたり、大き過ぎたりするものは、実感として把握できないかもしれないですね」
あいつがタバコに火をつけた。
「触れることのできない真理。科学的真理。でもすごいよねえ、最初に太陽と月の大きさと距離を三角関数で測ろうなんて考えついたやつ」
「でも、怖いですよね。何か最近、知りたくなかったことまで知らされてしまうって言うか」
「そうだよなー」
KIDOくんは思い出したようにフォークを口に運んだ。あいつの口から煙がのびた。
「あのさ……もし、もしだよ、脳とか遺伝子とか人間の構造が科学的にどんどん解明されてってさ、例えば『人間は食と生殖のために生きるのである』とかって結論が出たとしてさ、それを基にして人間を教育したり法律を制定したり、そんなことになったらどう思う?」
「人間が生きる目的の発見、みたいなものですよね……抗いたいような、従いたいような……わけ分かんないです」
あいつが灰皿に灰を落とす。
「GUUはどうなの?」
「うーん……言ってること、よくわからないけど……」
「けど、なに?」
私はフォークをかみながら思い出す。
「いまの話にぜんぜん関係ないかもしれないけど……私が新潟のおばあちゃんに『幸せになるにはどうしたらいいのー?』って聞いたら『やっちゃんは幸せになりたいの? それだったらいっぱい笑いなさい』って言われたことを思い出したの」
「いっぱい笑え、ねえ……そう言えばさ、幸福の対義語ってなにかなあ? 不幸は対義語って言うよりも幸福以外のものを指す言葉だろ? そうじゃなくて対極を表す言葉……いや、それよりも、幸福には三つの段階があって、無、定義、獲得、その意味枠が……」
またはじまった。KIDOくんはペンネをほおばったままワインを飲んだ。
「おばあさんって、どんな人なんですか?」
「おばあちゃん? おばあちゃんはねー、もー、めっちゃめちゃかわいい人なの。サイって名前で、いま……八十六、かなあ。ちっちゃくって、いーっつも笑ってて、遊びに行くと『やぁーっちゃん、ほーれ、こんげおっきょなってぇー。まーずながまらしぇー』って言うの」
あいつが首をかしげた。
「それ、どういう意味?」
「うーんと……『やっちゃん、大きくなったね。とりあえずくつろぎなさい』って意味」
「ながまらしぇー、が、くつろぎなさい、なんですか?」
「うん。ながまる、って横に長くなる、寝転ぶって意味なの。そう言えば、去年はおばあちゃんちに行かなかったなあー」
ALが顔をくしゃくしゃにしてあくびをした。
「よく行くんですか?」
「うん。私、小学校三年生までおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に住んでたの。おじいちゃんはもう死んじゃったけど。……それでね、おばあちゃんちのまわりには田んぼがずぅーっと広がってて、ちっちゃいころはよくおじいちゃんとドジョウとかザリガニとかとって遊んでたの。だからかなあ。私ね、山とか海にいるよりも田んぼのあぜ道にいるほうが落ち着くの」
「YASUKOさんって新潟出身なんですかー。へえー」
あいつがタバコをもみ消した。
「GUU、あの話もしてあげれば?」
「あの話? あー、あれね」
私はタバコに火をつけた。KIDOくんは目をパチクリさせた。
「あのね、おばあちゃんちは農家なんだけど、農業だけじゃなくて養鶏もやってるの。それでね、卵を産まなくなったニワトリを肉にするじゃない、そういうニワトリのお腹には卵の黄身みたいなのがふさになって入ってて、それをとり出して水炊きにして食べると、もうめっちゃめちゃおいしいの。いま考えると気持ち悪いけど、私、黄身が大好きだったから、おじいちゃんと一緒によくニワトリを殺してた」
「ねー、KIDOくん。GUUには気をつけたほうがいいよ」
「ははは」
タバコの灰を落とすと、オレンジ色の光があらわれて、ゆっくりもぐった。
「でも、そのときはかわいそうだとか残酷だなんて思わなかったなあー。ただあのふさになった黄身が食べたくて、いっしょうけんめい殺して、羽をむしって……でも、肉は嫌いなの。鳥だけじゃなくてぜんぶ」
ALが後ろ足であごのところをかいてる。
「好き嫌いとか、激しいほうなんですか?」
「いまはそうでもないけど、ちっちゃいころはすーごかった。放課後まで給食が机にのってる子だったから。でもね、私、保健室の先生が大好きで、よくお昼休みとかに遊びに行ってたんだけど、その先生に『食が片寄ると性格も片寄るよ』って言われたのがめちゃめちゃショックで、それから、いじでも給食を残さないことにしたの」
いつのまにか冷蔵庫が静かになってる。
「俺、スイカがだめです。何て言うか、あの赤いところに黒い種がツブツブーってなってるのを見ただけで寒気がして」
「俺は……別にないなー」
ALがあいつのヒザでまるくなって眠ってる。手をのばしてALの足をひっぱってみた。かわいいなー。熟睡してる。私は煙をはき出した。部屋がもくもく煙ってる。霧のロンドン。
部屋を満たした青白い煙をローソクの炎がのび縮みしながら揺らしてる。空になったワインボトルをすてに行ったKIDOくんは、帰りにハイネケンと梅酒を手にしてた。
ごちゃごちゃしたローテーブル。サラダもペンネもほとんどなくなってる。もう十一時。早いなあー。起きてからもう九時間。
「SATOさん、最近音楽のほうはどうですか?」
あいつは窓を少し開けて換気した。
「よくないねー。ドラムのやつがぜんぜんやる気なくてさー。あいつ、クビだよ、ほんっとに」
「一人でやることじゃないぶん、大変ですよね」
「まぁそのぶん、うまくいったときの気持ち良さは大きと思うけどね。でもあいつはクビ」
あいつはハイネケンを口にした。
「その人、かわいそう」
「かわいそうなんかじゃないよ。俺たちが一生懸命練習して、曲作って、さあライブ前最後のスタジオだって日に、あいつなんて言ったと思う? ゲンチャで酔っぱらい運転してコケて骨折した、って言ったんだぞ? 考えられるか? なんでこんな大事なときにそんなことしてんだ?」
「その人だって、骨折したくてしたんじゃないよ?」
「そんなこと言ってんじゃないよ。なんで事故る可能性のあることを、こんなときにやってんのかって言ってんだよ。分かるだろ? 今回だけじゃない。あいつ、ライブ前になると必ずと言っていいくらい、どっかケガすんだよ。それでいかにも不幸だったみたいに弁解してさ。不幸なんかじゃない、お前のコンディション作りが悪いんだっつうんだよ」
あいつはタバコに火をつけた。
「でも、やっぱりかわいそうだよー。だってその人、友達なんでしょー?」
あいつは勢いよく煙をはき出した。
「友達だけどさ、それとこれとは別問題だよ。俺たちは友達と仲良くするために音楽やってんじゃない。やりたい音楽があって、そこに集まった結果として友達になるんだよ。だからそれができないんだったらやめてもらう。友達としては続けられるかもしれないけど、一緒に音楽やってくことはできない」
「その人、それで納得するのー?」
あいつはせわしなく灰を落とした。
「しなくてもやめてもらう、たとえ友達じゃなくなったとしても。冷たいようだけど、俺にはあいつと付き合ってくことよりも、音楽のほうが大切なんだよ」
私と音楽だったら、って聞こうとしてやめた。バカみたい。
私はあいつに音楽をすててほしいなんて思ったことないし、それどころかあいつがキーボードに向かっていっしょうけんめいやりはじめると、遠くからALと一緒に「がんばれー」って応援してる。
あいつには世界中のステージに立つような人に絶対なってもらいたいし、それにくっついて世界中を旅行するのが私の夢。
「あのー……俺、ちょっとタバコ買ってきます」
KIDOくんは目を伏せたまま立ちあがると、ライターをポケットに入れて出て行った。あいつは自分のタバコの箱を開けて「俺のも頼めばよかったなー」って言った。
「ところでGUU、なにか考えてんの? そのー、なんだっけ? MICROMANCEの内容をさ」
私は梅酒を飲んだ。あー。顔がカアーって熱いー。
「言わなかったー? ALがかぁわいいー、とかー……」
「ロマンスとか、だろ? それは分かってんだけどさ、テーマだよ、テーマ」
「テーマ? MICROMANCEだよー?」
「いや、それはタイトルでしょ」
ALがあいつのヒザのうえで寝返りをうった。
「うーん、それじゃーあー……ささいでー、ロマンチックなー、ことー?」
「いや、それは……表現方法、でしょ? そうじゃなくてさ、その方法を使ってなにを表現するのか、だよー」
あいつの手に握られたハイネケンの缶。
「表現って……例えばー?」
「例えば……そうだなあ……喜びとか、悲しみとか、怒りとか、絶望とか、いろいろあるじゃん。感情じゃなくても、例えば愛についてとか、美についてとか、社会構造の仕組みについてとか、なにか自分の内で考えたり感じたりしたものを形にして外に表すことだよ」
「じゃあー、やっぱりー、ALがめちゃめちゃかわいい、とかじゃなーい?」
私はグラスをローテーブルにおいた。
「うーん、いやー、まぁそうなんだけど……でもさー、それだったら小説なんてめんどくさいことしないでさー、ALはこんなにかわいいんだよって話して歩けばすむことじゃないかー? まあ話せる人数には限りがあるだろうけどさー」
「でも、それじゃあシゴトにならないじゃなーい」
「仕事って言うけどさ……なんだよ、もしかして、仕事がないから小説書こうって思ったのか?」
「そうだよー。だってー、寝転んでー、好きなこと書くだけでいい、って言うからー」
おいたグラスの周りに水たまりができてる。
「……それじゃあ、ダメ、なのー?」
「いやぁ、だめって事はないだろうけどさぁ……」
足もとにのびてるパキラの影。五枚の葉。
「じゃあー、BAKAはー、どーして音楽やろうって、思ったのー?」
「俺? 俺が音楽やりたいって思ったのはさ、レコード聞いてて『ああ、ここはもっとこうしたほうがいいのになー』とか『どうしてこういう曲がないのかなー』って思ったからなんだよ。それでそのうち頭の中で曲が浮かぶようになって『ああ、これいい曲だな』って思うと、それを形にして何度も聞いてみたくてしょうがなくなってさ。だから俺の場合、表現することに必要性がある、わけだよ。うんうん」
のばしたまえ足を交差させて眠ってるAL。
「お金はほしく、ないのー?」
「そりゃあ金は欲しいけどさ、目的ではないんだよ。目的は、自分にとってこれ以上ないって曲を書くことだから。売れる売れない、じゃなくて」
スリッパからのぞく、私のパープルの足のツメ。動かしてみる。
「でも、売れたら、嬉しいんでしょ?」
あいつはALのしっぽをつかんで、はなした。
「そりゃあ、売れたら素直に嬉しいよ。売れるってのはさ、例えば音楽なら、その曲を何度も聞いてみたい、じっくり一人で聞きたい、自分の手元に置いておきたいって思うから買うわけだろ? それってさ、自分が認められてるってことだからやっぱり嬉しいんだよ。でもさー、使い古された言葉だけど、自分が好きで書いた曲が売れるのは嬉しいけど、好きでもない曲を書いて売れても嬉しくないんだよなー。例えばさ、自分の顔で女にモテんのは嬉しいけど、こういう顔がモテんだろうなって整形してモテても嬉しくない、みたいにさ」
「でも、売れなかったらバイトしなくちゃいけないんでしょー? だったら、そーゆー曲でも少しは練習になるんだからー、作ったほうがいいんじゃなーい?」
「確かにさ、そういうふうに使い分けてもいいとは思うよ。でも俺にはそれが割り切れないっていうかさ、なんか、自分の好きなことを冒涜してるような気がして嫌なんだよなー」
食べかけのチーズ。あいつの歯形。
「ふうーん、難しいんだねー。私なんか、なあーんにも考えてないのに」
「うーん……でもさ、意気込みで作品が評価されるわけじゃないし、されちゃいけないんだよ。意気込みだけじゃない。作者が誰だとか、その作品の作られた背景がどうだとか、そんなのは作品の評価にはぜんぜん関係しないことなんだよ」
ドレッシングまみれのサニーレタス。トマトのソースにもぐったフォークの頭。私は足をバタつかせる。
「……なーんか、めんどくさくなっちゃった」
「あ……いや、そう言われると困るん、で、す、け、ど」
ALがゆっくり目を開けて、まばたきして、立ちあがって、のびをした。
「まぁ、ほら、GUUはALのかわいさとか表現したいんだろうから、その……やっぱりそこにも必要性があって……だから、そのー、やるだけやってみたら? もしかしたらすごいのが出来るかもしれないし。ビギナーズラックってのが……」
ALがあいつのヒザからおりて、こんどはKIDOくんのいた場所でまるくなった。ゆっくり、目を閉じた。
「KIDOくん、遅いねー」
「もしもし? 聞いてる?」
私はタバコに火をつけた。ローテーブルに並ぶ三つのグラスと二本の缶。梅酒の入ったグラスに浮かぶ、とけて小さくなった氷。ビールの入ったKIDOくんのグラスの底からは、細かい泡の隊列が消えてしまいそうにのぼってる。
「そう言えばKIDOくん、辛いことあったって言ってた」
あいつが黙り込んだ。時計が一時を回ってる。私のタバコの先から流れる青白い煙があますことなく滞る。ローソクがALの寝顔を揺らしてる。あいつはハイネケンの缶を一気に口に傾けて立ちあがった。
「ちょっと、見てくるわ」
ローテーブルを回って歩く、きゃしゃな巨人。煙に頭をつっ込んだ。ALは眠そうに目を開いて、また閉じた。
巨人の長い影が私の体を通り過ぎる。スリッパの足音がとまり、ドアの開く音がする。タバコの灰を落とそうとして、吸い殻があふれそうになってるのに気がついた。
片手でタバコを吸いながら灰皿をキッチンに持って行くと、玄関のドアの向こうからあいつの声がかすかに聞こえてきた。
「……なにやってんだよ!……いいから、とにかくやめろ!……」
灰皿をとりあえずコンロのうえにおいてドアからのぞいてみた。すぐ近くであいつが、うつむくKIDOくんの正面に立って、なにか話してる。
パープルのツッカケに足をつっ込んで、ツカツカ歩いて近づくと、あいつは私に気がついた。タバコを吸ってはき出すと、澄んだ夜空が汚れたみたいだった。
「どうしたのー?」
「……ちょっと、な。KIDOくん、とにかく家に入ろう」
あいつはうつむくKIDOくんの肩を抱いて歩きだした。私はもう一度煙をはいてみた。こんどは風にのって高く混ざって行った。
玄関のドアを開いたら、ドーッって水の音がする。あいつがキッチンでなにかを水に流してる。近づいて横からのぞくと、透明な包みから白いさらさらの粉を流してた。
「なに、してるの?」
「KIDOくん、これやろうとしてたんだよ」
「なあに、これ……もしかしてー!」
あいつはうずを巻いて穴に流れてく白い粉を見つめたまま、ゆっくりとうなずいた。
「ちょっとKIDOくん! どうしてこんなことするの!」
KIDOくんはうつむいたまま「は、はは」と力なく笑った。
「笑えるようなことじゃないでしょ! ちょっとここに正座しなさい!」
「GUU、なにもそこまでしなくても……」
「BAKA、これは大変なことなんだよ! 一人の友達がダメになるか、ならないかのせとぎわなんだよ!」
私があいつを黙らせると、KIDOくんは私の正面にゆっくり正座してうつむいた。
「いーい! KIDOくん、君、ロクデナシだよ! どうしてこんなことするのか、ワケを話しなさい!」
なぜか吹き出したあいつをにらんで黙らせた。KIDOくんはためらいながらゆっくり静かに話しだした。
「俺……大月先生のアシスタント、クビになったんです」
「写真の?」
KIDOくんは小さくうなずいた。
「……先生は、アシスタントのプロが欲しかったんです。アシスタントって、いかに先生が気持ちよく撮れるか、そのことをいつも考えていなければいけないんです。安い手当で、毎日毎日、ほとんどの時間をそれにつぎ込んで。だけど……だけど俺は、アシスタントのプロになりたいわけじゃない、写真のプロになりたくてアシスタントになったんです! 大月先生につけばその道が開ける可能性が高いから、だから先生のアシスタントになりたくて……それでやっとの思いでなれて……確かに少しは技術を盗むこともできました……だけど、分からなくなったんです。自分はプロの写真家になりたいのか、それとも……とにかく何も、かも」
キュッと蛇口をひねる音がした。
「……でも、だからって、こんなことしていいことにはならないんだよ?」
私の言葉をさえぎって、あいつが話しだした。
「GUU、KIDOくんはさ」
「BAKAは黙ってて!」
「黙んねぇよ! あ、ごめん……でもさ、俺、分かる気がするんだよ、KIDOくんが悩んでることって。俺も悩んだことあるよ。自分は表現をしたいのか、認められたいのか。初めはいいものを作れば売れるって思うんだけど、やってるうちにさ、売れるものといいものが必ずしも一致しないって気付くんだよ。それって好みとか売り出し方とかだけの問題じゃなくて、受け取る側の無知とか鈍感とか、そういうのもあってさ。だから、結構売れたものと爆発的に売れたものとの間の差ってそんなに問題じゃなくて、どういう人たちに売れたのか、そっちのほうが重要で。でもね、KIDOくん。売れたものが必ずしもいいものとは限らないけど、いいものは必ず売れるんだよ。いいものっていうのはね、それを手にした者に世に広げる使命を負わせるものなんだよ」
KIDOくんは正座してうつむいてる。モモのうえで握った手を見つめてる。
「分からないんです……いいものって、何なのか……誰にとって、いいものなのか……誰に向かって表現するべきなのか……」
「それは、自分だよ。自分にとっていいものだよ。人にとっていいものなんて、分かるわけないだろ? 表現だって、本当は自分に向かうものなんじゃないのか? 例えばさ、音楽とか写真とかは同じものがコピーできるからいいけど、もしそれが陶磁器だったりしたらさ、最高の出来のものは手放したくないわけだろ?」
「……だけど、自分に向かうものだったら何も、形にしないで自分の中にしまっておけば済むことじゃないですか」
「いや、形にすることで、自分は自分とはっきり向き合えるんだよ。瞬間的には自分は一つしかない。つまり、過去の自分に今の自分が運動をもって同時に向かい合うためには、やっぱり形にすることが必要なんだよ。だから、どれだけありのままの自分を形にできているか、そこに表現の優劣が生じると思うんだよ。そのためには当然、技術も必要だし、自分自身の考察……」
「ねえ! どうしてこんな話になってるの?」
あいつがキッチンに寄りかかってる。
「あ、いや、だから、KIDOくんの前にはそういう状況があってさ……」
「それでも、こんなことしていいことにはならないよ」
「ちょっと待てよー、それじゃあ追い詰められたネズミが猫を噛んじゃいけないって話になるじゃないかー」
「なあに、それじゃあBAKAはKIDOくんがダメになってもいいって言うのー?」
「いや、そういう意味じゃなくてさ……」
KIDOくんが顔をあげた。
「SATOさん、俺が悪かったんです……どうもすみませんでした」
「じゃあ、もうしないって約束しなさい!」
「絶対に、もう、やりません」
「約束だよ!」
「はい」
正座したKIDOくんを立ちあがらせて、今度は「もうドラッグをしません記念パーティー」をした。時計は二時を回ってた。
白い冷蔵庫は静かに眠り、ちっちゃいパキラは薄い影をのばしてる。青いローテーブルではローソクが揺れ、耳を澄ませばまっ赤なソファーでまるくなってるALの寝息が聞こえそうな気がした。
ソファーの背中の窓からは、まっ黒な夜空が差し込んでた。私はタバコをふかしながら、今日という一日が自分にとって、とても意味のある日だったに違いないって思った。