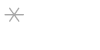MICROMANCE
1998年 木戸隆行著
3
私はいま、まっ赤なソファーに寝転びながらワープロに向かってる。ときどき足をバタつかせながら、あなたが読んでるこの小説を書いてる。パキラの新芽を横目で見ながら、私のかわいい五本の指が踊るように……動いたらいいのに。
私がいま向かってるのは、ワ、タ、シ、の、黄色いノート型ワープロ。先月の終わりにあいつが約束どおり買ってくれた、かわいいーワープロ。まっ赤なソファーにのせても青いローテーブルにのせてもぴったり。どこにのせてもぴったり。もー、ほんと、めっちゃめちゃかわいいーの。
でもね、最初は黄色じゃなくて黒だった。あいつといろいろ電器屋さんを回ってみたんだけど、どこに行っても黒かグレーのワープロしかなくて、私、どーしても黄色のじゃなきゃ嫌だったから、あいつにぬってもらったの。
その日はもう一日中うれしくてうれしくて、画面を開いたり閉じたりするだけで「きゃー」ってさけんでた。ALも一緒に「にゃー」ってさけんでた。あいつも「うるさーい、早く書けー」ってさけんでた。
いまも抱きしめたくてウズウズしてるけど、書くほうが優先。文豪はキビシイのだ。
「にゃー」
となりでALがボールペンにじゃれてる。白くて太いボールペン。あたまにゴムでできたアマガエルがくっついてて、ノックするたびに「ゲーコ」ってなく。
このカエルがはじめて家にやってきたとき、ALはソファーの陰に隠れて、じっとこの得体の知れない緑色のものの様子をうかがってた。
「なんだあ、あいつはー?」
いつまでもピクリとも動かないカエルの目をさけて、後ろからゆっくり近づく。かるくつついて逃げる。つついて逃げる。それを何度もくり返して、やっとALはカエルと仲良しになった。
いまでは頭にかみつくほどの愛しよう。愛されすぎてカエルはボロボロ。一時は手も足もちぎれたけど、私のブラックジャックのテクニックで治してあげた。今でもその手術の跡(ホチキスの針)が残ってる。
「ふあーあーあー」
あいつがとなりの部屋から起きてきた。
「あれ、GUU、どうしたの? こんなに早く起き……お? もしかして、仕事中?」
「そう。いま、い、そ、が、し、い、の」
「へえー! どれ、ちょっと見せてよ」
私は起きあがって、となりに座ったあいつにワープロを手わたした。タバコに火をつけた。あいつの横顔。はれぼったい真剣な目。
「結構、書いたねー」
「うん」
ローテーブルには、いっぱいになった灰皿と私の黄色いマグカップがのってる。マグカップからは湯気がのびてる。さっきいれたばかりのコーヒー。
「でもこれ、ほんとそのまんまだなー。日記みたい」
あいつは読みながら私のマグカップに手をのばした。
「あ、これ……この間俺に『あのときなんて言ってたー?』って聞いたの、この部分を書くためだったのかー?」
「うん」
あいつはカチャカチャとページをめくっていく。
「でもこれ、マズイんじゃなーい?」
あいつはコーヒーをすすった。
「どうしてー?」
「だってさ、俺は……俺は構わないけどさ、KIDOくんとかおばさんとかには許可をもらわないと、プライバシーの問題とか、いろいろあるんじゃないの?」
私は煙をはき出す。
「だ、い、じょーぶ」
「そうかぁ? まあ、確かにだめとは言わないだろうけどさー。でも、自分のこと書かれるのって、あんまり気持ちのいいもんじゃないと思うよー?」
「だって……二人をぬかしちゃったら話にならないじゃない」
あいつはコーヒーをローテーブルにおいた。
「いや、なにもドキュメントにする必要ないじゃん」
「なにそれー。このまえは『ありのままの自分を書け』とかなんとか言ってたじゃなーい」
「それはそういう意味じゃなくてさ、なんて言ったらいいかなぁ……そのー……外的事実じゃなくて、内的事実って言うか、そういう意味だよー」
ALはカエルのボールペンに飽きて毛づくろいしてる。
「ナイテキジジツ、って?」
「それは、そのー……なんて言うか、感じたり考えたりしたそのものって言うか、実際目の前にあるものじゃなくてさ……」
「だったら、写真はガイテキジジツじゃないの? 音楽だって実際に楽器から出る音でレコーディングするんでしょー?」
「いや、それを言ったら小説だって、実際にある紙と文字だろ? そうじゃなくてさ……」
私は灰皿に灰を落とした。
「と、に、か、く、これでいいのー。プライバシーとかなんとか言う人のことなんて書くつもりないし」
「ま、まあーいいんだけどね、なんでも」
開け放してた窓からさわやかな風が流れ込んだ。振り返った私の顔いっぱいに、まっ青な空が差し込んだ。向かいのアパートのベランダでは洗濯物がたくさん干されてる。
「BAKA、いい天気だねー」
窓にヒジをついて、タバコの煙を空に吹きかけた。空と私の汚れはあたたかな風にやさしくとけた。
今日は久しぶりの二人っきりの休日。私は小説家の特権でいつでも休日にできるけど、あいつは日曜日だけ。
あーあ、早く二人でラクラク印税生活がしたいなー。そしたら毎日休みにするのに。
見おろすと、幼稚園の制服を着たちっちゃい男の子と女の子がしゃがみ込んでる。二つの黄色いボウシが動いてる。となりの庭で、なにかいじってる。
「ねえ、お昼どうするー?」
「ん? そうだなー、ガゼボにでも行くかー」
そうか、春がきたんだー。
「うん」
あいつは立ちあがってのびをすると、となりの部屋に着替えに行った。私はタバコを消した。ソファーには私の黄色いワープロがちょこんと残されてる。開いたままの青白い画面には、ぎっしり文字が並んでる。
スイッチを切って画面を閉じると、ALが私を見あげてた。かわいい緑色の目。
「ALー、今日はBAKAと二人っきりでデートなのー。いいでしょー。だから、ALはうちでお留守番だよー?」
「にゃー」
「どーしてそんなうれしそうな顔するのー? 一人ぼっちになるのがそんなにうれしいのー?」
「にゃー」
「GUUの顔は見飽きたってさ」
あいつが着替えて部屋から出てきた。
「そーなの、AL?」
「にゃー」
「にゃー? ひどいなあー」
「ALだって、たまには一人になりたいよなー?」
「にゃー」
あいつはALを抱きあげてキスした。今度は私がしたくする番。
「ALのバーカ」
となりの部屋に行ってクローゼットを開く。少し迷ってから黒いパンツとセーターをとり出す。着替える。鏡をのぞき込む。今日もくるくるスパイラル。
まゆげを書いて、まつ毛をくるんとカール。マスカラ。ファンデーションと口紅を薄く薄く。
「まだー?」と聞こえるあいつの声を聞き流してマニキュアのキャップを回す。今日はぴかぴかシルバーにする。ツメのつけねから先端へ。フーフー。ムラなくぬって、フーフーフー。
疲れたー。
ベッドに倒れ込んでタバコに火をつける。鏡にはタバコをくわえて横になる私の姿がうつってる。
あーあ、私がもおーっとかわいかったらなあ。
私、横顔がサルみたいなの。したに行けば行くほど「あれれれ?」って盛りあがる。口はデカイしソバカスもある。いまはそうでもないけど、私、ちっちゃいころ、自分のソバカスが大嫌いだった。
それで小学校六年生くらいのとき、お母さんに「一生のお願い! 私、どーしてもほしいものがあるのー」ってたのみこんで、それまでちょっとずつためてた貯金をぜーんぶおろして、ソバカスの消える化粧水を買ったの。私の一大決心。
でも、ちーっとも、消えなかった。おつかいとかお手伝いとかしていっしょうけんめいためた貯金が一瞬にしてなくなって、自分のソバカスはちっとも消えなくて、あまりの悔しさに「お母さあーん!」ってジタバタしながら泣きわめいたの。
お母さんはとなりでジタバタしてる私を横目に、洗濯物をたたみながら「大人になったら消えるわよ」って慰めてくれた。
この年になって、確かに少しは薄くなったけど、それはあのころよりも日にあたらなくなったからだと思う。あのころは毎日、学校が終わってから日が沈むまでずうっと外で遊んでて、つねに日焼けしてる子だったから。
「なあ、まだー?」
あいつが顔をのぞかせた。
「ねえBAKA……私って、かわいい?」
「な? なんだよ急に」
あいつは部屋に入ると、寝転ぶ私のそばにきて座った。私はタバコを灰皿においた。
「どーなの?」
「か、かわいいよ、もちろん」
「どこがー?」
「どこが、って……そのー……くるくるのでかい頭も好きだしー、そのー、目とか唇の形とか……」
うえを見あげていっしょうけんめい話すあいつ。
「鼻は? 耳は? 手は? 胸は? お尻は?」
「い、いいねー」
「好き?」
「好きって言うか……愛、し、て、る」
「きゃー」
私はあいつに抱きついた。
「サルみたいなのにー?」
「俺、サル顔、好きだよ。GUUみたいな強面のサル顔が」
「きゃー」
よかったー。お父さん、お母さん、サル顔に産んでくれてありがとう。
……でも、コワモテ?
「ところで腹へってんだけど……まだ?」
ウデをあいつの首に交差させたまま、両手のツメを見てみた。もう大丈夫みたい。
あいつの背中越しにストラトキャスターってギターが見える。窓際にはキーボードがおかれてる。キーボードの横のデスクには楽譜とか、わからない黒い機械とかがごちゃごちゃしてる。
「ねえ、いい曲できたー?」
「ん? ま、あ、ね」
あいつの声が体に響く。
「じゃあ、そろそろワールドツアー?」
「ん? んー……ま、まあねえー」
「きゃー!」
あいつをぎゅっと抱きしめた。
「んー……それより、GUUが早く作家デビューできたらいいねー」
灰皿からタバコの煙がのびてる。私はまた寝転んでタバコを手にした。
「私は大、丈、夫。MICROMANCEでいきなり新人賞をとってー、それで……えーっと、ア、ク、タ、ガ、ワ、賞(?)、ついでにノーベル文学賞までとっちゃうの。『日本文学界に、驚異の天才アラワル!』って大騒ぎになって、うちのまえにマスコミの人がいーっぱいやってくるの。『ヒトコトお願いします、ヒトコト!』ってうるさいから、しかたなくキレイなドレスに着替えて外に出ると、なぜかお父さんとお母さんがいて『やっちゃんガンバレー』って手を振ってるの。私も手を振り返そうとするんだけど、ハッと気づいて手をひっ込めるの。あー、私はもう偉大なカリスマなんだから、イゲンを……」
「……さ、行こうか」
私はタバコを吸った。
「なあにー、ウソじゃないよー? 『知ってるつもり』から出演依頼がきたら、BAKAとALも一緒に出るんだよー?」
「はいはい」
「返事は一回」
「はーい」
私はタバコを消した。
「よくできました。それじゃあ行きましょう」
「はーい」
ALに見送られて玄関を出た。
気持ちいいなー。空気に色がついてるみたいに青い空。手をのばしたら染まりそう。イチョウの並木にびっしり開いたちっちゃな葉っぱが、さわやかな風にザワザワ揺れてる。太陽の光をいっぱいあびてまぶしいくらいに黄緑色に光ってる。
向こうに行列ができてる。チョコレート色のアパートの一階。クリーニング屋さん。そのうえの階のモスグリーンのベランダでは洗濯物がはためいてる。行列を通り過ぎるとき、おじさんが忙しそうに受け付けしてるのが見えた。
このおじさんはいつもは怖い顔してるけど、話しかけるとめちゃめちゃかわいい顔でニコニコ笑う。人と話すのが苦手で、必要以上にニコニコして疲れちゃうから、反動で普段怖い顔になっちゃうんだよってあいつが言ってた。
あいつと手をつないで山手通りを歩く。まっ青な空が遠くまで広い。楽しいなー。あいつも笑ってる。
「もうそろそろ桜が咲くんじゃないかなー」
「お花見しようねー」
駒沢通りとの交差点。自動販売機。横断歩道を左に曲がる。私の苦手な立体交差の橋が迫る。どんどん迫る。どんどん、どんどん。もうダメだー。私はあいつの手にしっかりつかまる。
「ん? ああ、GUUは橋がだめなんだっけ」
「ほんっっと、ダメ。私のとこだけヒューって落ちそうで」
「それって、体重が……いや……」
駒沢通りのカーブにそってゆるやかな坂をのぼりきると、ガゼボが見えた。アウトレットを恵比寿の方に越えて二十メートルくらいのところ。
ガゼボはオープンテラスのカフェ。まっ白なカベ、クリーム色のタイルの床。まるいテーブルとイスが店じゅうに並べられてる。
「込んでるなー」
短い行列のできたカウンターの向こうで、アフロの男の子がヒジをつきながらオーダーをとってる。グリーンのTシャツにデニムのエプロン。
「なんにする?」
あいつはメニューをとって見せてくれた。
「私は、ツナサンドと……ココア」
「じゃあ俺頼んどくから、GUUは先に席取っててよ」
見ると、入口近くのテーブルがあいてた。涼しそうな席。
「わかったー」
後ろに並ぶ女の子たちのすきまを通ってテーブルにつく。イスを引いたらガタガタなった。バッグからタバコをとり出して一息つく。テーブルにはシュガーポットとプラスチックの灰皿がおいてある。タバコの灰を落とそうとすると、となりのテーブルからアツイ視線を感じた。
これって! もしかして、私、モテモテ? きゃー! めちゃめちゃカッコいい人だったらどうしよう!
カッコよくタバコの煙をはき出しながらチラっと見たら、小学校一年生くらいの、わんぱくそうな男の子がフォークをくわえながら私をじいっと見てた。
なあーんだ。ガッカリ。
男の子のとなりには、ニットキャップをかぶったカッコいい女の人が座ってる。たぶんお母さん。さらにそのとなりのイスには、ちっちゃくて毛の長い犬がきちんと座ってる。
男の子は私と目があうと、めちゃめちゃ憎たらしい顔で舌を出した。私も対抗して、ヤツよりもっと憎たらしい顔で舌を出した。ヤツは負けずに、最上級の憎たらしい顔をした。
とっさにそれ以上の憎たらしい顔が思いつかなくてまごついてたら、ヤツは「ざまあみろ」の顔をしてソッポを向いた。
くやしいー。でも、あの憎たらしい顔、どこかで見たような気がする……あ、あれだー。
私がまだ新潟のおばあちゃんちにいたころ、おなじ小学校で仲のいい、ジュンくんって男の子と裏山に登ったことがあるの。私、その山のことよく知ってたから、一緒に探検しようって誘ったの。
私は「こんな秘密の場所も知ってるのよー」って威張りたかった。ジュンくんも「女の子になんか負けないぞー」って、その木はどこにでもあるもので大したものじゃないとか、その実はおじいちゃんのうちにいっぱい落ちてるとか強がってた。
私はどうしてもジュンくんにスゴイって言われたくて、ジュンくんはどうしても認めたくなくて、どんどんどんどん見たこともないような奥地にまで登って行ったの。
足もとはだんだん暗くなって、二人ともだんだん疲れてきて……五時のチャイムが聞こえたときにはもう、自分たちがどこにいるのかさえわからなくなってた。
ジュンくんが不安そうな顔で「もう、帰ろうよー」って言った。私は「いいよ」って答えた。もちろん帰り道なんてちっともわからなかったけど、強がってた手前、私は自信満々に歩きはじめた。道のない森のなかをぐるぐる。暗い森のなかをぐるぐる、ぐるぐる。
そのうち、ジュンくんが「この木、さっきも見たよおー……うえーん!」って泣きだした。青いビニールのヒモが枝に巻きつけられてた。
私が正直に、ここがどこなのかわからないって話したら、ジュンくんはよけい泣いちゃって「よく知ってるって言ってたじゃないかあー! やっちゃんのバカー! バカバカー! 僕はもう死んじゃうんだあー!」ってさけびだした。
私も「ジュンくんだって知ってるって言ってたじゃないー」って言い返したら「言ってないよ、そんなこと言ってないよおー」って。
幼心に私は、もうダメだなってあきらめた。遠く空を見ると、影絵みたいな林のあいだからまっ赤な夕焼けが見えた。めちゃめちゃキレイだった。
夕焼けのしたにはとなりの山が見えて、そのふもとから金色に揺らめく田んぼがずうーっと広がってた。田んぼのまんなかに、まっ赤な鉄塔が立ってた。
そのとき、ハッと気がついた。もしかしたら、あの鉄塔に向かってまっすぐ歩けば自分の知ってるところに出られるんじゃないかって。
私は泣きじゃくるジュンくんの手をひっぱってどんどん歩いてった。どんどんどんどん。泣いてしゃがみ込むジュンくんを立ちあがらせて、どんどんどんどん。
さんざん歩いてなんとか鉄塔にたどり着いたら、見たことのある人たちが私とジュンくんの名前を呼んでた。部落の人たちが総出で私たちを探してたの。私たちは一気に泣き声をあげてその人たちに走ってった。
その後、私はめちゃめちゃ怒られて、おばあちゃんと一緒にジュンくんのうちに謝りに行ったの。「ごめんくださーい」って言うと、おばさんが出てきて……
私が「ごめんなさい」ってペコリとしたとき、おばさんの陰からジュンくんがした顔、それがこの最上級の憎たらしい顔だった。
あいつがオーダーを終えて帰ってきた。イスに座るなり、体をひねってジーパンのポケットからタバコをとり出した。私は指にはさんだままの自分のタバコに気がついた。灰がゾウの鼻みたいだった。
「いくらだったー?」
「ん? ああ、いいよ」
「だーめ。いくらだったのー?」
私は財布からお金をとり出して、あいつに手わたした。
「ねえ、ママ! ジャニスにもあげていーい?」
あの男の子が大声で、すぐとなりにいるお母さんにさけんだ。ジャニスはたぶん犬の名前。お母さんは自分の料理を食べながら、冷静に答えた。
「ダメだよ。ジャニスは辛いもの食べられないんだから」
男の子はまだあきらめない。
「ねえ、なんでー! なーんーでー!」
「じゃあ、あんたもニンジン食べるの?」
男の子はすぐに話題を変えて、ジュースの入った大きなグラスにちっちゃな手をのばした。顔は憎たらしいけど、手はかわいい。
「あのね、きのう学校でね……」
ほんっと、よくしゃべるなあー。
私もあの男の子くらいのときはめちゃめちゃおしゃべりで、お母さんに「あんたは口から産まれたみたいな子だねえ」って言われてた。でも、そのころの私ってなにを話してたんだろう。いまでは思いつくことをぜんぶしゃべってもあの子ほどしゃべれないのに。どこに行っちゃったんだろう。どこからきてたんだろう。
あ、でも、そう言えば……
店員さんがやってきて、テーブルに並べはじめた。私のツナサンドとココア。あいつは……ローストビーフサンドとポテト、コーヒー。
「ねえBAKA、最近、書いてて思うんだけど……言葉ってどこからやってくるのかなあ?」
あいつはサンドを口いっぱいにほおばりながら視線を私に向けて、戻した。
「ううん、私から出てくるのはわかってるの。でもね、どんどんどんどん目のまえに文字があらわれるのを見てると、だんだん怖くなってきて」
あいつは口をいっぱいにしたままモグモグ答えた。
「徒、然、草?」
「小学校で習ったやつでしょ? うん、たぶんあんな感じ。最初のうちはうーんって考えながら書いてるんだけど、だんだん書いた後から考えるようになって、気がつくと考えることが追いつかなくなってるの。BAKAも音楽やってて、そうなることないー?」
あいつはコーヒーを口に流し込みながら、大きく二回うなずいた。
「あれって、なんなのかなあ?」
「反射、モグモグ、だよ、反射」
「ハ、ン、シャ?」
あいつはやっと飲み込んで、ちゃんとキレイに話せるようになった。
「反射って言うかさ、条件反射みたいな感じだと思うよ。例えばさ、熱いものに触ったときには考えるよりも先に手を引っ込めてる、みたいに、イメージが理性を通さずに直接言葉を出してるんだと思うよ」
「ふうーん……」
あいつはフォークにさしたポテトを口に入れようとして、やめた。
「……本当に分かってんの?」
私はココアを口にした。
「言ってることは、わかってるよ? ただー、共感できないだけー」
「んー……じゃあさ、GUUは自分が調子に乗ってしゃべりまくってるときに、いちいち頭の中で考えてからしゃべったりするか?」
「うーん……」
あの男の子がテーブルのしたで足をバタバタしてる。
「しなーい」
「それと同じなんだよ、GUUの言ってる状態は。ん、いや待てよー。考えるっていうのは、頭の中でしゃべるってことなのかー? だとしたら、なにが違うんだ? 冷静さ? いや、理性も自分自身を見ることができない……」
「ねえー、ちょっとー、BAKAの言ってること、なんとなくわかったからー」
「あ、ああ」
私はツナサンドを手にした。レタスと卵がどっさりトーストにはさまれてる。あいつはポテトを次々に食べた。
「じゃあー、それとは逆でー、ちいーっとも書けないときがあるのは、どうしてなのー?」
となりのテーブルの犬……確かジャニス、が、長い毛のあいだからちらっと私を見た。
「お、なかなかいい質問するじゃん。それはねー、GUUが『書かなくちゃー』と思うGUUになって、実際に書くGUUを外化してしまうからなんだよ。そうだなあ……例えば、街を歩いてて奇麗な女……いや、カッコいい男、か……とすれ違うときに、自分の歩き方を妙に意識しちゃって、うまく歩けなくなったりするだろ? それは、歩く自分を外化してしまったからなんだよ」
「そんなふうにならないけど」
あいつはサンドの残りを食べようとして、またやめた。
「……ま、まぁー、要するに、自分の位置の問題なんだよ」
「なあに、それ?」
「あー……本当の自分って、知ってる?」
「ほんとの、自分?」
私はタバコに火をつけた。
「そう。本当の自分の周りにはさ、イメージを作る部分とか、言葉を作る部分とか、感情を作る部分とか、いろいろな部分の自分があって……あ、もちろんそれは全部自分なんだけど、なんて言うかその、自分の中の自分って言うかさ……」
私は煙をはいた。
「自分のなかの自分?」
「そうそう。人間ってさ、イメージとか感情とか理性とか欲求とか、指令を出すところが増え過ぎちゃってるんだよ。でもさ、それを一つにする必要があって、その一つにする部分が本当の自分って言うかさ。もし本当の自分が一つしかないとするなら、だけどね」
そう言うと、あいつはサンドの残りをぜんぶ口に入れた。
「……なに言ってるか、ぜーんぜんわからない」
「俺も自分で言っててよく分からないんで、す、け、ど、ね」
タバコを吸いながら、あいつの言葉を頭のなかでくり返してみた。だんだんぐちゃぐちゃになってきた。
「それでー……あー! その自分はなんなのー?」
「なんなの、って……さあー?」
あいつはのんきにコーヒーなんか飲んでる。
「さあー、じゃないでしょー? イライラー! ちゃんと責任とってはっきりさせてよー!」
「うーん……じゃあー、切り替えスイッチ。外から入ってきたり自分の中で発生した刺激に対して、理性とか欲求とか感情とかの指令系の中で一番強く反応した部分の自分に従って体なりなんなりを使って対抗するように切り替えるスイッチ、とでもしとこう」
「じゃあ今話してるこの私はどの私なのー?」
「耳から入ってくる言語刺激によって発生したイメージに対して経験の中の理性で処理し切れないことから起こる不安定な感情を解消するべく経験の中の言葉と体の動きを使用させるスイッチを入れた、その部分のGUU」
「きゃー!」
さけんだらスッキリした。あやうくバカがうつるとこだった。まわりのテーブルから違う意味でアツイ視線を感じるけど。
「人間は分からないものが怖いからなー。だからそれが分かったり分かったつもりになったときにはむちゃくちゃ気持ちよくなるんだよ。まあ、そうじゃなくても、分からなくていいや、とか、それはそういうもんなんだ、とか思えば怖くはなくなるんだけどな」
「うん、わからなくていい」
私はタバコを吸った。
「そ、そうねえー。まあ、でも、考えたり感じたりしてこそ自分なんだから、ほんとの自分は自分じゃないとも言えるんだけど……」
「それで、」私は煙をはいた。「言葉ってどこからやってくることになったのー?」
「だ、か、らー、経験、感情、イメージ、理性、その他諸々の指令系の部分のGUUが言葉に変換する部分のGUUと結びついて発生するものなんだよー。GUUが怖くなったってのは、理性じゃない部分から言葉が出てたことに対して『言葉は理性だけから出る』っていう偏見がびっくりしただけのことー。言葉はさ、理性以外からも出るんだよ。だから自分が発した言葉に自分が考えさせられるってことが起きるんだよ」
「もういいよー」
私はタバコを消した。灰皿にはさっき吸ってた吸い殻が転がってる。私は新しい吸い殻をその吸い殻に寄りそわせて、おいた。残りのツナサンドを手にした。
「……でも、もしかして、BAKAはバカじゃないのー?」
「え? いや……スミマセン、実は全てデタラメでした……そう言うことによって、私は責任から逃れたいと思います」
あいつは自分のお皿に残ったポテトをつつきだした。
「まぁ、全ての言葉はGUUから出てくるけど、それは経験からも出てるわけで……だけど経験ってのは、例えば人から聞いた言葉をそのまま出したら純粋な自分だって言い切れないわけで……いや、待てよ。自分で自分を見ることができるのって理性だけじゃないのか? もしかして理性って自分じゃない?? 理性は社会??? じゃあ今考えてる自分ってなに? パラダイムの中で生きる特殊……」
私はツナサンドを飲み込んで、手についたカスをお皿に払い落とした。
「バーーーカ。やっぱりバカだ」
となりのテーブルにいた、あの男の子とそのお母さんとその飼い犬は、いつのまにか女の子三人のグループになってた。ココアを飲みながら、私は振り返った。
空いてるテーブルがのほうが多いくらい。お店はガラガラ。アフロの店員さんは、カウンターの向こうでおしゃべりしてる。カベにかかったまるい時計が動いてる。
「もう、三時だよ」
あいつはタバコに火をつけてた。
「え、もーお? ああー、こうして休日は何事もなくいつの間にか過ぎて行くのだー。休日とは一体なにを休む日なのか。それは仕事、シゴト、しごと?」
食べ終わったお皿に残ったマヨネーズ混じりの水のなかに、フォークのカーブが沈んでる。ココアとコーヒーのあいだでは、プラスチックの灰皿がくすぶってる。
あいつのタバコの煙をくぐり抜けて、となりのテーブルの女の子たちが出て行った。お店のまえの駒沢通りをいろんな車が横切ってく。そのたびに窓に反射する光が、ここから見えない太陽の高さをとぎれとぎれに教えてくれる。
「ねえ、サンダル見に行かない? 私ね、ヒールが高くって、まっ赤で、かわいいーサンダルがほしいの。黒でもいいかなあ。とにかく、いろいろ見たいの」
「んじゃあ、行きましょうか」
あいつはタバコを灰皿でもみ消して、私はバッグを肩に立ちあがる。お店を出て、ゆるやかにのぼる坂道を、あいつと手をつないで歩く。鮮やかな街路樹の緑。見あげると、遥かに遠い空の青。続く、続く。
あー、ずうーっとこのままがいいなー。ぽかぽかのなか、手をつないで、いつまでも歩いて歩いて。ゆっくりゆっくり、惜しむように。
「お」
あいつが急に立ちどまった。
「サンダルの、ま、え、にー」
あいつが指差すのは、二人のお気に入りの雑貨屋さん。名前はジョリ・ジョリ。
お店のまえには赤、白、黄色のパイプチェアーが重ねられ、その手前にはテーブルクロスやエプロンの入ったバケツが並んでる。
「いいよー」
黄色地に青の線が入ったテーブルクロスを広げてみると、お店の奥から声がした。
「あー! YASUKOちゃん! SATOSHIくーん!」
走って出てきたのは、AKIさんだった。
「あー、AーKIーさあーん!」
AKIさんはこのお店で働いてる友達。いつもは日曜日がお休みの日なんだけど、エプロンをしてるところを見ると今日は違うみたい。
「AKIさん、どうしたのー? 今日はお休みじゃないのー?」
「うん、カゼひいちゃった子がいて、代わりなのー。元気ー?」
「げんきー」
AKIさんは、見た目はめちゃめちゃクールなのに、しゃべるとめちゃめちゃかわいいの。はじめてAKIさんと話す人は、必ずそのギャップに驚いて「AKIさんはしゃべらないほうがいいねー」って言うくらい。でも、見た目も中身もカッコいい人って、実際はあんまりいない。
「AKIさん、商品入れ替えしたの?」
あいつがお店をのぞいて言った。
「うん、おとといねー。ねえ、それよりYASUKOちゃん、プーやってるんだってー?」
「うん、先週までねー」
「え、なになにー、今度はどこで働いてるのー?」
「あのねー」
「GUU、今、小説書いてるんだよ」
「えー! 小説ー?」
通りすがりの人たちがみんな私たちを見てく。あいつのカッコよさとAKIさんのクールさ、それよりなにより私のかわいさが、人目を引いて離さない……にチガイない。
「ねえねえ、どんなの書いてるのー? 恋愛? サスペンス? それともSF? まさかー、推理小説ー?」
「うんとねー」
「全然そんなんじゃなくて、なんか、日記みたいなやつだよ」
「え、じゃあじゃあ今日のことも書くー? 私も登場するー?」
「うん」
「きゃー! じゃあもっとカッコよくしゃべらなきゃー!」
お店の奥から女の子の声がした。
「AKIちゃーん! レジお願ーい!」
「あ、行かなきゃー。あとでねー!」
水色のTシャツにジーパン。アップにした茶色い髪を揺らしながら、AKIさんの後ろ姿が走ってく。
「ほんっと、よく喋るなあー」
「でもねー、AKIさん、いま思春期なんだよー」
私たちはお店に入った。
「どういうこと?」
「MANABUさんとシュラバ中なんだってー」
「修羅場って、どんな?」
「夜毎、カサのトガったほうを相手に向けてたたかってるらしいよー」
「ふうーん。日本にも、しかもこんな身近なところにも、眠れない場所ってあったんだねえー」
そう言いながら、あいつはマグカップを手にとった。
「うちも、ALのおかげで大変だよ」
このあいだ、ALがいたずらしてマグカップを三つも割った。だれかが遊びにきたら足りないから、買わなくちゃいけない。
「楽しんでるくせにー」
「そんなこと、あるよー」
あいつが手にしたのはイタリア製のシンプルなマグカップ。外は山吹色、中は白。口のところはモスグリーン。
私が手にしたのはフランス製のシェイプしたマグカップ。外も中も赤。口のところが青。とっ手に二つ、穴が開いてる。
あいつは私のマグカップを、私はあいつのを見る。見比べて、目をあわせて、見比べる。あいつは自分のマグカップのほうがかわいいって目で訴えてる。
「なあにー、言いたいことがあるならちゃんと口で言いなさい?」
あいつは口をとがらせて、まだ目で訴える。私はわからない振りをしてあげる。
「なんなの? 言葉はどうしたの? なくしちゃったの?」
あいつは大きく二回うなずいた。私はわざと大きなため息をついてあげる。
「なくしちゃったんならしかたないわね。私のに決まり」
あいつは大きく二回首を横に振った。
「悪いひと。言葉を話せない振りしてたのね」
あいつは一段と口をとがらせて、首をまた横に振った。
「私には聞こえるのよ、あなたの声が、そのしぐさから」
「……マリアンヌ、君は僕を知っていると言い、すぐさま知らないと言う。君は僕に触れながら、遥か彼方にいると言う」
「いいえフェルディナン。あなたの目からは言葉が聞こえなかった、ただそれだけだわ」
「ああ。言葉、いや、表現は発信と受信の両者が互いにイメージに働きかけなければ成立しないものだ。僕たちを分け隔てているものは、なんだ?」
「きっと……愛、よ」
「愛が二人を結びつけ、そして隔てている……」
「そう。空の青と私とのあいだには『空の青』があるわ。だから、もう、行かなくちゃ」
「あ、あ、あ、ちょ、ちょっと」
あいつは手をのばして私をとめた。
「なあに?」
「あ……結局、GUUのマグカップに……すんの?」
私ははっきりうなずいた。
「いやー、こっちの方がいいって。だってさ、これのほうが……ほら、コーヒーの色に合ってるしさ、それに……」
あいつの説明がえんえんと続く。マジメに聞いてると、だんだんめんどくさくなってくる。奥に見える棚がだんだん気になってくる。
棚のいちばんうえの段に、大きなサラダボウルが重ねられておかれてる。ガラス製、木製、プラスチック製。そのとなりは……あー、もう。あいつの顔がじゃまで見えない。
「……だからね、こっちのほうが……」
「いいよ、それで」
「え?」
「BAKAのやつにしよ?」
「いや、あの、ちょ、ちょっと待ってよ。そう言われるとGUUのやつがいいかなーなんて思ったりして」
「なあにー? どっちなのー?」
「い、いやあー……そっち」
ほんとにバカだ。
混雑するお店をぐるぐる回りつくしたころ、あいつの持つ買い物カゴはいっぱいになってた。
うちに二個目のワインオプナー、コーヒーの木、木製のサラダボウル、新しいALの遠出用のカゴ、ローソク、麻の人形。結局、マグカップは二つ買うことになった。
レジにできた行列の向こうで、AKIさんはいっしょうけんめい会計してる。私たちは行列に並びながら、カウンターに並べられたおもちゃで遊ぶ。
変装グッズ、アメリカンクラッカー、動かすと交尾するサルのキーホルダー。あいつは何度も何度も交尾させて、めちゃめちゃうれしそうにはしゃいでる。
「うれしいのー?」
あいつは笑顔でうなずく。
「よかったねー」
大きくうなずく。
私たちの番がきて、AKIさんはちょっとほっとした顔をした。ヒタイが汗で少し光ってる。もう一人の店員の女の子は棚のものを整理したり新しく並べたりしてる。タイヘンだー。
レジを打ちながら、AKIさんは他のお客さんに聞こえないようにささやいた。
「安くしとくねー」
「ありがとー」
私たちも小声で答える。お金を払って黄色い袋に入れてもらう。
「YASUKOちゃん、こんど電話するね」
「うん」
「AKIさん、がんばってね」
AKIさんは小さくうなずいた。
「じゃあ、またねー」
AKIさんの振る手が、次のお客さんの背中で見えなくなった。行列は続いてる。
「AKIさん、かわいそう」
「日曜だからねえ」
「ちがうよー。日曜はなんにもわるくな、い……」
振り返ると、町は金色の光だった。ビルも道も街路樹も看板も車も人も、あいつも私の体も。坂の頂上にあるまぶしい光を手でさえぎると、ビーズのブレスレットが一瞬きらめいた。
「GUU、これー、結構重いよー」
あいつは荷物を逆の手に持ちかえた。
「帰るー?」
「う、うん。そうしてしまおう」
私の頭にサンダルがよぎった。でも、しかたないかあー……ん? あー!
「ねえ見てー!」
道路をはさんで向こう側のお店のウインドウに、カッコいいロングドレスが飾られてる。
ワインレッドで、ソデがなくて、胸が深く開いてて、長いスリットが入ってて、シルエットがめちゃめちゃカッコいい。
「ちょっと見ていいー?」
「たぶん、むちゃくちゃ高いよー?」
「いーいーかーらー」
道路をわたって近くで見ると、大きな花柄が薄く入ってる。私がこのドレスを着てる姿を想像してみた。きゃー。カッコいいー。
「やっぱり、高いねえー」
「決めた。私、ノーベル文学賞の授賞式はこれを着てあいさつする。だから、それまでだれにも買われないで待っててねー」
「それまでって、いつだ?」
あいつは両手で荷物を持ってまぶしそうにしてる。
「夏、かなあー」
「……夏、ねえー」
坂をくだる私たちの先に、足長な私たちの影が歩いてる。両手を広げてみる。翼に羽のない鳥になった。あいつも荷物を持ったまま翼を広げる。オモリを縛りつけられた翼。
ふらふら左右に走る。二羽の飛べない鳥の助走。羽のない身重な鳥。スピードがあがる。金色の歩道。まっ黒な影。
「ねえ! 言葉って、なんなのー!」
「もやもやを閉じ込めた、鍵付きの宝箱!」
カーブの終わりで息をきらす。あきらめる。
「音楽も? 写真も? 絵も? 映画も? 服も? 化粧も? 料理も? ケーキも?」
「そう。みんな、そう」
遠回りしてビルの谷間を歩いてく。日陰のツタの細道。放置されてサビついた自転車の陰から汚れたノラ猫が私を見てた。枯葉色のこのカベにも、少しずつ緑が戻ってきてる。耐えられなくなってしゃがみこむと、頭上に青とも黒とも言えない細い空が見えた。
あいつは言った。
「人は生かされ、生きさせられているんだ」
私はノラ猫を見つめながら、今夜のことを考える。
ソウルミュージックに包まれながら、あいつとALと三人で、ゆっくり話して、ゆっくり黙って、ゆっくり見つめあったら、ゆっくり抱きあって、ゆっくりキスして、ゆっくり眠る。
だって、それが「休日」でしょ?
私はいま、まっ赤なソファーに寝転びながらワープロに向かってる。ときどき足をバタつかせながら、あなたが読んでるこの小説を書いてる。パキラの新芽を横目で見ながら、私のかわいい五本の指が踊るように……動いたらいいのに。
私がいま向かってるのは、ワ、タ、シ、の、黄色いノート型ワープロ。先月の終わりにあいつが約束どおり買ってくれた、かわいいーワープロ。まっ赤なソファーにのせても青いローテーブルにのせてもぴったり。どこにのせてもぴったり。もー、ほんと、めっちゃめちゃかわいいーの。
でもね、最初は黄色じゃなくて黒だった。あいつといろいろ電器屋さんを回ってみたんだけど、どこに行っても黒かグレーのワープロしかなくて、私、どーしても黄色のじゃなきゃ嫌だったから、あいつにぬってもらったの。
その日はもう一日中うれしくてうれしくて、画面を開いたり閉じたりするだけで「きゃー」ってさけんでた。ALも一緒に「にゃー」ってさけんでた。あいつも「うるさーい、早く書けー」ってさけんでた。
いまも抱きしめたくてウズウズしてるけど、書くほうが優先。文豪はキビシイのだ。
「にゃー」
となりでALがボールペンにじゃれてる。白くて太いボールペン。あたまにゴムでできたアマガエルがくっついてて、ノックするたびに「ゲーコ」ってなく。
このカエルがはじめて家にやってきたとき、ALはソファーの陰に隠れて、じっとこの得体の知れない緑色のものの様子をうかがってた。
「なんだあ、あいつはー?」
いつまでもピクリとも動かないカエルの目をさけて、後ろからゆっくり近づく。かるくつついて逃げる。つついて逃げる。それを何度もくり返して、やっとALはカエルと仲良しになった。
いまでは頭にかみつくほどの愛しよう。愛されすぎてカエルはボロボロ。一時は手も足もちぎれたけど、私のブラックジャックのテクニックで治してあげた。今でもその手術の跡(ホチキスの針)が残ってる。
「ふあーあーあー」
あいつがとなりの部屋から起きてきた。
「あれ、GUU、どうしたの? こんなに早く起き……お? もしかして、仕事中?」
「そう。いま、い、そ、が、し、い、の」
「へえー! どれ、ちょっと見せてよ」
私は起きあがって、となりに座ったあいつにワープロを手わたした。タバコに火をつけた。あいつの横顔。はれぼったい真剣な目。
「結構、書いたねー」
「うん」
ローテーブルには、いっぱいになった灰皿と私の黄色いマグカップがのってる。マグカップからは湯気がのびてる。さっきいれたばかりのコーヒー。
「でもこれ、ほんとそのまんまだなー。日記みたい」
あいつは読みながら私のマグカップに手をのばした。
「あ、これ……この間俺に『あのときなんて言ってたー?』って聞いたの、この部分を書くためだったのかー?」
「うん」
あいつはカチャカチャとページをめくっていく。
「でもこれ、マズイんじゃなーい?」
あいつはコーヒーをすすった。
「どうしてー?」
「だってさ、俺は……俺は構わないけどさ、KIDOくんとかおばさんとかには許可をもらわないと、プライバシーの問題とか、いろいろあるんじゃないの?」
私は煙をはき出す。
「だ、い、じょーぶ」
「そうかぁ? まあ、確かにだめとは言わないだろうけどさー。でも、自分のこと書かれるのって、あんまり気持ちのいいもんじゃないと思うよー?」
「だって……二人をぬかしちゃったら話にならないじゃない」
あいつはコーヒーをローテーブルにおいた。
「いや、なにもドキュメントにする必要ないじゃん」
「なにそれー。このまえは『ありのままの自分を書け』とかなんとか言ってたじゃなーい」
「それはそういう意味じゃなくてさ、なんて言ったらいいかなぁ……そのー……外的事実じゃなくて、内的事実って言うか、そういう意味だよー」
ALはカエルのボールペンに飽きて毛づくろいしてる。
「ナイテキジジツ、って?」
「それは、そのー……なんて言うか、感じたり考えたりしたそのものって言うか、実際目の前にあるものじゃなくてさ……」
「だったら、写真はガイテキジジツじゃないの? 音楽だって実際に楽器から出る音でレコーディングするんでしょー?」
「いや、それを言ったら小説だって、実際にある紙と文字だろ? そうじゃなくてさ……」
私は灰皿に灰を落とした。
「と、に、か、く、これでいいのー。プライバシーとかなんとか言う人のことなんて書くつもりないし」
「ま、まあーいいんだけどね、なんでも」
開け放してた窓からさわやかな風が流れ込んだ。振り返った私の顔いっぱいに、まっ青な空が差し込んだ。向かいのアパートのベランダでは洗濯物がたくさん干されてる。
「BAKA、いい天気だねー」
窓にヒジをついて、タバコの煙を空に吹きかけた。空と私の汚れはあたたかな風にやさしくとけた。
今日は久しぶりの二人っきりの休日。私は小説家の特権でいつでも休日にできるけど、あいつは日曜日だけ。
あーあ、早く二人でラクラク印税生活がしたいなー。そしたら毎日休みにするのに。
見おろすと、幼稚園の制服を着たちっちゃい男の子と女の子がしゃがみ込んでる。二つの黄色いボウシが動いてる。となりの庭で、なにかいじってる。
「ねえ、お昼どうするー?」
「ん? そうだなー、ガゼボにでも行くかー」
そうか、春がきたんだー。
「うん」
あいつは立ちあがってのびをすると、となりの部屋に着替えに行った。私はタバコを消した。ソファーには私の黄色いワープロがちょこんと残されてる。開いたままの青白い画面には、ぎっしり文字が並んでる。
スイッチを切って画面を閉じると、ALが私を見あげてた。かわいい緑色の目。
「ALー、今日はBAKAと二人っきりでデートなのー。いいでしょー。だから、ALはうちでお留守番だよー?」
「にゃー」
「どーしてそんなうれしそうな顔するのー? 一人ぼっちになるのがそんなにうれしいのー?」
「にゃー」
「GUUの顔は見飽きたってさ」
あいつが着替えて部屋から出てきた。
「そーなの、AL?」
「にゃー」
「にゃー? ひどいなあー」
「ALだって、たまには一人になりたいよなー?」
「にゃー」
あいつはALを抱きあげてキスした。今度は私がしたくする番。
「ALのバーカ」
となりの部屋に行ってクローゼットを開く。少し迷ってから黒いパンツとセーターをとり出す。着替える。鏡をのぞき込む。今日もくるくるスパイラル。
まゆげを書いて、まつ毛をくるんとカール。マスカラ。ファンデーションと口紅を薄く薄く。
「まだー?」と聞こえるあいつの声を聞き流してマニキュアのキャップを回す。今日はぴかぴかシルバーにする。ツメのつけねから先端へ。フーフー。ムラなくぬって、フーフーフー。
疲れたー。
ベッドに倒れ込んでタバコに火をつける。鏡にはタバコをくわえて横になる私の姿がうつってる。
あーあ、私がもおーっとかわいかったらなあ。
私、横顔がサルみたいなの。したに行けば行くほど「あれれれ?」って盛りあがる。口はデカイしソバカスもある。いまはそうでもないけど、私、ちっちゃいころ、自分のソバカスが大嫌いだった。
それで小学校六年生くらいのとき、お母さんに「一生のお願い! 私、どーしてもほしいものがあるのー」ってたのみこんで、それまでちょっとずつためてた貯金をぜーんぶおろして、ソバカスの消える化粧水を買ったの。私の一大決心。
でも、ちーっとも、消えなかった。おつかいとかお手伝いとかしていっしょうけんめいためた貯金が一瞬にしてなくなって、自分のソバカスはちっとも消えなくて、あまりの悔しさに「お母さあーん!」ってジタバタしながら泣きわめいたの。
お母さんはとなりでジタバタしてる私を横目に、洗濯物をたたみながら「大人になったら消えるわよ」って慰めてくれた。
この年になって、確かに少しは薄くなったけど、それはあのころよりも日にあたらなくなったからだと思う。あのころは毎日、学校が終わってから日が沈むまでずうっと外で遊んでて、つねに日焼けしてる子だったから。
「なあ、まだー?」
あいつが顔をのぞかせた。
「ねえBAKA……私って、かわいい?」
「な? なんだよ急に」
あいつは部屋に入ると、寝転ぶ私のそばにきて座った。私はタバコを灰皿においた。
「どーなの?」
「か、かわいいよ、もちろん」
「どこがー?」
「どこが、って……そのー……くるくるのでかい頭も好きだしー、そのー、目とか唇の形とか……」
うえを見あげていっしょうけんめい話すあいつ。
「鼻は? 耳は? 手は? 胸は? お尻は?」
「い、いいねー」
「好き?」
「好きって言うか……愛、し、て、る」
「きゃー」
私はあいつに抱きついた。
「サルみたいなのにー?」
「俺、サル顔、好きだよ。GUUみたいな強面のサル顔が」
「きゃー」
よかったー。お父さん、お母さん、サル顔に産んでくれてありがとう。
……でも、コワモテ?
「ところで腹へってんだけど……まだ?」
ウデをあいつの首に交差させたまま、両手のツメを見てみた。もう大丈夫みたい。
あいつの背中越しにストラトキャスターってギターが見える。窓際にはキーボードがおかれてる。キーボードの横のデスクには楽譜とか、わからない黒い機械とかがごちゃごちゃしてる。
「ねえ、いい曲できたー?」
「ん? ま、あ、ね」
あいつの声が体に響く。
「じゃあ、そろそろワールドツアー?」
「ん? んー……ま、まあねえー」
「きゃー!」
あいつをぎゅっと抱きしめた。
「んー……それより、GUUが早く作家デビューできたらいいねー」
灰皿からタバコの煙がのびてる。私はまた寝転んでタバコを手にした。
「私は大、丈、夫。MICROMANCEでいきなり新人賞をとってー、それで……えーっと、ア、ク、タ、ガ、ワ、賞(?)、ついでにノーベル文学賞までとっちゃうの。『日本文学界に、驚異の天才アラワル!』って大騒ぎになって、うちのまえにマスコミの人がいーっぱいやってくるの。『ヒトコトお願いします、ヒトコト!』ってうるさいから、しかたなくキレイなドレスに着替えて外に出ると、なぜかお父さんとお母さんがいて『やっちゃんガンバレー』って手を振ってるの。私も手を振り返そうとするんだけど、ハッと気づいて手をひっ込めるの。あー、私はもう偉大なカリスマなんだから、イゲンを……」
「……さ、行こうか」
私はタバコを吸った。
「なあにー、ウソじゃないよー? 『知ってるつもり』から出演依頼がきたら、BAKAとALも一緒に出るんだよー?」
「はいはい」
「返事は一回」
「はーい」
私はタバコを消した。
「よくできました。それじゃあ行きましょう」
「はーい」
ALに見送られて玄関を出た。
気持ちいいなー。空気に色がついてるみたいに青い空。手をのばしたら染まりそう。イチョウの並木にびっしり開いたちっちゃな葉っぱが、さわやかな風にザワザワ揺れてる。太陽の光をいっぱいあびてまぶしいくらいに黄緑色に光ってる。
向こうに行列ができてる。チョコレート色のアパートの一階。クリーニング屋さん。そのうえの階のモスグリーンのベランダでは洗濯物がはためいてる。行列を通り過ぎるとき、おじさんが忙しそうに受け付けしてるのが見えた。
このおじさんはいつもは怖い顔してるけど、話しかけるとめちゃめちゃかわいい顔でニコニコ笑う。人と話すのが苦手で、必要以上にニコニコして疲れちゃうから、反動で普段怖い顔になっちゃうんだよってあいつが言ってた。
あいつと手をつないで山手通りを歩く。まっ青な空が遠くまで広い。楽しいなー。あいつも笑ってる。
「もうそろそろ桜が咲くんじゃないかなー」
「お花見しようねー」
駒沢通りとの交差点。自動販売機。横断歩道を左に曲がる。私の苦手な立体交差の橋が迫る。どんどん迫る。どんどん、どんどん。もうダメだー。私はあいつの手にしっかりつかまる。
「ん? ああ、GUUは橋がだめなんだっけ」
「ほんっっと、ダメ。私のとこだけヒューって落ちそうで」
「それって、体重が……いや……」
駒沢通りのカーブにそってゆるやかな坂をのぼりきると、ガゼボが見えた。アウトレットを恵比寿の方に越えて二十メートルくらいのところ。
ガゼボはオープンテラスのカフェ。まっ白なカベ、クリーム色のタイルの床。まるいテーブルとイスが店じゅうに並べられてる。
「込んでるなー」
短い行列のできたカウンターの向こうで、アフロの男の子がヒジをつきながらオーダーをとってる。グリーンのTシャツにデニムのエプロン。
「なんにする?」
あいつはメニューをとって見せてくれた。
「私は、ツナサンドと……ココア」
「じゃあ俺頼んどくから、GUUは先に席取っててよ」
見ると、入口近くのテーブルがあいてた。涼しそうな席。
「わかったー」
後ろに並ぶ女の子たちのすきまを通ってテーブルにつく。イスを引いたらガタガタなった。バッグからタバコをとり出して一息つく。テーブルにはシュガーポットとプラスチックの灰皿がおいてある。タバコの灰を落とそうとすると、となりのテーブルからアツイ視線を感じた。
これって! もしかして、私、モテモテ? きゃー! めちゃめちゃカッコいい人だったらどうしよう!
カッコよくタバコの煙をはき出しながらチラっと見たら、小学校一年生くらいの、わんぱくそうな男の子がフォークをくわえながら私をじいっと見てた。
なあーんだ。ガッカリ。
男の子のとなりには、ニットキャップをかぶったカッコいい女の人が座ってる。たぶんお母さん。さらにそのとなりのイスには、ちっちゃくて毛の長い犬がきちんと座ってる。
男の子は私と目があうと、めちゃめちゃ憎たらしい顔で舌を出した。私も対抗して、ヤツよりもっと憎たらしい顔で舌を出した。ヤツは負けずに、最上級の憎たらしい顔をした。
とっさにそれ以上の憎たらしい顔が思いつかなくてまごついてたら、ヤツは「ざまあみろ」の顔をしてソッポを向いた。
くやしいー。でも、あの憎たらしい顔、どこかで見たような気がする……あ、あれだー。
私がまだ新潟のおばあちゃんちにいたころ、おなじ小学校で仲のいい、ジュンくんって男の子と裏山に登ったことがあるの。私、その山のことよく知ってたから、一緒に探検しようって誘ったの。
私は「こんな秘密の場所も知ってるのよー」って威張りたかった。ジュンくんも「女の子になんか負けないぞー」って、その木はどこにでもあるもので大したものじゃないとか、その実はおじいちゃんのうちにいっぱい落ちてるとか強がってた。
私はどうしてもジュンくんにスゴイって言われたくて、ジュンくんはどうしても認めたくなくて、どんどんどんどん見たこともないような奥地にまで登って行ったの。
足もとはだんだん暗くなって、二人ともだんだん疲れてきて……五時のチャイムが聞こえたときにはもう、自分たちがどこにいるのかさえわからなくなってた。
ジュンくんが不安そうな顔で「もう、帰ろうよー」って言った。私は「いいよ」って答えた。もちろん帰り道なんてちっともわからなかったけど、強がってた手前、私は自信満々に歩きはじめた。道のない森のなかをぐるぐる。暗い森のなかをぐるぐる、ぐるぐる。
そのうち、ジュンくんが「この木、さっきも見たよおー……うえーん!」って泣きだした。青いビニールのヒモが枝に巻きつけられてた。
私が正直に、ここがどこなのかわからないって話したら、ジュンくんはよけい泣いちゃって「よく知ってるって言ってたじゃないかあー! やっちゃんのバカー! バカバカー! 僕はもう死んじゃうんだあー!」ってさけびだした。
私も「ジュンくんだって知ってるって言ってたじゃないー」って言い返したら「言ってないよ、そんなこと言ってないよおー」って。
幼心に私は、もうダメだなってあきらめた。遠く空を見ると、影絵みたいな林のあいだからまっ赤な夕焼けが見えた。めちゃめちゃキレイだった。
夕焼けのしたにはとなりの山が見えて、そのふもとから金色に揺らめく田んぼがずうーっと広がってた。田んぼのまんなかに、まっ赤な鉄塔が立ってた。
そのとき、ハッと気がついた。もしかしたら、あの鉄塔に向かってまっすぐ歩けば自分の知ってるところに出られるんじゃないかって。
私は泣きじゃくるジュンくんの手をひっぱってどんどん歩いてった。どんどんどんどん。泣いてしゃがみ込むジュンくんを立ちあがらせて、どんどんどんどん。
さんざん歩いてなんとか鉄塔にたどり着いたら、見たことのある人たちが私とジュンくんの名前を呼んでた。部落の人たちが総出で私たちを探してたの。私たちは一気に泣き声をあげてその人たちに走ってった。
その後、私はめちゃめちゃ怒られて、おばあちゃんと一緒にジュンくんのうちに謝りに行ったの。「ごめんくださーい」って言うと、おばさんが出てきて……
私が「ごめんなさい」ってペコリとしたとき、おばさんの陰からジュンくんがした顔、それがこの最上級の憎たらしい顔だった。
あいつがオーダーを終えて帰ってきた。イスに座るなり、体をひねってジーパンのポケットからタバコをとり出した。私は指にはさんだままの自分のタバコに気がついた。灰がゾウの鼻みたいだった。
「いくらだったー?」
「ん? ああ、いいよ」
「だーめ。いくらだったのー?」
私は財布からお金をとり出して、あいつに手わたした。
「ねえ、ママ! ジャニスにもあげていーい?」
あの男の子が大声で、すぐとなりにいるお母さんにさけんだ。ジャニスはたぶん犬の名前。お母さんは自分の料理を食べながら、冷静に答えた。
「ダメだよ。ジャニスは辛いもの食べられないんだから」
男の子はまだあきらめない。
「ねえ、なんでー! なーんーでー!」
「じゃあ、あんたもニンジン食べるの?」
男の子はすぐに話題を変えて、ジュースの入った大きなグラスにちっちゃな手をのばした。顔は憎たらしいけど、手はかわいい。
「あのね、きのう学校でね……」
ほんっと、よくしゃべるなあー。
私もあの男の子くらいのときはめちゃめちゃおしゃべりで、お母さんに「あんたは口から産まれたみたいな子だねえ」って言われてた。でも、そのころの私ってなにを話してたんだろう。いまでは思いつくことをぜんぶしゃべってもあの子ほどしゃべれないのに。どこに行っちゃったんだろう。どこからきてたんだろう。
あ、でも、そう言えば……
店員さんがやってきて、テーブルに並べはじめた。私のツナサンドとココア。あいつは……ローストビーフサンドとポテト、コーヒー。
「ねえBAKA、最近、書いてて思うんだけど……言葉ってどこからやってくるのかなあ?」
あいつはサンドを口いっぱいにほおばりながら視線を私に向けて、戻した。
「ううん、私から出てくるのはわかってるの。でもね、どんどんどんどん目のまえに文字があらわれるのを見てると、だんだん怖くなってきて」
あいつは口をいっぱいにしたままモグモグ答えた。
「徒、然、草?」
「小学校で習ったやつでしょ? うん、たぶんあんな感じ。最初のうちはうーんって考えながら書いてるんだけど、だんだん書いた後から考えるようになって、気がつくと考えることが追いつかなくなってるの。BAKAも音楽やってて、そうなることないー?」
あいつはコーヒーを口に流し込みながら、大きく二回うなずいた。
「あれって、なんなのかなあ?」
「反射、モグモグ、だよ、反射」
「ハ、ン、シャ?」
あいつはやっと飲み込んで、ちゃんとキレイに話せるようになった。
「反射って言うかさ、条件反射みたいな感じだと思うよ。例えばさ、熱いものに触ったときには考えるよりも先に手を引っ込めてる、みたいに、イメージが理性を通さずに直接言葉を出してるんだと思うよ」
「ふうーん……」
あいつはフォークにさしたポテトを口に入れようとして、やめた。
「……本当に分かってんの?」
私はココアを口にした。
「言ってることは、わかってるよ? ただー、共感できないだけー」
「んー……じゃあさ、GUUは自分が調子に乗ってしゃべりまくってるときに、いちいち頭の中で考えてからしゃべったりするか?」
「うーん……」
あの男の子がテーブルのしたで足をバタバタしてる。
「しなーい」
「それと同じなんだよ、GUUの言ってる状態は。ん、いや待てよー。考えるっていうのは、頭の中でしゃべるってことなのかー? だとしたら、なにが違うんだ? 冷静さ? いや、理性も自分自身を見ることができない……」
「ねえー、ちょっとー、BAKAの言ってること、なんとなくわかったからー」
「あ、ああ」
私はツナサンドを手にした。レタスと卵がどっさりトーストにはさまれてる。あいつはポテトを次々に食べた。
「じゃあー、それとは逆でー、ちいーっとも書けないときがあるのは、どうしてなのー?」
となりのテーブルの犬……確かジャニス、が、長い毛のあいだからちらっと私を見た。
「お、なかなかいい質問するじゃん。それはねー、GUUが『書かなくちゃー』と思うGUUになって、実際に書くGUUを外化してしまうからなんだよ。そうだなあ……例えば、街を歩いてて奇麗な女……いや、カッコいい男、か……とすれ違うときに、自分の歩き方を妙に意識しちゃって、うまく歩けなくなったりするだろ? それは、歩く自分を外化してしまったからなんだよ」
「そんなふうにならないけど」
あいつはサンドの残りを食べようとして、またやめた。
「……ま、まぁー、要するに、自分の位置の問題なんだよ」
「なあに、それ?」
「あー……本当の自分って、知ってる?」
「ほんとの、自分?」
私はタバコに火をつけた。
「そう。本当の自分の周りにはさ、イメージを作る部分とか、言葉を作る部分とか、感情を作る部分とか、いろいろな部分の自分があって……あ、もちろんそれは全部自分なんだけど、なんて言うかその、自分の中の自分って言うかさ……」
私は煙をはいた。
「自分のなかの自分?」
「そうそう。人間ってさ、イメージとか感情とか理性とか欲求とか、指令を出すところが増え過ぎちゃってるんだよ。でもさ、それを一つにする必要があって、その一つにする部分が本当の自分って言うかさ。もし本当の自分が一つしかないとするなら、だけどね」
そう言うと、あいつはサンドの残りをぜんぶ口に入れた。
「……なに言ってるか、ぜーんぜんわからない」
「俺も自分で言っててよく分からないんで、す、け、ど、ね」
タバコを吸いながら、あいつの言葉を頭のなかでくり返してみた。だんだんぐちゃぐちゃになってきた。
「それでー……あー! その自分はなんなのー?」
「なんなの、って……さあー?」
あいつはのんきにコーヒーなんか飲んでる。
「さあー、じゃないでしょー? イライラー! ちゃんと責任とってはっきりさせてよー!」
「うーん……じゃあー、切り替えスイッチ。外から入ってきたり自分の中で発生した刺激に対して、理性とか欲求とか感情とかの指令系の中で一番強く反応した部分の自分に従って体なりなんなりを使って対抗するように切り替えるスイッチ、とでもしとこう」
「じゃあ今話してるこの私はどの私なのー?」
「耳から入ってくる言語刺激によって発生したイメージに対して経験の中の理性で処理し切れないことから起こる不安定な感情を解消するべく経験の中の言葉と体の動きを使用させるスイッチを入れた、その部分のGUU」
「きゃー!」
さけんだらスッキリした。あやうくバカがうつるとこだった。まわりのテーブルから違う意味でアツイ視線を感じるけど。
「人間は分からないものが怖いからなー。だからそれが分かったり分かったつもりになったときにはむちゃくちゃ気持ちよくなるんだよ。まあ、そうじゃなくても、分からなくていいや、とか、それはそういうもんなんだ、とか思えば怖くはなくなるんだけどな」
「うん、わからなくていい」
私はタバコを吸った。
「そ、そうねえー。まあ、でも、考えたり感じたりしてこそ自分なんだから、ほんとの自分は自分じゃないとも言えるんだけど……」
「それで、」私は煙をはいた。「言葉ってどこからやってくることになったのー?」
「だ、か、らー、経験、感情、イメージ、理性、その他諸々の指令系の部分のGUUが言葉に変換する部分のGUUと結びついて発生するものなんだよー。GUUが怖くなったってのは、理性じゃない部分から言葉が出てたことに対して『言葉は理性だけから出る』っていう偏見がびっくりしただけのことー。言葉はさ、理性以外からも出るんだよ。だから自分が発した言葉に自分が考えさせられるってことが起きるんだよ」
「もういいよー」
私はタバコを消した。灰皿にはさっき吸ってた吸い殻が転がってる。私は新しい吸い殻をその吸い殻に寄りそわせて、おいた。残りのツナサンドを手にした。
「……でも、もしかして、BAKAはバカじゃないのー?」
「え? いや……スミマセン、実は全てデタラメでした……そう言うことによって、私は責任から逃れたいと思います」
あいつは自分のお皿に残ったポテトをつつきだした。
「まぁ、全ての言葉はGUUから出てくるけど、それは経験からも出てるわけで……だけど経験ってのは、例えば人から聞いた言葉をそのまま出したら純粋な自分だって言い切れないわけで……いや、待てよ。自分で自分を見ることができるのって理性だけじゃないのか? もしかして理性って自分じゃない?? 理性は社会??? じゃあ今考えてる自分ってなに? パラダイムの中で生きる特殊……」
私はツナサンドを飲み込んで、手についたカスをお皿に払い落とした。
「バーーーカ。やっぱりバカだ」
となりのテーブルにいた、あの男の子とそのお母さんとその飼い犬は、いつのまにか女の子三人のグループになってた。ココアを飲みながら、私は振り返った。
空いてるテーブルがのほうが多いくらい。お店はガラガラ。アフロの店員さんは、カウンターの向こうでおしゃべりしてる。カベにかかったまるい時計が動いてる。
「もう、三時だよ」
あいつはタバコに火をつけてた。
「え、もーお? ああー、こうして休日は何事もなくいつの間にか過ぎて行くのだー。休日とは一体なにを休む日なのか。それは仕事、シゴト、しごと?」
食べ終わったお皿に残ったマヨネーズ混じりの水のなかに、フォークのカーブが沈んでる。ココアとコーヒーのあいだでは、プラスチックの灰皿がくすぶってる。
あいつのタバコの煙をくぐり抜けて、となりのテーブルの女の子たちが出て行った。お店のまえの駒沢通りをいろんな車が横切ってく。そのたびに窓に反射する光が、ここから見えない太陽の高さをとぎれとぎれに教えてくれる。
「ねえ、サンダル見に行かない? 私ね、ヒールが高くって、まっ赤で、かわいいーサンダルがほしいの。黒でもいいかなあ。とにかく、いろいろ見たいの」
「んじゃあ、行きましょうか」
あいつはタバコを灰皿でもみ消して、私はバッグを肩に立ちあがる。お店を出て、ゆるやかにのぼる坂道を、あいつと手をつないで歩く。鮮やかな街路樹の緑。見あげると、遥かに遠い空の青。続く、続く。
あー、ずうーっとこのままがいいなー。ぽかぽかのなか、手をつないで、いつまでも歩いて歩いて。ゆっくりゆっくり、惜しむように。
「お」
あいつが急に立ちどまった。
「サンダルの、ま、え、にー」
あいつが指差すのは、二人のお気に入りの雑貨屋さん。名前はジョリ・ジョリ。
お店のまえには赤、白、黄色のパイプチェアーが重ねられ、その手前にはテーブルクロスやエプロンの入ったバケツが並んでる。
「いいよー」
黄色地に青の線が入ったテーブルクロスを広げてみると、お店の奥から声がした。
「あー! YASUKOちゃん! SATOSHIくーん!」
走って出てきたのは、AKIさんだった。
「あー、AーKIーさあーん!」
AKIさんはこのお店で働いてる友達。いつもは日曜日がお休みの日なんだけど、エプロンをしてるところを見ると今日は違うみたい。
「AKIさん、どうしたのー? 今日はお休みじゃないのー?」
「うん、カゼひいちゃった子がいて、代わりなのー。元気ー?」
「げんきー」
AKIさんは、見た目はめちゃめちゃクールなのに、しゃべるとめちゃめちゃかわいいの。はじめてAKIさんと話す人は、必ずそのギャップに驚いて「AKIさんはしゃべらないほうがいいねー」って言うくらい。でも、見た目も中身もカッコいい人って、実際はあんまりいない。
「AKIさん、商品入れ替えしたの?」
あいつがお店をのぞいて言った。
「うん、おとといねー。ねえ、それよりYASUKOちゃん、プーやってるんだってー?」
「うん、先週までねー」
「え、なになにー、今度はどこで働いてるのー?」
「あのねー」
「GUU、今、小説書いてるんだよ」
「えー! 小説ー?」
通りすがりの人たちがみんな私たちを見てく。あいつのカッコよさとAKIさんのクールさ、それよりなにより私のかわいさが、人目を引いて離さない……にチガイない。
「ねえねえ、どんなの書いてるのー? 恋愛? サスペンス? それともSF? まさかー、推理小説ー?」
「うんとねー」
「全然そんなんじゃなくて、なんか、日記みたいなやつだよ」
「え、じゃあじゃあ今日のことも書くー? 私も登場するー?」
「うん」
「きゃー! じゃあもっとカッコよくしゃべらなきゃー!」
お店の奥から女の子の声がした。
「AKIちゃーん! レジお願ーい!」
「あ、行かなきゃー。あとでねー!」
水色のTシャツにジーパン。アップにした茶色い髪を揺らしながら、AKIさんの後ろ姿が走ってく。
「ほんっと、よく喋るなあー」
「でもねー、AKIさん、いま思春期なんだよー」
私たちはお店に入った。
「どういうこと?」
「MANABUさんとシュラバ中なんだってー」
「修羅場って、どんな?」
「夜毎、カサのトガったほうを相手に向けてたたかってるらしいよー」
「ふうーん。日本にも、しかもこんな身近なところにも、眠れない場所ってあったんだねえー」
そう言いながら、あいつはマグカップを手にとった。
「うちも、ALのおかげで大変だよ」
このあいだ、ALがいたずらしてマグカップを三つも割った。だれかが遊びにきたら足りないから、買わなくちゃいけない。
「楽しんでるくせにー」
「そんなこと、あるよー」
あいつが手にしたのはイタリア製のシンプルなマグカップ。外は山吹色、中は白。口のところはモスグリーン。
私が手にしたのはフランス製のシェイプしたマグカップ。外も中も赤。口のところが青。とっ手に二つ、穴が開いてる。
あいつは私のマグカップを、私はあいつのを見る。見比べて、目をあわせて、見比べる。あいつは自分のマグカップのほうがかわいいって目で訴えてる。
「なあにー、言いたいことがあるならちゃんと口で言いなさい?」
あいつは口をとがらせて、まだ目で訴える。私はわからない振りをしてあげる。
「なんなの? 言葉はどうしたの? なくしちゃったの?」
あいつは大きく二回うなずいた。私はわざと大きなため息をついてあげる。
「なくしちゃったんならしかたないわね。私のに決まり」
あいつは大きく二回首を横に振った。
「悪いひと。言葉を話せない振りしてたのね」
あいつは一段と口をとがらせて、首をまた横に振った。
「私には聞こえるのよ、あなたの声が、そのしぐさから」
「……マリアンヌ、君は僕を知っていると言い、すぐさま知らないと言う。君は僕に触れながら、遥か彼方にいると言う」
「いいえフェルディナン。あなたの目からは言葉が聞こえなかった、ただそれだけだわ」
「ああ。言葉、いや、表現は発信と受信の両者が互いにイメージに働きかけなければ成立しないものだ。僕たちを分け隔てているものは、なんだ?」
「きっと……愛、よ」
「愛が二人を結びつけ、そして隔てている……」
「そう。空の青と私とのあいだには『空の青』があるわ。だから、もう、行かなくちゃ」
「あ、あ、あ、ちょ、ちょっと」
あいつは手をのばして私をとめた。
「なあに?」
「あ……結局、GUUのマグカップに……すんの?」
私ははっきりうなずいた。
「いやー、こっちの方がいいって。だってさ、これのほうが……ほら、コーヒーの色に合ってるしさ、それに……」
あいつの説明がえんえんと続く。マジメに聞いてると、だんだんめんどくさくなってくる。奥に見える棚がだんだん気になってくる。
棚のいちばんうえの段に、大きなサラダボウルが重ねられておかれてる。ガラス製、木製、プラスチック製。そのとなりは……あー、もう。あいつの顔がじゃまで見えない。
「……だからね、こっちのほうが……」
「いいよ、それで」
「え?」
「BAKAのやつにしよ?」
「いや、あの、ちょ、ちょっと待ってよ。そう言われるとGUUのやつがいいかなーなんて思ったりして」
「なあにー? どっちなのー?」
「い、いやあー……そっち」
ほんとにバカだ。
混雑するお店をぐるぐる回りつくしたころ、あいつの持つ買い物カゴはいっぱいになってた。
うちに二個目のワインオプナー、コーヒーの木、木製のサラダボウル、新しいALの遠出用のカゴ、ローソク、麻の人形。結局、マグカップは二つ買うことになった。
レジにできた行列の向こうで、AKIさんはいっしょうけんめい会計してる。私たちは行列に並びながら、カウンターに並べられたおもちゃで遊ぶ。
変装グッズ、アメリカンクラッカー、動かすと交尾するサルのキーホルダー。あいつは何度も何度も交尾させて、めちゃめちゃうれしそうにはしゃいでる。
「うれしいのー?」
あいつは笑顔でうなずく。
「よかったねー」
大きくうなずく。
私たちの番がきて、AKIさんはちょっとほっとした顔をした。ヒタイが汗で少し光ってる。もう一人の店員の女の子は棚のものを整理したり新しく並べたりしてる。タイヘンだー。
レジを打ちながら、AKIさんは他のお客さんに聞こえないようにささやいた。
「安くしとくねー」
「ありがとー」
私たちも小声で答える。お金を払って黄色い袋に入れてもらう。
「YASUKOちゃん、こんど電話するね」
「うん」
「AKIさん、がんばってね」
AKIさんは小さくうなずいた。
「じゃあ、またねー」
AKIさんの振る手が、次のお客さんの背中で見えなくなった。行列は続いてる。
「AKIさん、かわいそう」
「日曜だからねえ」
「ちがうよー。日曜はなんにもわるくな、い……」
振り返ると、町は金色の光だった。ビルも道も街路樹も看板も車も人も、あいつも私の体も。坂の頂上にあるまぶしい光を手でさえぎると、ビーズのブレスレットが一瞬きらめいた。
「GUU、これー、結構重いよー」
あいつは荷物を逆の手に持ちかえた。
「帰るー?」
「う、うん。そうしてしまおう」
私の頭にサンダルがよぎった。でも、しかたないかあー……ん? あー!
「ねえ見てー!」
道路をはさんで向こう側のお店のウインドウに、カッコいいロングドレスが飾られてる。
ワインレッドで、ソデがなくて、胸が深く開いてて、長いスリットが入ってて、シルエットがめちゃめちゃカッコいい。
「ちょっと見ていいー?」
「たぶん、むちゃくちゃ高いよー?」
「いーいーかーらー」
道路をわたって近くで見ると、大きな花柄が薄く入ってる。私がこのドレスを着てる姿を想像してみた。きゃー。カッコいいー。
「やっぱり、高いねえー」
「決めた。私、ノーベル文学賞の授賞式はこれを着てあいさつする。だから、それまでだれにも買われないで待っててねー」
「それまでって、いつだ?」
あいつは両手で荷物を持ってまぶしそうにしてる。
「夏、かなあー」
「……夏、ねえー」
坂をくだる私たちの先に、足長な私たちの影が歩いてる。両手を広げてみる。翼に羽のない鳥になった。あいつも荷物を持ったまま翼を広げる。オモリを縛りつけられた翼。
ふらふら左右に走る。二羽の飛べない鳥の助走。羽のない身重な鳥。スピードがあがる。金色の歩道。まっ黒な影。
「ねえ! 言葉って、なんなのー!」
「もやもやを閉じ込めた、鍵付きの宝箱!」
カーブの終わりで息をきらす。あきらめる。
「音楽も? 写真も? 絵も? 映画も? 服も? 化粧も? 料理も? ケーキも?」
「そう。みんな、そう」
遠回りしてビルの谷間を歩いてく。日陰のツタの細道。放置されてサビついた自転車の陰から汚れたノラ猫が私を見てた。枯葉色のこのカベにも、少しずつ緑が戻ってきてる。耐えられなくなってしゃがみこむと、頭上に青とも黒とも言えない細い空が見えた。
あいつは言った。
「人は生かされ、生きさせられているんだ」
私はノラ猫を見つめながら、今夜のことを考える。
ソウルミュージックに包まれながら、あいつとALと三人で、ゆっくり話して、ゆっくり黙って、ゆっくり見つめあったら、ゆっくり抱きあって、ゆっくりキスして、ゆっくり眠る。
だって、それが「休日」でしょ?