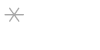MICROMANCE
1998年 木戸隆行著
4
雨が降ってる。屋根にパラパラ雨の音。闇夜に白く雨脚がシトシト静かに浮かんで消える。くもって流れる窓ガラスには淡い私が映ってる。どこにいるんだろう。あいつはまだ、帰らない。
明日はみんなでお花見なのに。
黄色いワープロに向かいながら、私はいったいだれにこの言葉を向けてるの? あなたにじゃない。あいつにじゃない。私にじゃない。ゴミ箱に。
おととい、あいつと大ゲンカした。
その夜、私とALはあいつの帰りを「おかえりー」って出迎えた。あいつはただいまも言わず靴を脱いだ。いつもより三時間遅い、十時だった。
「どうしたのー?」
あいつは黙ったまま。私と目もあわせずにソファーに座り込んだ。めったに見ないテレビをつけて、タバコを吸う。
私がもう一度「どうしたの?」って聞いた。あいつはテレビを見つめたまま「ちょっとほっといてよ」ってつぶやいた。
私はだんだん不安になってきて、あいつの背中に抱きついてみた。
「どうしたのー!」
あいつは本気で私のウデを振り払った。
「べたべたすんなよ!」
頭にきた。
「べたべたすんなよって……抱きつくのをやめたときから、人はほんとに孤独になるんだよ? そんなこともわからないの!」
「頼むからほっといてくれよ!」
「なんなの! ひとがせっかく心配してあげてるって言うのに!」
あいつは黙り込んでタバコをふかした。
「そうやって黙る! バイトでなにがあったのか知らないけど、そんなのうちに持ち込まないでよ!」
「バイトじゃねーよ」
「じゃあなんなのー!」
「別になんでもいいじゃん……関係ないだろ」
「関係ないならそんな顔して帰ってこないでよ!」
あいつはプイッとすると、それきり口を閉じた。こうなったらいつものパターン。
私がキーってなればなるほど、あいつは黙り込む。その態度がますます頭にきて、私はめちゃくちゃになる。怒って怒って怒って。だんだん涙が出てきて、鼻水もたれてくる。それでも怒るのをやめない。
そのうち、自分がどうして怒ってるのかわからなくなってくる。それでも意地で怒り続ける。疲れて眠るまで。
次の日、私はさわやかな気分で目を覚ます。私はめちゃめちゃ笑ってる。ケンカを次の日に持ち越すのは嫌い。お母さんに「あんたはニワトリみたいな子ね。三歩あるくともう笑ってる」って言われたくらい。
「ガチャ、ザーッ、ガチャ」
あいつが帰ってきた。時計は十二時を回ってる。ALはすぐに玄関に走ってった。私も暖かく出迎えてあげる。
「ちょっと! 遅くなるなら電話ぐらいしてよ!」
やっぱりあいつは目をそらしたまま黙ってる。雨に濡れたクツを脱いで私を通り過ぎると、ソファーに座ってテレビをつけた。
私は部屋の入口で腰に手をあてて立った。ドス黒いオーラをまわりに漂わせながらタバコをふかすあいつを眺めてたら、ため息が出た。
「はあー、どうしたものかー。その気持ちは、しつこい大臣の君にしかわからないよー」
それでもあいつは黙ったまま。もう、ほんとにしつこいんだから。
あいつのしつこさはケンカのときだけじゃない。去年、ブーツィーのライブに行ったときだってそう。
あいつは帰ってくるなり目をうるませて、ライブの感動を情緒たっぷりに語りはじめた。遅い夕食を食べながら、お風呂からあがって続きを話し、ベッドのなかでも語ってた。私は眠気に襲われながら、くり返されるあいつの話題にうなされてるみたいにウンウンうなずいてあげた。
二ヵ月後、そのライブのビデオが出た。あいつはバイトを休んで買ってきて、何度も何度も見続けた。くり返される巻き戻し音。
私が「寝るよー」って電気を消しても「もう一回」。あいつはまっ暗な部屋でテカテカテレビを光らせて黙ってじいっと見入ってた。
次の日も、またその次の日も、あいつはバイトに行って帰ってくると、お菓子を片手にくり返す。私が「まだ飽きないのー?」って聞いても「もう一回」って答えるだけ。
その生活を二週間も続けたあいつの頭のなかがどうなっていたのか、私には到底わからない。
もしかしたら虹のスパイラルがまっ黒な宇宙で絡まりながら渦巻いてたのかもしれないし、四つの太陽がのぼったり沈んだりしてたのかもしれない。
それは外から見ててもわからない。いまだってそう。あいつの頭のなかがどうなってるのか、私にはちっともわからない。
だから、そんなときは抱きついてみるの。
手をつないだり、しがみついたり、キスしてみたり。そうすると、私の体にあいつの形が伝わってくる。あいつのカタさが伝わってくる。あいつの温かさが伝わってくる。あいつの気持ちが伝わってくる。私もあいつに伝わって、やっと二人はわかりあう。
それなのに、あいつは抱きつくことを禁止して、私はもうお手上げダー。
電話がなった。あいつはやっぱり黙ってる。私はため息をついて受話器をとった。お母さんだった。
「はい」
「あ、やっちゃん? お母さんよ」
「うん」
あいつがタバコをもみ消した。
「どうしたの? 元気がないわね」
「うん、ちょっと」
「ちょっと、なんなの?」
ALがあいつのヒザに跳びのった。
「うん……あのね……いま、BAKAとケンカちゅうなの」
「あら……もしかして、邪魔しちゃった?」
「ううん、いいの。それよりどうしたの? こんな遅くに」
「え? あ、そうそう」
パキラの新芽にちっちゃな葉っぱが開きかかってる。かわいいなー。ちゃんと五枚。
「あのね、庭の桜が満開で、もう、本当に奇麗なのよ。白い花が枝いっぱいに開花してね、そうね、まるで大粒のぼたん雪が空に留まっているみたいなの。それでね、真下から見上げると、桜の花びらに透き通った微妙な光が真っ青な空と一緒にお母さんの額で揺れるの。お母さん、洗濯物を干してる最中だったけど、思わず木の下で佇んで、いつの間にかレジャーシートを敷いてお昼寝しちゃってたわよ」
「いいなあー、私もお昼寝したーい」
振り返ると、ALがあいつのヒザで眠ってた。
「あら、明日家に来ればいいじゃない、聡君も連れて」
「だって、あいつ、口もきいてくれないんだよー?」
「またやっちゃんが駄々をこねたんでしょう?」
「ちがうよー。私なんにも悪くないもん」
あいつはテレビのリモコンを手にとって、チャンネルを変えようとして、やめた。
「喧嘩って言うのはねえ、どちらか一方だけが悪いことなんてないのよ。お互いに我を突き付け合うから起きるものなの。特に好きなもの同士は喧嘩になりやすいものよ。それはね、怒りというものが焦りから始まるからなの。分かる? 自分に都合のいいように立てた予定が、狂うことから始まるのよ。聡君のことが好きなんでしょう? だったらもっと優しくしてあげなさい?」
「やさしくしてるよー。どうしてお母さん、BAKAに味方するのー?」
「味方なんてしていないわよ。ただね、やっちゃんが後で後悔しないように……」
あいつがリモコンを私の黄色いワープロにおいた。
「あ……そうだ、お母さん」
「なあに?」
「私ね、フフフ、ついに小説書きはじめたのー!」
「……」
「それでね、いま……百ページくらいかなあ、BAKAもALもKIDOくんもAKIさんも、そしてなあーんと、お母さんも出てくるんだよー」
「……」
「そーれーでー、六月には完成させてー、新人賞に、応募するの! すごいでしょー?」
「……」
「……ん? どうしたの? あー、ひょっとしてお母さんいま、モモのところくるくるなぞってるでしょー?」
お母さんは電話の向こうで長い長いため息をついた。
「はあーーーーー。やっぱり、あれは、本気、だったの、ね」
「うん」
私は冷蔵庫をあけてミルクをとり出した。
「はあー……やっちゃん、あなた本を読んだことあるの? お母さん、あなたがオムツしてるころから見てるけど、本を読んでいる姿を一回も見たことがないわよ?」
「だ、い、じょーぶ」
ミルクを一口飲んだ。結構冷えてる。がんばったねーって冷蔵庫をなでてあげる。
「大丈夫って、あなた……小説ってなんだか分かっているの? 小学生の作文じゃないのよ? まあ、あなたは言い出したら聞かない子だからなにを言っても無駄なんだろうけど、もう二十六にもなるんだから、少しは考えて行動しなさい?」
「んー……」
「それじゃあもう遅いから切るわね? 早く聡くんと仲直りしなさい? いーい? それじゃあね」
ガチャン、プーッ、プーッ……切れた。
「しなさい」の連続。なんだか子供に戻ったみたいな嫌な気分。でも「二十六」って数字がお母さんの言葉に説得力を持たせるのだー。
あーあー。私はミルクを冷蔵庫に戻した。
小学生の作文じゃない、かー。きっと私の小説のことを言ってるんだろうなあー。
でも、中学生の作文だったら小説なのかなあ? それとも高校生、大学生、専門学校生? じつは、もっと年上の、七十、八十の人の作文のことだったりして。イジワルな私。
でも……ねえ、小説ってなんなの? 私が書いてるのは小説じゃないの? どうなの? ねえ……なんて、あなたに聞いてもダメだよね。だって未来のあなただから。
他に教えてくれそうな人って……あぁぁー。あいつだけだー。
あいつはあい変わらずソファーに座って、黙ってテレビを見つめてる。ヒザではALがまるくなって眠ってる。ローテーブルにおかれた灰皿から、細い煙が立ちのぼってる
ALが寝返りをうってあいつのヒザから落ちそうになった。あいつはそれを押さえて引き寄せると、灰皿のタバコに手をのばした。見つめる私と目があった。
あ……いまだー!
「あー、あのー……BAKAさん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけどー」
あいつは目をそらした。でもまだ聞いてるみたい。
「小説って……ううん、芸術ってなんなのか、教えてください。一生……今年最大のおねがい。ねえー。教えてくれたら、また黙ってもいいからー」
あいつはタバコをふかして黙ってる。こうなったら奥の手だー。
「愛と仕事のためには出し惜しみ、しないんでしょー?」
「……だよ」
つぶやくようなあいつの声。しばらくしてなかった話すという動作を思い出しながら、探りながら、おそるおそる話したみたいな細い声。もちろん私は聞きのがしてた。
「BAKAせんせい、もう一度おねがいします」
あいつはタバコを灰皿において、自分のバッグに手をつっ込んだ。
「せ、か、い。それ自身の時間と空間とを持つもの」
あいつはごそごそバッグからブ厚い本をとり出すと、パラパラめくって、とめた。
「どちらか一方しか持たないものは実用だ。芸術は自ら運動し、かつ広がりをも持たなければならない。その際、時間がゼロでも無限大でもない速度に留まるよう、細心の注意を払う必要がある。なぜなら速すぎる速度は空間を失うからだ」
「……」
「写真芸術においては対象に構図的静止を要求すべきではなく、むしろ自然運動の切片でなければならない。文物芸術においても同じことが言える。情報は時間を持たず、論は空間を持たない。つまりそれは完全なる客観でも完全なる主観でもなく、主観中の客観、客観中の主観であり、矛盾した両者の統合である」
「……」
「見ろ。受け手に時間感受能力を要求する写真、絵画を。空間感受能力を要求する古典音楽を。両者を要求する小説を、より強く詩を。受け手と同じ時空で行われ、それ自身の時空に飛び立つことの困難な演劇を。それらは折衷された現代音楽に押され、より映画に押されて風前の灯だ」
「……」
「しかし芸術家よ! 人は三次元に留まったままだ。芸術はさらに上位次元、つまり四次元世界へと到達しなければならない。それは果てのない空であり、底のない地であり、精神の形容を越えた形態である。無限の有であり、同時に無である時空。そこにこそ、最上の芸術があるのだ」
「……」
あいつは本を閉じて、となりにおいた。
「さっき、古本屋で買った」
「……だから、遅くなったの?」
あいつは灰皿においたタバコに手をのばしながら首を横に振った。
「まだ、怒ってるの?」
あいつはまた首を横に振った。
「じゃあどうしてまた黙るの?」
あいつはタバコをくわえて灰皿に目を落とすと、そのまま動かなくなった。タバコの先からのびる煙が、あいつの髪の表面を流れてのぼってく。
「……あのさ」
ALのお腹がゆっくり動いてる。
「ドラムのやつ、クビにするとか、言ってただろ」
「うん」
「それが……代わりやることになってたやつが、急に『できない』って言いだしてさ」
「うん」
あいつはタバコを光らせた。煙を吸い込むオレンジ色の光。光が消えて、煙がのぼる。あいつの口からあふれ出す。
「それで、他のドラム、探してんだけど、なかなかああいうドラム叩けるやつって、少なくてさ」
「うん」
あいつは灰を落とした。
「今更、前のドラムのやつに『やっぱりやってくれ』とも言えないし」
「うん」
灰を落としたタバコをじっと見つめて、また、くわえる。
「それで、さっきまでホーンのやつと話してて」
「うん」
あいつはため息みたいに煙をはいた。
「このままだと、自然解散みたいになるかもしれない」
はいた煙はふくらんで、薄まって、漂った。
「……ドラムなしじゃ、ダメなの?」
あいつはむせた。
「ゴホゴホッ……だーめだよー」
ちょっと笑った。やっと、笑った。
あいつはタバコの灰を落として、ヒザで眠るALを見つめて、なでた。ALは目をつぶったまま耳だけぴくぴく動かした。
「それで、黙ってたの?」
テレビから「ワハハ」と笑い声がする。
「考えてただけだよ」
「じゃあなんで私をムシするの?」
あいつは顔をあげて、まともに私を見つめた。瞳で光るクリップライト。
「……いまはー、してないけどー、さっきまでー……」
あいつは両目をさらに大きく見開いた。白目がいっぱい。まばたきしないで私を見つめる。じっと、じっと……
「わかったー、もう言わないからー」
あいつは見開いた目をもとに戻した。消そうとするタバコを追う目がやさしくゆるんでる。くもった窓にあいつの背中が映ってる。雨音がやんでる。やっと、あがったみたい。
「じゃあ、もう、仲直りー?」
「んー」
あいつはALをソファーに移して立ちあがった。
「あーよかったー。明日のお花見、どうしようかと思ってたんだからー」
あいつはテレビを消して、しゃがんで、レコードを選んでる。
「あ、そうか、明日かー」
「なあにー、忘れてたのー?」
レコードをプレーヤーにのせて針を落とす。
「いや……はい」
アレサが静かに歌いだす。
そう。明日の日曜日はガーデンプレースの近くの公園でお花見。私とあいつとKIDOくんとAKIさんとMANABUさんとMIKAちゃんとMONKEY、ぜんぶで七人で。
私はタバコに火をつけた。くもった窓を手で拭いた。もくもく黒い雲の切れ間から、まっ白な月がのぞいてる。満開の桜が暗闇に白く浮かびあがってる。きっと、明日は晴れだ。
「ねえ」
「あん?」
あいつはボリュームをあげた。部屋じゅう音で満たされる。
「明日はお弁当作らなくちゃいけないから、早起きするんだよー」
「何時?」
ALがうるさそうに目を開けて、顔をあげて、また眠った。
「待ちあわせが一時だから……九時くらい?」
あいつはALの顔色を見ながらボリュームをあわせて、リズムをとりながらソファーに座る。
「場所取りはどうすんの?」
「あ、そうかー。じゃあ……六時?」
「六時?!」
そんなに驚かなくてもいいのに。あいつはビデオデッキの時計を見た。
「二時?!」
あいつは一気に立ちあがった。
「GUU、寝よう!」
あいつは鼻息を荒くしてそう言うと、ずんずん歩いてレコードをとめた。
カチャ。
とつぜん消えた曲。とつぜんあらわれた静寂、そして私。なんとなく、切ない。
「……寝れるの?」
私の声が響いた。
あいつは上着を脱ぎながら「寝、る、のー!」とさけんでとなりの部屋に消えてった。ソファーに残されたまるいAL。ブ厚い本。黄色い、私の、ワープロ。
私はALの寝顔にしゃがみ込み、おやすみのキスをした。かわいいなー。ちっちゃくイビキをかいてる。私は立ちあがって電気を消す。
パチ。
窓から月が飛び込んだ。姿をあらわした月光、澄んだ闇。遠い、遠い、切ないもの。
青白いソファー。青白いAL。青白いローテーブル。青白い床。青白いカベ。青白い部屋。青白い、私。
青白い足が交互に歩く。タバコの赤が一瞬光る。消える。煙る。汚れる。歩く。過ぎる。私はベッドのまえに立つ。あいつは目をつぶってる。
「ねえ、もっと向こう行ってー。私の場所ー」
「んー」
あいつはごろんと回ってどけた。私はタバコの灰が落ちないようにゆっくりとベッドにもぐった。あいつが目を開けた。やっぱり眠れないみたい。
「なんだか一緒に寝るの、めちゃめちゃ久しぶりのような気がする」
「そうかー?」
「そうだよー」
私は枕もとの灰皿でタバコを消した。
この二日間、あいつと私は別々に寝てた。あいつがソファーで私はベッド。毎日は嫌だけど、たまにはこういうのもいいかもって思った。
だって、ベッドに入って両手と両足を思いきりのばした瞬間「一人で寝るってこーんなに気持いいものだったのかあー」って感動したの。
「そう言えばGUU、さっきの電話、誰だったの?」
あいつはタバコをとり出してくわえた。
「お母さん」
ライターがあいつの顔を照らした。
「なんて、言ってた?」
光が消えて、タバコの赤が残る。強く光って、弱まる。
「あのね、実家の庭の桜が満開で、もーめちゃめちゃキレイなんだって。お母さん、あまりのキレイさにお昼寝しちゃったみたいで、私が、いいなーって」
「なんだそれ」
タバコの赤がまた光る。
「あ、それでね、最後にお母さん、はやくBAKAと仲直りしなさい、って言ってたよ。よかったねー。これでお母さんたちとも仲直りじゃない?」
「んー……仲直りって言うか……俺とGUUの両親は憎み合ってケンカしてるわけじゃないからねえ」
あいつは灰皿に灰を落とした。
「じゃあ、どうしてすぐに仲直りしないのー?」
「どうしてって……うーん……なんて言うか、一度出しちゃったものはすぐに引っ込められない、みたいな変な意地を張っちゃっててさ……それに、ケンカしてても、お互い大して困ることもないし……」
あいつは煙をはき出した。
「どうでもいい、ってことー?」
「どうでもいいわけじゃないけど……なんて言うかさ、それぞれがGUUと繋がってさえいれば、お互い、それでいいわけで……『いいとも』みたいに友達の友達は自分の友達かもしれないけど、友達の親は自分の親じゃないし、子供の友達は自分の子供じゃないって言うか……んー」
あいつは吸ってたタバコを私に手わたした。
「でも、私とBAKAは『友達』じゃないでしょー?」
「それはそうだけど……んー……あー、あれかもなー。どっちもさ、自分とGUUとの関係に誰かが入ってくるのが嫌なんだよ、きっと」
私は受けとったタバコを吸って、はいた。
「……君たち、そーんなに私を独占したいのー?」
「はっ」
あいつは口を開いたまま動かなくなった。
「しかたない、手をつないであげる」
私は手を差し出した。あいつはじっと動かない。
「なあに? 嫌ならいいんだよー?」
ひっ込めようとしたら、あいつが手をのばした。触れて、握りしめた。ごつごつして、大きい手。
「繋ぎたい」
「どうぞ」
横になった二人のあいだで交差する二本のウデ。その先で握りあう二人の手。ウデを曲げて、つないだ手を顔に近づける。絡みあった指と指。なんだか不思議。私の手じゃないみたい。そこだけ別の生き物みたい。
指を動かしてみる。親指、人差し指、中指、薬指、小指。ちゃんと動く。でもやっぱり私の手じゃない。
「なにしてんの?」
あ、そうか。私の、じゃなくて、二人の、なんだー。
「んーん、なんでもない。おやすみ」
枕もとの灰皿にタバコを押しつけると、赤い光が砕けて、消えた。
「……おやすみ」
窓からのびた青白い光が部屋を貫いてる。黒の濃淡でわかるあいつの形。肌の感触でわかるあいつの形。
「俺さ、GUUといると……」
あいつがささやいた。
「いると?」
「いると……なんて言うか……安らぐんだよ」
青白い天井。
「それだけ?」
「それだけ、って?」
ぶらさがったライト。
「安らぎをあげたり、もらったり、そんなの簡単でしょ? 私なんて、毎日ドキドキしたり、コゲちゃったりしてるんだよ?」
あいつの横顔。天井を見あげてる。
「……それを言うなら、俺だって、シューってなったりバーンってなったりしてるよ」
「きゃー」
あいつの胸に抱きついた。かたい胸。かたいウデ。かたいあいつが私をぎゅっと抱きしめる。
あいつの鼓動に包まれる。あいつの温かさに包まれる。あいつの匂いに包まれる。あいつの愛でいっぱいになる。そして私の鼓動が、温かさが、匂いが、愛が、あいつを包む。二人の体は触れあう部分をとかしあいながら流動する。
「人は全身で物を見るんだよ」
「知ってる」
あいつの手が私のくるくるの髪をなでた。
「物が見えるのは、すべてが球だからなんだよ」
「知ってる」
あいつの指が私の顔に触れた。
「すべての球は引力でくっついてるんだよ」
「知ってる」
あいつの手が私の頬を包み込んだ。私の目がとけるみたいに閉じた。
「隙間なく球がくっつっくと、より強い、結晶になるんだよ」
「愛、の?……」
唇に私のすべてが集まる。私は私のすべてであいつを受けとる。あいつの柔らかさを、強さを受けとる。
あいつの唇が移動する。私のすべても移動する。額に、まぶたに、頬に、首筋に、胸に。動き回りながら私のすべてはだんだん凝縮される。凝縮されて、光りだす。光はさらに小さくなり、さらに強く輝いてく。
私のすべてはひとつのまぶしい光の点になる。そして、その輝きがすべてを純白に照らした瞬間、光の点は瞬き、粉々に飛び散る。どこからか私の体があらわれる。光の空に投げ出され、ふわふわ漂う。ふわふわ、ふわふわ。
はるか遠くからあいつの声がする。優しい、暖かい声。私は光に包まれ、あいつの声に包まれる。そのうち光はゆっくり消えだして、あいつのささやきは近くなる。まだ、戻りたくないなあー。そして光は闇になる。
私の体が闇のなかで風船のようにぐんぐん膨らみだす。気持ち悪いくらいはやく、ぐんぐん、ぐんぐん。あーあ、そして、いなくなった。目を開けばあいつが迎えてくれる。
「やべぇー、もう四時だー!」
どうでもいいのに。
雨が降ってる。屋根にパラパラ雨の音。闇夜に白く雨脚がシトシト静かに浮かんで消える。くもって流れる窓ガラスには淡い私が映ってる。どこにいるんだろう。あいつはまだ、帰らない。
明日はみんなでお花見なのに。
黄色いワープロに向かいながら、私はいったいだれにこの言葉を向けてるの? あなたにじゃない。あいつにじゃない。私にじゃない。ゴミ箱に。
おととい、あいつと大ゲンカした。
その夜、私とALはあいつの帰りを「おかえりー」って出迎えた。あいつはただいまも言わず靴を脱いだ。いつもより三時間遅い、十時だった。
「どうしたのー?」
あいつは黙ったまま。私と目もあわせずにソファーに座り込んだ。めったに見ないテレビをつけて、タバコを吸う。
私がもう一度「どうしたの?」って聞いた。あいつはテレビを見つめたまま「ちょっとほっといてよ」ってつぶやいた。
私はだんだん不安になってきて、あいつの背中に抱きついてみた。
「どうしたのー!」
あいつは本気で私のウデを振り払った。
「べたべたすんなよ!」
頭にきた。
「べたべたすんなよって……抱きつくのをやめたときから、人はほんとに孤独になるんだよ? そんなこともわからないの!」
「頼むからほっといてくれよ!」
「なんなの! ひとがせっかく心配してあげてるって言うのに!」
あいつは黙り込んでタバコをふかした。
「そうやって黙る! バイトでなにがあったのか知らないけど、そんなのうちに持ち込まないでよ!」
「バイトじゃねーよ」
「じゃあなんなのー!」
「別になんでもいいじゃん……関係ないだろ」
「関係ないならそんな顔して帰ってこないでよ!」
あいつはプイッとすると、それきり口を閉じた。こうなったらいつものパターン。
私がキーってなればなるほど、あいつは黙り込む。その態度がますます頭にきて、私はめちゃくちゃになる。怒って怒って怒って。だんだん涙が出てきて、鼻水もたれてくる。それでも怒るのをやめない。
そのうち、自分がどうして怒ってるのかわからなくなってくる。それでも意地で怒り続ける。疲れて眠るまで。
次の日、私はさわやかな気分で目を覚ます。私はめちゃめちゃ笑ってる。ケンカを次の日に持ち越すのは嫌い。お母さんに「あんたはニワトリみたいな子ね。三歩あるくともう笑ってる」って言われたくらい。
「ガチャ、ザーッ、ガチャ」
あいつが帰ってきた。時計は十二時を回ってる。ALはすぐに玄関に走ってった。私も暖かく出迎えてあげる。
「ちょっと! 遅くなるなら電話ぐらいしてよ!」
やっぱりあいつは目をそらしたまま黙ってる。雨に濡れたクツを脱いで私を通り過ぎると、ソファーに座ってテレビをつけた。
私は部屋の入口で腰に手をあてて立った。ドス黒いオーラをまわりに漂わせながらタバコをふかすあいつを眺めてたら、ため息が出た。
「はあー、どうしたものかー。その気持ちは、しつこい大臣の君にしかわからないよー」
それでもあいつは黙ったまま。もう、ほんとにしつこいんだから。
あいつのしつこさはケンカのときだけじゃない。去年、ブーツィーのライブに行ったときだってそう。
あいつは帰ってくるなり目をうるませて、ライブの感動を情緒たっぷりに語りはじめた。遅い夕食を食べながら、お風呂からあがって続きを話し、ベッドのなかでも語ってた。私は眠気に襲われながら、くり返されるあいつの話題にうなされてるみたいにウンウンうなずいてあげた。
二ヵ月後、そのライブのビデオが出た。あいつはバイトを休んで買ってきて、何度も何度も見続けた。くり返される巻き戻し音。
私が「寝るよー」って電気を消しても「もう一回」。あいつはまっ暗な部屋でテカテカテレビを光らせて黙ってじいっと見入ってた。
次の日も、またその次の日も、あいつはバイトに行って帰ってくると、お菓子を片手にくり返す。私が「まだ飽きないのー?」って聞いても「もう一回」って答えるだけ。
その生活を二週間も続けたあいつの頭のなかがどうなっていたのか、私には到底わからない。
もしかしたら虹のスパイラルがまっ黒な宇宙で絡まりながら渦巻いてたのかもしれないし、四つの太陽がのぼったり沈んだりしてたのかもしれない。
それは外から見ててもわからない。いまだってそう。あいつの頭のなかがどうなってるのか、私にはちっともわからない。
だから、そんなときは抱きついてみるの。
手をつないだり、しがみついたり、キスしてみたり。そうすると、私の体にあいつの形が伝わってくる。あいつのカタさが伝わってくる。あいつの温かさが伝わってくる。あいつの気持ちが伝わってくる。私もあいつに伝わって、やっと二人はわかりあう。
それなのに、あいつは抱きつくことを禁止して、私はもうお手上げダー。
電話がなった。あいつはやっぱり黙ってる。私はため息をついて受話器をとった。お母さんだった。
「はい」
「あ、やっちゃん? お母さんよ」
「うん」
あいつがタバコをもみ消した。
「どうしたの? 元気がないわね」
「うん、ちょっと」
「ちょっと、なんなの?」
ALがあいつのヒザに跳びのった。
「うん……あのね……いま、BAKAとケンカちゅうなの」
「あら……もしかして、邪魔しちゃった?」
「ううん、いいの。それよりどうしたの? こんな遅くに」
「え? あ、そうそう」
パキラの新芽にちっちゃな葉っぱが開きかかってる。かわいいなー。ちゃんと五枚。
「あのね、庭の桜が満開で、もう、本当に奇麗なのよ。白い花が枝いっぱいに開花してね、そうね、まるで大粒のぼたん雪が空に留まっているみたいなの。それでね、真下から見上げると、桜の花びらに透き通った微妙な光が真っ青な空と一緒にお母さんの額で揺れるの。お母さん、洗濯物を干してる最中だったけど、思わず木の下で佇んで、いつの間にかレジャーシートを敷いてお昼寝しちゃってたわよ」
「いいなあー、私もお昼寝したーい」
振り返ると、ALがあいつのヒザで眠ってた。
「あら、明日家に来ればいいじゃない、聡君も連れて」
「だって、あいつ、口もきいてくれないんだよー?」
「またやっちゃんが駄々をこねたんでしょう?」
「ちがうよー。私なんにも悪くないもん」
あいつはテレビのリモコンを手にとって、チャンネルを変えようとして、やめた。
「喧嘩って言うのはねえ、どちらか一方だけが悪いことなんてないのよ。お互いに我を突き付け合うから起きるものなの。特に好きなもの同士は喧嘩になりやすいものよ。それはね、怒りというものが焦りから始まるからなの。分かる? 自分に都合のいいように立てた予定が、狂うことから始まるのよ。聡君のことが好きなんでしょう? だったらもっと優しくしてあげなさい?」
「やさしくしてるよー。どうしてお母さん、BAKAに味方するのー?」
「味方なんてしていないわよ。ただね、やっちゃんが後で後悔しないように……」
あいつがリモコンを私の黄色いワープロにおいた。
「あ……そうだ、お母さん」
「なあに?」
「私ね、フフフ、ついに小説書きはじめたのー!」
「……」
「それでね、いま……百ページくらいかなあ、BAKAもALもKIDOくんもAKIさんも、そしてなあーんと、お母さんも出てくるんだよー」
「……」
「そーれーでー、六月には完成させてー、新人賞に、応募するの! すごいでしょー?」
「……」
「……ん? どうしたの? あー、ひょっとしてお母さんいま、モモのところくるくるなぞってるでしょー?」
お母さんは電話の向こうで長い長いため息をついた。
「はあーーーーー。やっぱり、あれは、本気、だったの、ね」
「うん」
私は冷蔵庫をあけてミルクをとり出した。
「はあー……やっちゃん、あなた本を読んだことあるの? お母さん、あなたがオムツしてるころから見てるけど、本を読んでいる姿を一回も見たことがないわよ?」
「だ、い、じょーぶ」
ミルクを一口飲んだ。結構冷えてる。がんばったねーって冷蔵庫をなでてあげる。
「大丈夫って、あなた……小説ってなんだか分かっているの? 小学生の作文じゃないのよ? まあ、あなたは言い出したら聞かない子だからなにを言っても無駄なんだろうけど、もう二十六にもなるんだから、少しは考えて行動しなさい?」
「んー……」
「それじゃあもう遅いから切るわね? 早く聡くんと仲直りしなさい? いーい? それじゃあね」
ガチャン、プーッ、プーッ……切れた。
「しなさい」の連続。なんだか子供に戻ったみたいな嫌な気分。でも「二十六」って数字がお母さんの言葉に説得力を持たせるのだー。
あーあー。私はミルクを冷蔵庫に戻した。
小学生の作文じゃない、かー。きっと私の小説のことを言ってるんだろうなあー。
でも、中学生の作文だったら小説なのかなあ? それとも高校生、大学生、専門学校生? じつは、もっと年上の、七十、八十の人の作文のことだったりして。イジワルな私。
でも……ねえ、小説ってなんなの? 私が書いてるのは小説じゃないの? どうなの? ねえ……なんて、あなたに聞いてもダメだよね。だって未来のあなただから。
他に教えてくれそうな人って……あぁぁー。あいつだけだー。
あいつはあい変わらずソファーに座って、黙ってテレビを見つめてる。ヒザではALがまるくなって眠ってる。ローテーブルにおかれた灰皿から、細い煙が立ちのぼってる
ALが寝返りをうってあいつのヒザから落ちそうになった。あいつはそれを押さえて引き寄せると、灰皿のタバコに手をのばした。見つめる私と目があった。
あ……いまだー!
「あー、あのー……BAKAさん、ちょっとお聞きしたいことがあるんですけどー」
あいつは目をそらした。でもまだ聞いてるみたい。
「小説って……ううん、芸術ってなんなのか、教えてください。一生……今年最大のおねがい。ねえー。教えてくれたら、また黙ってもいいからー」
あいつはタバコをふかして黙ってる。こうなったら奥の手だー。
「愛と仕事のためには出し惜しみ、しないんでしょー?」
「……だよ」
つぶやくようなあいつの声。しばらくしてなかった話すという動作を思い出しながら、探りながら、おそるおそる話したみたいな細い声。もちろん私は聞きのがしてた。
「BAKAせんせい、もう一度おねがいします」
あいつはタバコを灰皿において、自分のバッグに手をつっ込んだ。
「せ、か、い。それ自身の時間と空間とを持つもの」
あいつはごそごそバッグからブ厚い本をとり出すと、パラパラめくって、とめた。
「どちらか一方しか持たないものは実用だ。芸術は自ら運動し、かつ広がりをも持たなければならない。その際、時間がゼロでも無限大でもない速度に留まるよう、細心の注意を払う必要がある。なぜなら速すぎる速度は空間を失うからだ」
「……」
「写真芸術においては対象に構図的静止を要求すべきではなく、むしろ自然運動の切片でなければならない。文物芸術においても同じことが言える。情報は時間を持たず、論は空間を持たない。つまりそれは完全なる客観でも完全なる主観でもなく、主観中の客観、客観中の主観であり、矛盾した両者の統合である」
「……」
「見ろ。受け手に時間感受能力を要求する写真、絵画を。空間感受能力を要求する古典音楽を。両者を要求する小説を、より強く詩を。受け手と同じ時空で行われ、それ自身の時空に飛び立つことの困難な演劇を。それらは折衷された現代音楽に押され、より映画に押されて風前の灯だ」
「……」
「しかし芸術家よ! 人は三次元に留まったままだ。芸術はさらに上位次元、つまり四次元世界へと到達しなければならない。それは果てのない空であり、底のない地であり、精神の形容を越えた形態である。無限の有であり、同時に無である時空。そこにこそ、最上の芸術があるのだ」
「……」
あいつは本を閉じて、となりにおいた。
「さっき、古本屋で買った」
「……だから、遅くなったの?」
あいつは灰皿においたタバコに手をのばしながら首を横に振った。
「まだ、怒ってるの?」
あいつはまた首を横に振った。
「じゃあどうしてまた黙るの?」
あいつはタバコをくわえて灰皿に目を落とすと、そのまま動かなくなった。タバコの先からのびる煙が、あいつの髪の表面を流れてのぼってく。
「……あのさ」
ALのお腹がゆっくり動いてる。
「ドラムのやつ、クビにするとか、言ってただろ」
「うん」
「それが……代わりやることになってたやつが、急に『できない』って言いだしてさ」
「うん」
あいつはタバコを光らせた。煙を吸い込むオレンジ色の光。光が消えて、煙がのぼる。あいつの口からあふれ出す。
「それで、他のドラム、探してんだけど、なかなかああいうドラム叩けるやつって、少なくてさ」
「うん」
あいつは灰を落とした。
「今更、前のドラムのやつに『やっぱりやってくれ』とも言えないし」
「うん」
灰を落としたタバコをじっと見つめて、また、くわえる。
「それで、さっきまでホーンのやつと話してて」
「うん」
あいつはため息みたいに煙をはいた。
「このままだと、自然解散みたいになるかもしれない」
はいた煙はふくらんで、薄まって、漂った。
「……ドラムなしじゃ、ダメなの?」
あいつはむせた。
「ゴホゴホッ……だーめだよー」
ちょっと笑った。やっと、笑った。
あいつはタバコの灰を落として、ヒザで眠るALを見つめて、なでた。ALは目をつぶったまま耳だけぴくぴく動かした。
「それで、黙ってたの?」
テレビから「ワハハ」と笑い声がする。
「考えてただけだよ」
「じゃあなんで私をムシするの?」
あいつは顔をあげて、まともに私を見つめた。瞳で光るクリップライト。
「……いまはー、してないけどー、さっきまでー……」
あいつは両目をさらに大きく見開いた。白目がいっぱい。まばたきしないで私を見つめる。じっと、じっと……
「わかったー、もう言わないからー」
あいつは見開いた目をもとに戻した。消そうとするタバコを追う目がやさしくゆるんでる。くもった窓にあいつの背中が映ってる。雨音がやんでる。やっと、あがったみたい。
「じゃあ、もう、仲直りー?」
「んー」
あいつはALをソファーに移して立ちあがった。
「あーよかったー。明日のお花見、どうしようかと思ってたんだからー」
あいつはテレビを消して、しゃがんで、レコードを選んでる。
「あ、そうか、明日かー」
「なあにー、忘れてたのー?」
レコードをプレーヤーにのせて針を落とす。
「いや……はい」
アレサが静かに歌いだす。
そう。明日の日曜日はガーデンプレースの近くの公園でお花見。私とあいつとKIDOくんとAKIさんとMANABUさんとMIKAちゃんとMONKEY、ぜんぶで七人で。
私はタバコに火をつけた。くもった窓を手で拭いた。もくもく黒い雲の切れ間から、まっ白な月がのぞいてる。満開の桜が暗闇に白く浮かびあがってる。きっと、明日は晴れだ。
「ねえ」
「あん?」
あいつはボリュームをあげた。部屋じゅう音で満たされる。
「明日はお弁当作らなくちゃいけないから、早起きするんだよー」
「何時?」
ALがうるさそうに目を開けて、顔をあげて、また眠った。
「待ちあわせが一時だから……九時くらい?」
あいつはALの顔色を見ながらボリュームをあわせて、リズムをとりながらソファーに座る。
「場所取りはどうすんの?」
「あ、そうかー。じゃあ……六時?」
「六時?!」
そんなに驚かなくてもいいのに。あいつはビデオデッキの時計を見た。
「二時?!」
あいつは一気に立ちあがった。
「GUU、寝よう!」
あいつは鼻息を荒くしてそう言うと、ずんずん歩いてレコードをとめた。
カチャ。
とつぜん消えた曲。とつぜんあらわれた静寂、そして私。なんとなく、切ない。
「……寝れるの?」
私の声が響いた。
あいつは上着を脱ぎながら「寝、る、のー!」とさけんでとなりの部屋に消えてった。ソファーに残されたまるいAL。ブ厚い本。黄色い、私の、ワープロ。
私はALの寝顔にしゃがみ込み、おやすみのキスをした。かわいいなー。ちっちゃくイビキをかいてる。私は立ちあがって電気を消す。
パチ。
窓から月が飛び込んだ。姿をあらわした月光、澄んだ闇。遠い、遠い、切ないもの。
青白いソファー。青白いAL。青白いローテーブル。青白い床。青白いカベ。青白い部屋。青白い、私。
青白い足が交互に歩く。タバコの赤が一瞬光る。消える。煙る。汚れる。歩く。過ぎる。私はベッドのまえに立つ。あいつは目をつぶってる。
「ねえ、もっと向こう行ってー。私の場所ー」
「んー」
あいつはごろんと回ってどけた。私はタバコの灰が落ちないようにゆっくりとベッドにもぐった。あいつが目を開けた。やっぱり眠れないみたい。
「なんだか一緒に寝るの、めちゃめちゃ久しぶりのような気がする」
「そうかー?」
「そうだよー」
私は枕もとの灰皿でタバコを消した。
この二日間、あいつと私は別々に寝てた。あいつがソファーで私はベッド。毎日は嫌だけど、たまにはこういうのもいいかもって思った。
だって、ベッドに入って両手と両足を思いきりのばした瞬間「一人で寝るってこーんなに気持いいものだったのかあー」って感動したの。
「そう言えばGUU、さっきの電話、誰だったの?」
あいつはタバコをとり出してくわえた。
「お母さん」
ライターがあいつの顔を照らした。
「なんて、言ってた?」
光が消えて、タバコの赤が残る。強く光って、弱まる。
「あのね、実家の庭の桜が満開で、もーめちゃめちゃキレイなんだって。お母さん、あまりのキレイさにお昼寝しちゃったみたいで、私が、いいなーって」
「なんだそれ」
タバコの赤がまた光る。
「あ、それでね、最後にお母さん、はやくBAKAと仲直りしなさい、って言ってたよ。よかったねー。これでお母さんたちとも仲直りじゃない?」
「んー……仲直りって言うか……俺とGUUの両親は憎み合ってケンカしてるわけじゃないからねえ」
あいつは灰皿に灰を落とした。
「じゃあ、どうしてすぐに仲直りしないのー?」
「どうしてって……うーん……なんて言うか、一度出しちゃったものはすぐに引っ込められない、みたいな変な意地を張っちゃっててさ……それに、ケンカしてても、お互い大して困ることもないし……」
あいつは煙をはき出した。
「どうでもいい、ってことー?」
「どうでもいいわけじゃないけど……なんて言うかさ、それぞれがGUUと繋がってさえいれば、お互い、それでいいわけで……『いいとも』みたいに友達の友達は自分の友達かもしれないけど、友達の親は自分の親じゃないし、子供の友達は自分の子供じゃないって言うか……んー」
あいつは吸ってたタバコを私に手わたした。
「でも、私とBAKAは『友達』じゃないでしょー?」
「それはそうだけど……んー……あー、あれかもなー。どっちもさ、自分とGUUとの関係に誰かが入ってくるのが嫌なんだよ、きっと」
私は受けとったタバコを吸って、はいた。
「……君たち、そーんなに私を独占したいのー?」
「はっ」
あいつは口を開いたまま動かなくなった。
「しかたない、手をつないであげる」
私は手を差し出した。あいつはじっと動かない。
「なあに? 嫌ならいいんだよー?」
ひっ込めようとしたら、あいつが手をのばした。触れて、握りしめた。ごつごつして、大きい手。
「繋ぎたい」
「どうぞ」
横になった二人のあいだで交差する二本のウデ。その先で握りあう二人の手。ウデを曲げて、つないだ手を顔に近づける。絡みあった指と指。なんだか不思議。私の手じゃないみたい。そこだけ別の生き物みたい。
指を動かしてみる。親指、人差し指、中指、薬指、小指。ちゃんと動く。でもやっぱり私の手じゃない。
「なにしてんの?」
あ、そうか。私の、じゃなくて、二人の、なんだー。
「んーん、なんでもない。おやすみ」
枕もとの灰皿にタバコを押しつけると、赤い光が砕けて、消えた。
「……おやすみ」
窓からのびた青白い光が部屋を貫いてる。黒の濃淡でわかるあいつの形。肌の感触でわかるあいつの形。
「俺さ、GUUといると……」
あいつがささやいた。
「いると?」
「いると……なんて言うか……安らぐんだよ」
青白い天井。
「それだけ?」
「それだけ、って?」
ぶらさがったライト。
「安らぎをあげたり、もらったり、そんなの簡単でしょ? 私なんて、毎日ドキドキしたり、コゲちゃったりしてるんだよ?」
あいつの横顔。天井を見あげてる。
「……それを言うなら、俺だって、シューってなったりバーンってなったりしてるよ」
「きゃー」
あいつの胸に抱きついた。かたい胸。かたいウデ。かたいあいつが私をぎゅっと抱きしめる。
あいつの鼓動に包まれる。あいつの温かさに包まれる。あいつの匂いに包まれる。あいつの愛でいっぱいになる。そして私の鼓動が、温かさが、匂いが、愛が、あいつを包む。二人の体は触れあう部分をとかしあいながら流動する。
「人は全身で物を見るんだよ」
「知ってる」
あいつの手が私のくるくるの髪をなでた。
「物が見えるのは、すべてが球だからなんだよ」
「知ってる」
あいつの指が私の顔に触れた。
「すべての球は引力でくっついてるんだよ」
「知ってる」
あいつの手が私の頬を包み込んだ。私の目がとけるみたいに閉じた。
「隙間なく球がくっつっくと、より強い、結晶になるんだよ」
「愛、の?……」
唇に私のすべてが集まる。私は私のすべてであいつを受けとる。あいつの柔らかさを、強さを受けとる。
あいつの唇が移動する。私のすべても移動する。額に、まぶたに、頬に、首筋に、胸に。動き回りながら私のすべてはだんだん凝縮される。凝縮されて、光りだす。光はさらに小さくなり、さらに強く輝いてく。
私のすべてはひとつのまぶしい光の点になる。そして、その輝きがすべてを純白に照らした瞬間、光の点は瞬き、粉々に飛び散る。どこからか私の体があらわれる。光の空に投げ出され、ふわふわ漂う。ふわふわ、ふわふわ。
はるか遠くからあいつの声がする。優しい、暖かい声。私は光に包まれ、あいつの声に包まれる。そのうち光はゆっくり消えだして、あいつのささやきは近くなる。まだ、戻りたくないなあー。そして光は闇になる。
私の体が闇のなかで風船のようにぐんぐん膨らみだす。気持ち悪いくらいはやく、ぐんぐん、ぐんぐん。あーあ、そして、いなくなった。目を開けばあいつが迎えてくれる。
「やべぇー、もう四時だー!」
どうでもいいのに。